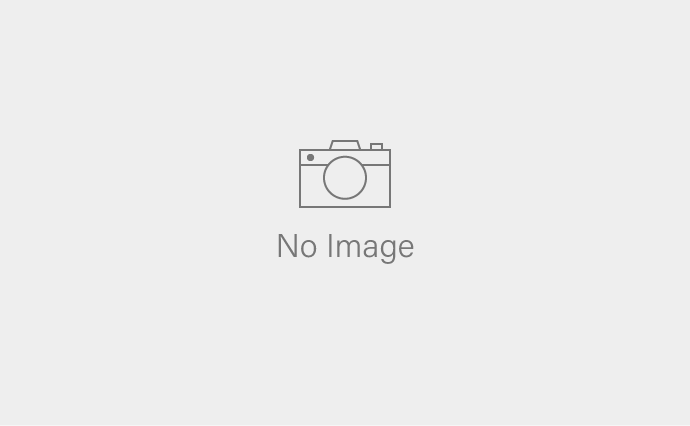中世イタリアの物語『デカメロン』はペストの流行から避難する話である。この流行は何年もかけてユーラシア大陸を横切り、物語が始まった1348年には、エジプトからヨーロッパに広まったところであった[1]。2009年のインフルエンザ・パンデミック(H1N1)はメキシコから、2020年のコロナウイルス・パンデミック(COVID-19)は中国から、あっというまに全世界に広まった。地球はもはや一つの感染システムである。
今回のテーマは世界システムである。その概念と歴史を国民国家と市場に言及しながら説明してみよう。
まずは、システムという概念に注目する。『広辞苑』によると、「複数の要素が有機的に関係しあい、全体としてまとまった機能を発揮している要素の集合体。組織。系統。仕組み。」とある[2]。ソーラーシステムは英語で「太陽系」のことで、発電装置のことではない。太陽系は単なる物体としての星々の集合体ではなく、恒星の周りを惑星が公転する、とか、惑星の周りを衛星が回る、とか「全体としてまとまった機能を発揮する要素の集合体」である。
世界システムは宇宙を含むか?、という問いはチャレンジングである。イーロン・マスクであれば、イエス、と言うであろう。しかし、彼はふつうでない。大多数の人々の意識が向かう先は地球上にかぎられる。多数決に従えば、世界システムは大気・海洋・陸から成る地球と生物を含む生態系である。人間活動に着目すれば、政治・軍事のサブシステム、経済・生産のサブシステム、そして社会・人格のサブシステムに分けられる。
国境線は宇宙からは見えないが、世界システムの理解にきわめて重要である。なぜなら、主権国家とそれらのネットワーク、すなわち国際システムこそが基本枠組みであり、世界の動きを考える際の手がかりであるからである。侵すことのできない国境が主権国家の領域をとり囲み、例外として、南極や公海といった共有地、そしてパレスチナのような線引きできないでいる紛争地帯がある。
中世には、これは違っていた。全国レベルの支配者は、狭い所領を一所懸命と守る封建領主に反抗され、不安定な存在であった。彼または彼女は宗教勢力とも権力を分かち合わなければならなかった。生産力は低く、王さえ、強大な軍隊をいつも手元に置いておけなかった。徒歩や馬での移動は妨害に遭いままならず、地の果ての安全はドラゴンや鬼などの魔物によって阻まれた。
近代では、暴力によって国土を分裂させるような反抗は常態でない。生産力は上がり、中央政府の実効支配は地の果てに及ぶ。ヒト・モノ・カネ・情報の移動を妨げる土着勢力はもはやない。
近代世界システムの概念が生まれるきっかけを作ったのは、フランス史アナール学派のフェルナン・ブロデルである。彼の『世界時間1』という本に、ヨーロッパ「世界-経済」の拡大を示す図が載っている。正距方位図法で描かれた世界地図の上に引かれた海上交易路の線は、1500年では地中海・大西洋・北海・バルト海をつなぐだけであったのが、1775年には大西洋とインド洋の一帯に伸び、中国とメキシコの間の太平洋航路も点線ながら描かれている[3]。
ヨーロッパ世界拡大のクライマックスは、新大陸の征服であった。そのテーマでは、ジャレド・ダイアモンドの『銃・病原菌・鉄』が読まれている。今のペルーにあったインカ帝国はスペイン人に滅ぼされた。168人のスペイン人にインカ軍8万人が敗れたのは、持ち込まれた天然痘、鉄の武器、そして馬のせいであった。さらなる根本原因は、ユーラシアが南北アメリカよりも動植物が多様で、面積が大きく、人口が多く、地理的な障壁が低いからであった。つまり、凶悪な病原菌への抵抗力がつき、人を乗せて戦うのに適した動物が進化できた。また、大規模な文明の誕生が早く、人々の経験が蓄積し、鉄器が発明された。ユーラシア大陸のなかでも世界の主導権を握りえたのは、政治的に統一されておらず、それゆえに文明の硬直化が起きていなかったヨーロッパ諸国であった[4]。
さて、世界システム論といえば、イマニュエル・ウォーラーステインの名前が思い浮かぶ。彼の認識枠組みは近代社会の特徴をうまく言い当てている。経済と政治をその広がりによって国民単位と世界単位に分けた。理論的には、国民経済、世界経済、国民国家、そして世界帝国の四つの類型があることになる。現実の近代世界システムは、このうち、世界経済と国民国家の組み合わせであり、国民経済として単独で存立したり、世界帝国として自己完結したりはしない。一国において不足した資源があれば、通常、世界経済のなかで、貿易によって市場をつうじ、調達される。歴史上、国民経済を拡大して帝国を作ろうとする試みがあった。しかし、ナポレオン帝国とヒトラーの「生存圏」といったものはいずれも失敗した[5]。日本の満州・モンゴルの「生命線」もそうなった。ドナルド・J・トランプのMAGAはどうであろう?
資本主義世界経済論もまたウォーラーステインの研究を魅力的にしている。他の従属論と呼ばれる学派では、先進地域と開発途上地域とに世界を二分するのが普通であるが、彼の場合は、中核、半辺境、そして辺境に三分する。生産要素や原料が生産される段階から最終生産物が売られる段階までの一連の流れを、商品連鎖というが、先進的な地域である中核と開発途上である辺境との間を半辺境が結びつけ、中核と半辺境の間、そして半辺境と辺境の間で不等価交換が発生する。マージンの大きい商品は先進的な中核で生産される。投資は利潤が目的であるから、マージンの大きい商品の生産に集まり、やがてその商品は過剰生産になり、最終的には、マージンの小さい辺境あるいは半辺境の生産物に転落してしまう。転落が起きる前に技術革新を成し遂げた地域のみが、中核の地位を維持し続ける[6]。
具体的な製品を想像すれば、世界システム論に同意できるかもしれない。白黒テレビはカラーテレビに駆逐され、カラーテレビはハイビジョンに追いやられ、ブラウン管は液晶・有機ELパネルに取って代わられた。電話では、はじめに固定電話があり、携帯電話が現れ、スマートフォンが広まった。古くなったテクノロジーでも、半辺境の国で作られ続け、安い価格で売られている。
この理論の面白いところはほかにもある。一つは半辺境という地位を設定することにより、従属論のように先進地域と開発途上地域との格差は広がる一方でないことが織り込まれたことである。1980年代から1990年代、アジアNIES(新興工業経済地域)のような新興国をうまく説明できると世界システム論は評価されたものである。それから、やはり当時、はやっていた大国の興亡論とともに、技術革新が国家の栄枯盛衰と関係あることを人々に意識させた。
再度、ブロデルに注目したい。彼は時間を三つに分けた。一つは「事件(エベーヌマン)」である。自身の言葉では「歴史的大事件と並べて、日常生活の平凡な出来事、たとえば火事、鉄道事故、小麦価格、犯罪、芝居、洪水」と表現されている。二つ目は「変動局面、重合局面(コンジョンクテュール)」である。これは1回きりの出来事ではなく、「10年、四半世紀、―中略―半世紀」にわたり、「価格曲線、人口動態、賃金動向、利率変化、生産調査―中略―厳密な流通分析」といった統計をつうじて認識される。三つ目は「長期的持続(ロングデュレ)」であり、 何世紀にもわたる。それはゆったりとした歴史の大きな枠組みであり、「構造」、「地理的束縛」、「ラテン文明」などと記述されることがある。資本主義もそうした一種の文明である[7]。
ブロデルの時間観はウォーラーステインの研究に大きな影響を与えた。特に、変動局面に相当するコンドラチェフの波に、二人とも注目した。それは経済活動の上下運動でありながら、いわゆる景気循環よりも周期が長く、半世紀を1周期とするので、長期波動とも呼ばれる[8]。
ウォーラーステインは、覇権国の交代とコンドラチェフの波とを結びつける。新しいテクノロジーの活用によって成長の波に乗った国は、世界戦争に勝って覇権国になる。覇権国は突出した海軍力によって世界貿易を支配する。やがて覇権に挑戦する国が現れるが、次の覇権が誰に帰するかは世界戦争の過程で決まる[9]。コンドラチェフの波は半世紀周期で、覇権国は1世紀が単位であるため、この相関関係を実証するだけのデータが足りない。また、フェリペ二世のスペインやルイ十四世およびナポレオンのフランスといった陸の覇者を外してよいのか?、あるいは、三十年戦争や七年戦争を覇権戦争としないのか?、といった論者による理論構成の違いがある。覇権循環論は科学と呼べるほどの緻密さはないが、興味深い歴史哲学である。
上のように近代世界システムは非常に大きな分析枠組みであり、本書の内容はほとんどそこに収まってしまう。本書は重商主義から自由主義に転換して以後を扱うが、その前史に触れておく。
大航海時代の駆動力は貴金属(金銀)の略奪と採掘であった。略奪と採掘が一段落すると、経済取引によって貴金属を得ることが目的になった。貴金属の蓄積を優先する経済政策を重商主義という。輸入を制限し、輸出を奨励すると、金貨と銀貨が手元に残る。しかし、航路と植民地は海賊と敵国に狙われるので、通商は海軍によって守られなければならなかった。軍事費をまかなうためにも、貴金属が国庫から尽きないことが必要であった。通商、海軍、そして植民地経営を総合的に行ったのが、フランスの財務大臣であったジャンバティスト・コルベールであった。
イギリスも、航海法によって貿易を規制した。第1に、輸出入は自国の船で行わなければならなかった。第2に、植民地は本国としか貿易できなかった。植民地側は反発し、アメリカ十三植民地の独立を招くことになる。第3に、高い輸入関税が課せられた。これらの保護主義政策はライバルのオランダから海軍と植民地を守るのが目的であり、自由貿易の父アダム・スミスさえ支持した[10]。
スミスの『諸国民の富』(1776年)は、重商主義の全盛期に著された。彼の自由貿易論が実現したのは七十余年後、彼の死後のことであった。一つには平和が、もう一つには国内政治の変化が必要であった。そこに至るまでの道のりは「相互依存」の回で述べる。 では、18世紀後半までは、持続可能な選択の自由に、何も進展はなかったのか? そうではない。国民国家が主役となったのは、封建領主がもはや個人を縛ることができなくなったからである。領主に個人の内面を縛る力を貸してきたローマ教会が弱体化したのが原因であった。個人の知的レベルは上がり、聖職者は人々の疑問に答えられなくなった。科学者ガリレオ・ガリレイは物理現象をよりよく説明した。個人は経済活動や娯楽に関してまで、聖職者の言うことを聴くのは窮屈であったし、国家の側は、領主と教会から権威を奪って、実効支配を強化した。ともに力を高めた個人と国家であったが、両者のバランスは時とともに変化することになる。それはこれから述べる国際政治経済の一大テーマである。
[1] ボッカッチョ、『デカメロン』、上、平川祐弘訳、Kindle 版、河出書房新社、2017年。
[2] 新村出編、『広辞苑』、第5版、岩波書店、1998年、1171ページ。
[3] フェルナン・ブローデル、『世界時間1』、村上光彦、みすず書房、1996年、20-21ページ。
[4] ジャレド・ダイアモンド、『銃・病原菌・鉄』、上、倉骨彰訳、草思社、2012年、153、327ページ。
[5] I・ウォーラーステイン、『史的システムとしての資本主義』、川北稔訳、岩波書店、1997年。
[6] ウォーラーステイン、『史的システムとしての資本主義』。
[7] フェルナン・ブローデル、「長期持続」、井上幸治編、『フェルナン・ブローデル 1902~1985』、新評論、1989年、15-68ページ。
[8] ブローデル、『世界時間1』、93ページ。イマニュエル・ウォーラーステイン『脱=社会科学―19世紀パラダイムの限界』、本多健吉、高橋章訳、藤原書店, 1993年。J・S・ゴールドスティン、『世界システムと長期波動論争』、岡田光正訳、世界書院、1997年、346ページ。
[9] ゴールドスティン、『世界システムと長期波動論争』。
[10] アダム・スミス、『諸国民の富 (三)』、大内兵衛、松川七郎訳、岩波書店、1965年、72ページ。
© 2026 Ikuo Kinoshita