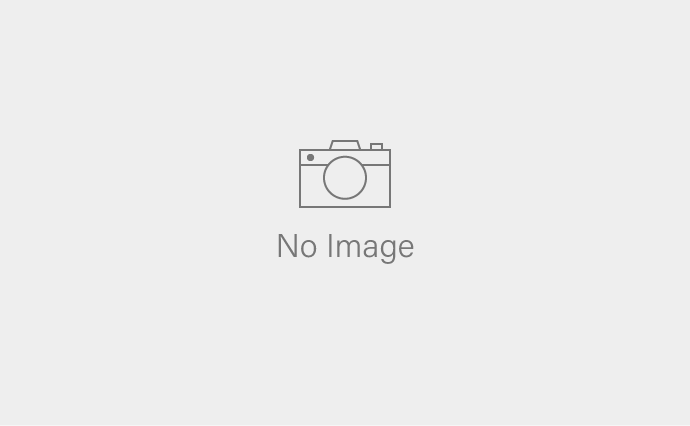経済秩序に関する戦後構想は、フランクリン・D・ローズベルトが演説した四つの自由のうち、欠乏からの自由が始まりである。欠乏というのは、何かが足りないことである。足りないのがモノであるとすれば、生産、交換、売買、あるいは贈与によって補うことで、欠乏から自由になる。
四つの自由演説から7か月後の1941年8月、ローズベルトとイギリスのウィンストン・チャーチル首相は大西洋憲章に合意した。第4条は「すべての国家の貿易と原料へのアクセス」を謳った。これは自給自足に比べれば前進であった。しかし、取引の品目と量がどのように決まるのか、すなわち、市場メカニズムによるのか、計画によるのか、までは明記されていなかった。他方、第5条は、労働基準、経済発展、そして社会保障を向上するためにすべての国々が共同作業をすることに期待を示した。ローズベルト政権が始めたニューディールと福祉国家の政策を世界に広める意図が認められる。市場か、計画か、の二分法で言えば、計画よりの発想である。
これらの提案がどういう結末にたどり着いたか見届けることなく、ローズベルトは1945年4月に亡くなった。チャーチルもその年の7月に下野した。その間の6月に署名された国連憲章には経済条項が存在し、第55条aは「いっそう高い生活水準、完全雇用」の促進を国連の任務とした。
今回のテーマは、第二次世界大戦後の国際経済レジームを「覇権安定論」と「埋め込まれた自由主義」という二つの言葉を用いて論じなさい、である。覇権安定論については、アメリカ合衆国は孤立主義から脱し、世界の指導者としての責任を受け入れる決意はできていたものの、果たすべき具体的な役割は手探りで見つけていった。埋め込まれた自由主義については、戦後経済秩序が単純な自由主義とどこが違ったかを理解したい。
時間を巻き戻して、連合国の勝利が固まった1944年の状況を見よう。新旧覇権国の経済的な条件はどうであったか?
アメリカ合衆国は世界の軍需に応えてカネ、特に金(きん)、を貯め込み、空襲からは無傷のまま、突出した生産力を蓄えていた。外国には多額の債権を持ち、ドル紙幣は誰もが喉から手が出るほど欲しい安定した通貨であった。
他方、イギリスは金本位制から離脱し、ポンド紙幣は海外では余っていた。空襲で国力は消耗し、多額の債務を負っていた。
「大恐慌」の回で見た戦前の教訓は、カネ/金は天下の回り物ということである。これを応用するならば、アメリカ合衆国が蓄えたカネ/金を世界に還流し、流動性を高めることが戦後経済には必須であった。ところが、ブレトンウッズ会議に臨むにあたってアメリカ合衆国が用意した金額はなお十分でなく、英米の対立につながった。
イギリスが出した案はジョン・M・ケインズが考えたケインズ案であった。国際清算同盟を作り、そこに「バンコール」を単位とする巨額の当座借越枠260億ドルを設定する。そのドルを借りて、加盟国は国内経済を拡大できる。枠が使い尽くされれば、加盟国は経常収支を均衡させなければならないが、ケインズは赤字国に温情的であり、赤字国が支出を抑えるだけでなく、黒字国にも国内経済を調整して、黒字を減らす義務があるとした[1]。インフレーションの懸念はありながらも世界的に通貨量を増やし、景気を良くしようというのがケインズ案の狙いであった。
これにたいし、アメリカ合衆国のホワイト案はハリー・D・ホワイトという財務省職員によって作られた。日米開戦に関わったソ連のスパイとして知っている人もいるかもしれない。
ホワイト案の核心は連合国安定基金という制度であった。通貨危機において、そこから加盟国は自国が出資していた額(金・自国通貨・国債50億ドル)まで引き出すことができる。出資した分を返してもらうにすぎないので、信用創造によって有効需要を拡大しない緊縮的な制度である。通貨切り下げによる国際収支の改善は禁止されたので、赤字が出ないよう、国内経済を厳しく監督し、景気の過熱を抑える必要がある[2]。満ち足りた時代であればいざしらず、戦後復興が課題であった時期、この基金だけでは資金需要に応えられず、デフレーションに陥る懸念があった。復興の目的のためには、連合国復興銀行という別の機関を作ることをホワイトは提案した。
ケインズ案とホワイト案が戦わされたのは1944年7月のブレトンウッズ会議においてである。ブレトンウッズは、アメリカ合衆国ニューハンプシャー州のリゾートである。
会議の結果、通貨ではIMF(国際通貨基金)、開発ではIBRD(国際復興開発銀行)という二つの国際機構が設立された。これらはまとめてブレトンウッズ諸制度と呼ばれる。IMFは、国際収支を国内経済より重視するという意味で、ホワイト案を多く採用した[3]。出資額もケインズ案ほどには巨額でなく、金が25パーセント、自国通貨が75パーセントの割合で計88億ドルであった[4]。
為替相場の変更にはホワイト案では禁止されたが、より自由度の高い「調整可能な釘付け」というメカニズムが採用された。
大戦によって多くの国では金が枯渇し、不換紙幣を使いながら国際経済に復帰しなければならなくなった。そうした国々はドルを主な外貨準備とした。十分な金を保有するアメリカ合衆国だけが金本位制を採用した。つまり、金ドル本位制とは、金1オンスを35ドルと交換するアメリカ合衆国の金本位制と各国通貨のドル平価とを合体させたものである。
調整可能な釘付けとは、国際収支の状況を見ながらドル平価を柔軟に変えることができることである。通貨の切り下げによって、国際収支を改善し、国内産業のダメージを緩和することができる。ただし、輸入品の消費が減ることは避けられない。このように見れば、自国通貨の切り下げは本来、権利の享受であるはずである。ところが、悲しいことに、国家というものは二兎を追おうとする。輸入品の消費が減らされることに、消費者としての国民は不満を感じるからである。リチャード・N・ガードナーは次のように指摘する。
しかし、為替相場変更はつねに正しい時ないしは最も効果のある方法で実施されるとはかぎらなかったというのがひろく一致したところである。その威信にかけて、一国の指導者たちは、変更を必要以上に遠い先に引き延ばそうとする――そして結局は巨大な投機圧力の下で、変更を余儀なくされる[5]。
こうして、各国は国際収支に合わせて通貨切り下げを行うことをしなかった。調整可能な釘付けは1950年代には事実上の固定相場制になった。やがて崩壊するブレトンウッズ体制の実態とは、そのようなものであった[6]。
国際復興開発銀行については、世界銀行という通称があり、世界銀行グループの中核である。グループにはほかに、IDA(国際開発協会)、IFC(国際金融公社)、MIGA(多国間投資保証機関)、そしてICSID(投資紛争解決国際センター)があるが、IDAとICSIDは別の回で言及する。
IBRDはいまでこそ開発途上国を援助する機関であるが、かつては先進国をも援助していた。日本も、産業の必要に応じてインフラストラクチャーの援助を受けた。1950年代前半には火力発電所、同後半以降は製鉄所と水力発電所、1960年代には名神・東名高速道路と東海道新幹線がIBRDの資金で造られた[7]。
創設当初、ブレトンウッズ諸制度はいかに機能したであろうか? イギリスでは、自由貿易が戦間期に衰退したことを受けて、ホイッグ党の伝統を継ぐ自由党も衰退した。大戦では保守党のチャーチルが強力な指導力を発揮したものの、国民は戦いに疲れていた。1945年7月、総選挙で労働党が勝利し、クレメント・R・アトリー政権が成立した。
労働党のマニフェストは完全雇用と国有化を掲げ、教育・健康・社会保険など生活水準向上を訴えた。こうして、ゆりかごから墓場までと言われた福祉国家の建設が始まった。国内経済がそれにより拡大したのは必然であった。経常収支は悪化の一途をたどった。
1946年にドル準備がイギリスから流出した原因は軍隊の国外駐留であった。1947年には輸入の激増によって赤字が増え、他方、戦前にあった海外からの利子・収益・配当の送金は減少した。結局、ポンドは交換停止に追い込まれた。ブレトンウッズ体制、すなわちIMF、はまだ動いていなかった。その代わりに対英借款を行ったのはアメリカ合衆国であった。借款と引き換えに、コモンウェルス諸国の対米関税は有無を言わせず引き下げられた[8]。英帝国はかくて解体された。
カネを天下に回すという点では、対英借款は一時的かつ局地的な処置でしかなかった。終戦から2年を経過すると、ソ連とアメリカ合衆国とのライバル関係が明らかになった。西ヨーロッパの復興という成果が、世界のリーダーと自認するアメリカ合衆国には必要であった。
アメリカ合衆国のジョージ・C・マーシャル国務長官は、ともすれば孤立主義に傾きがちな連邦議会と協力し、1948年にヨーロッパを対象とする経済援助法を成立させた。これが世にいうマーシャル・プランである。スペインとフィンランドを除いて、西ヨーロッパの全体と、戦略的に重要なギリシャおよびトルコが援助の対象であった。NATOとマーシャル・プランは車の両輪であり、それぞれ軍事と経済で、アメリカ合衆国がヨーロッパを支援した。
復興はヨーロッパの人々を貧困から救っただけでなく、資材の輸出によってアメリカ合衆国の産業に貢献した。ソ連はこれを、経済主権を侵害する合衆国の棍棒外交、と批判した。ところが、マーシャル・プランが実施された町々には、雨後のタケノコのように、近代的なビルディングが建てられ、ソ連の説明に疑いを突き付けた[9]。
マーシャル・プランが可能であったのは、一つは圧倒的な経済力、もう一つはあらゆる妨害を排除するだけの軍事力をアメリカ合衆国が持っていたからである。
マーシャル・プランの受け皿機関OEEC(欧州経済協力機構)は1961年にOECD(経済協力開発機構)に発展した。日本も1964年に加盟した。現在は、アジア・中南米・太平洋に加盟国を増やし、先進国あるいは自由主義経済のクラブとして、経済・社会・開発の課題に取り組む。
マーシャル・プランの対象はヨーロッパ限定であった。日本への復興援助は、ガリオア(占領地域救済援助)とエロア(占領地域復興援助)という別の枠組みで行われた[10]。
経済が正常化してくると、貿易の役割はますます重要になった。国際貿易機関(ITO)を設けるハバナ憲章は1948年に起草されたものの、国際連盟規約と同じく孤立主義者の餌食となり、アメリカ合衆国の上院が批准を拒否して、発効しなかった[11]。冷戦の始まりが国際主義への期待を下げていたことも災いした。
代わって、暫定適用された簡素な国際制度がGATT(関税及び貿易に関する一般協定)であった。これが数十年間、貿易レジームの屋台骨となる。世界最大のアメリカ市場に魅せられた国々は合衆国の指導に従うことにやぶさかでなかったので、簡素なメカニズムだけで十分であった。
GATTの基本原則は自由・無差別・多角である。関税率を下げるのが自由、特定の相手国だけを不利に扱ってはならないのが無差別、そして多くの締約国が参加してなされる関税交渉が多角である。多角的貿易交渉は「ラウンド」と呼ばれ、GATTのもとで数回、行われた。そのかいあって、世界の関税率は20世紀後半、急激に低下した[12]。
大恐慌になすすべがなかった戦前の金本位制と違い、戦後の国際経済レジームはキンドルバーガーが言うところの覇権安定を実現した。まず、「比較的に開かれた市場を維持する」役割は、GATTのもとでアメリカ合衆国が果たした。つぎに、「景気調整的な長期貸付を行」ったのはマーシャル・プランであった。多国間のIBRDは1940年代にはまだ働いていなかったからである。最後に、対英借款が「手形を割引く」のと同じく、債務を軽くした。
ところで、戦後経済秩序については、「埋め込まれた自由主義」という言葉で説明されることがある。国際経済は自由主義であったものの、国内経済は介入主義であった、というのがその意味である[13]。金ドル本位制は金本位制とドル本位制との折衷であり、もはや自由主義的な金だけに縛られず、アメリカ合衆国ではケインジアンの経済政策が行われ、イギリスは福祉国家の建設をあきらめなかった。自由主義が埋め込まれたのはそうした介入主義の国内経済であった。
以下では、その後のブレトンウッズ諸制度について論じる。ただし、それは「ブレトンウッズ体制」、すなわち金ドル本位制、の話題ではなく、IMFとIBRDという法人格を持つ国際機構のことである。ブレトンウッズ体制の崩壊については「覇権の衰退」の回で扱う。
一元的な秩序は多様な要求に応えられない。IMFとIBRDがまさにこの理由で批判されてきた。
構造調整は、1980年代におけるIMFおよび世界銀行による融資の概念であった。そうした融資は新古典派経済学に従い、開発途上国の経済体質を改革しようとした。具体的には、緊縮財政、自由化、そして民営化の政策が融資の条件として求められた。これらの政策は福祉予算の切り捨てと、それにともなう悲惨な人道的な影響をもたらしたと論じられることがある。
それと前後して、東側諸国のIMF加盟が相次いだ。国名を挙げれば、1972年のルーマニア、1980年の中国、1982年のハンガリー、1986年のポーランド、1990年のブルガリア、そして1992年のロシアである。中国以外のこれらは、それまで経済相互援助会議(CMEA、スメア、セフ、コメコン)において、「振替ルーブル」という帳簿上の単位を使って貿易を行っていた。各国通貨に金平価はあったものの、それらは名目的で、交換性がなく、為替相場は恣意的であった。決済には相手国の承認が必要であったから、貨幣経済というよりも物々交換であった[14]。各国のIMF加盟によって経済相互援助会議は有名無実になり、ソ連の崩壊に先んじて廃止された。
冷戦後、移行諸国と呼ばれた旧共産国は勝ち組と負け組に二分した。チェコ、ポーランド、そしてハンガリーには西側からの投資が押し寄せ、勝ち組となった。ところが、民営化と自由化というIMFが主導した「ショック療法」はロシアなど移行国の一部に大混乱をもたらした[15]。当時、ロシア政府に助言を行っていたハーバード大学教授のジェフリー・サックスの本から引用する。
要するに、ビジネスマンと称する背徳的なグループ――のちに集団としてロシアの新しい政商「オリガルヒ」と呼ばれることになる――は百億ドルもの価値のある天然資源、おもにロシア国有の石油ガスをまんまと自分の懐に入れることができた[16]。
1994年から1995年には、注目はメキシコの通貨危機に移った。アメリカ合衆国のクリントン政権の対応は早かったとされる。ロバート・E・ルービン財務長官はペソの暴落、インフレーション、景気後退、失業、さらには隣国アメリカ合衆国への違法薬物密輸といった悪影響を警告した[17]。
1997年から1998年のアジア通貨危機は日本円の為替相場と関係がある、という説がある。プラザ合意による円高のため、1980年代後半、日本企業はアジアへの投資を増大させた。ところが、1990年代半ば円安に転じると、自国通貨をドルとの固定相場(ドルペッグ)にしていたアジア諸国からの輸出は減少し、ドル準備の不足を招いた[18]。
円との関係はともかく、ドルとの固定相場がアジア通貨危機の決定的な原因であったことはまちがいない。何かの理由でアジアの国の経済見通しに不安が広まり、現地通貨の相場が落ち始めると、その通貨は投機的に売り浴びせられる。固定相場の防衛に失敗すれば、現地資産を保有することは不利になり、短期資金は一斉に国外に引き揚げられる。現地通貨の暴落は止めようがない。
アジア通貨危機に関しては、クローニー資本主義と呼ばれる政権の腐敗が原因であるとも言われた。クローニーとは政府に縁故がある人々のことであり、そうした人々が経営する企業を優遇しすぎて、政府のムダ遣いと輸出競争力のない産業を膨らませた、というのである。
アジア危機への対応はメキシコ危機の時より遅れたとされる。日本から新宮沢プランが提案され、結果的にIMF、日本、そしてアメリカ合衆国が中心となって支援が行われた[19]。回復はおおむね順調であったものの、インドネシアで政権崩壊と民主化が起き、不当支配をされていたティモールレステが独立した。その後、アジア諸国はチェンマイ・イニシアティブという通貨スワップ協定を結び、危機時にドルなど外貨を融通し合うことを約束した[20]。 IMFとIBRDへの毀誉褒貶は、しばしばアメリカ合衆国の制度的な優越と結び付けられる。IMFの場合、理事会での投票は、各国250票の基礎票に出資割当額10万SDR(特別引出権)ごとに1票ずつ加算する、という方法で計算される。これだけでも経済大国に有利である。さらに、重要な決定については70パーセントあるいは85パーセントの特別多数率が適用されることで、アメリカ合衆国、ドイツ、イギリス、フランス、そしてイタリアが一致すれば、拒否権を行使することができる。しかし、近年、IBRDでも、IMFでも、増資のたびに中国の投票権が拡大している。時代は変わりつつあるが、一変するまでには至っていない。
[1] リチャード・N・ガードナー、『国際通貨体制成立史』、村野孝、加瀬正一訳、東洋経済新報社、1973年、193-235ページ。山本栄治、『国際通貨システム』、岩波書店、1997年、81ページ。
[2] ガードナー、『国際通貨体制成立史』、193-235ページ。山本、『国際通貨システム』、81ページ。
[3] ヘンリー・R・ナウ、『アメリカ没落の神話』、石関一夫訳、TBSブリタニカ、1994年。
[4] 山本、『国際通貨システム』、81ページ。
[5] ガードナー、『国際通貨体制成立史』、上、66ページ。
[6] 山本、『国際通貨システム』、83ページ。
[7] 大野健一、大野泉、『IMFと世界銀行』、日本評論社、201ページ。渡辺利夫、三浦有史、『ODA』、中央公論新社、2003年、47ページ。
[8] ガードナー、『国際通貨体制成立史』、下、512ページ。
[9] Library of Congress, “For European Recovery: The Fiftieth Anniversary of the Marshall Plan Online Exhibition,” Library of Congress, https://www.loc.gov/exhibits/marshall/marsh–exhibition.html, accessed on January 11, 2026.
[10] 村田良平、『OECD(経済協力開発機構)』、中央公論新社、2000年。永田実、『マーシャル・プラン』、中央公論社、1990年、157ページ。
[11] ガードナー、『国際通貨体制成立史』、下、565-608ページ。
[12] Paul Bairoch, Economics and World History: Myths and Paradoxes (Chicago: The University of Chicago Press, 1993), p. 40.
[13] John Gerard Ruggie, “International Regimes, Transactions, and Change: Embedded Liberalism in the Postwar Economic Order,” in Stephen D. Krasner, ed., International Regimes (Ithaca: Cornell University Press, 1983), p. 209.
[14] 永田実、『ルーブル―ソ連の国際経済戦略』、教育社、1986年。
[15] ジェフリー・サックス、『貧困の終焉』、鈴木主税、野中邦子訳、早川書房、2006年、194ページ。毛利良一、『グローバリゼーションとIMF・世界銀行』、大月書店、2001年、213ページ。山下知志、『図解 世界のお金の動きが一目でわかる本』、講談社、2008年、14、176ページ。
[16] サックス、『貧困の終焉』、220ページ。
[17] ロバート・E・ルービン、ジェイコブ・ワイズバーグ、『ルービン回顧録』、古賀林幸、鈴木淑美訳、日本経済新聞社、2005年、14ページ。
[18] 毛利、『グローバリゼーションとIMF・世界銀行』、227ページ。
[19] 毛利、『グローバリゼーションとIMF・世界銀行』、251ページ。
[20] 小原雅博、『東アジア共同体』、日本経済新聞社、2005年、41ページ。『日本経済新聞』、朝刊、2010年3月24日。
© 2026 Ikuo Kinoshita