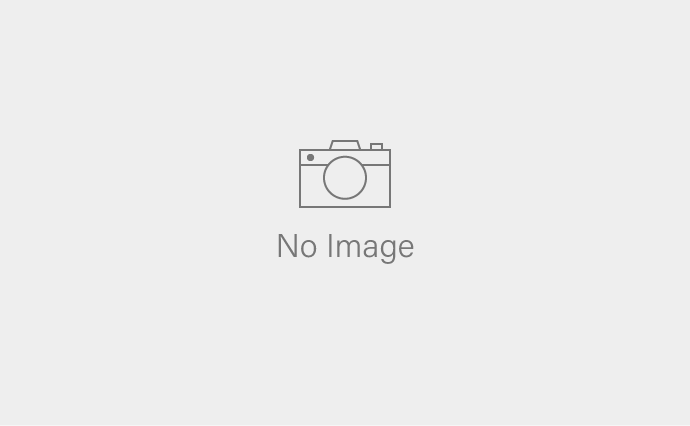永遠平和の功利性に対する異議は、実行できないこと以外には何もない、とベンサムは書いた。そして、それを実現するには、議会を作って各国から代議士を出し、意見交換させればよい、と提案した[1]。もちろん、それは実現しなかった。なぜなら、死後、出版されたその論文が実際に書かれたのはフランス革命が始まろうとしていたころで、まだ絶対君主の時代であったからである。
今回のテーマは、19世紀外交を旧外交および会議外交の観点から論じなさい、である。19世紀は旧外交のもとであったものの、会議外交が国際秩序を定める一つの方式として定着した。ベンサムが提案した「議会」が実現に一歩、近づいたことになる。
しかし、会議外交の話題に進む前に旧外交について知っておく必要がある。この用語はイギリスの外交官、ハロルド・ニコルソン、によって広められた。彼自身の解説を引用する。
絶対君主制の時代には、国はその住民とともに、支配君主の絶対的所有物とみなされていた。かくして、[フランスの-訳者注]ルイ十四世や、それ以上に、[ロシアの-訳者注]エカテリーナ二世や[プロシアの-訳者注]フリードリヒ大王は、対外政策の遂行、平和か戦争かの問題を自己の掌中に保持していたのである[2]。
つまり、旧外交とは、戦争・平和・同盟などに関する意思決定権を絶対君主が握っていたことをいう。これは17世紀と18世紀には統治一般の原則でもあり、民主主義と相反した。
閨房外交という用語がある。閨房が寝室という意味であることから、君主の私生活により影響される外交のことである。ニコルソンはマムズベリー伯ジェイムズ・ハリスの回想録を引用する。1779年、ロシアのエカチェリーナ二世を誘って同盟を結ぶため、イギリス政府はハリスをサンクトペテルブルクに派遣した。容姿がよかったので、女帝のお気に入りになったという。ハリスの日記からの引用である。
―前略―仮装舞踏会で、コルサコフ氏が余の許へやってきた。そして、自分のあとについて来て欲しいと言って、裏道を女帝陛下専用のお化粧室へと余を案内した。そして余を女帝陛下に御紹介申し上げるやただちに退室した[3]。
フランスのベルサイユ宮殿を訪れれば、寝室が公務の場であった光景を思い浮かべることができる。閨房外交は常態であったのである。
宗教改革までは、封建的な序列がそのまま通用した。教皇が諸国をリストに載せる際の1504年における順序が残されている。それによると、ローマ教皇が首位で、神聖ローマ帝国皇帝がそれに次ぎ、皇帝の推定相続人、フランス王、スペイン王、アラゴン王、イングランド王……と続いた。
ところが、宗教改革後、プロテスタントに転じた国々は、これまで絶対的な基準であった教皇の権威を認めなかった。国家の地位を上げるためには、もはや各国の自助努力によるしかなかった。
各国は都合の良い根拠を示して、自己の地位を主張した。例えば、王号の古さを根拠として持ち出す国があった。フランスは482年におけるクロービスのフランク王即位、スペインは718年におけるアストゥリアス王国成立、イングランドは827年におけるエグバートのイングランド統一、とまるで小学生の口げんかのように競いあった。これは国際法秩序のなかでの古さであり、東洋のオスマン帝国や日本は19世紀にそこに入ってからの年数しかカウントされなかった。
席次争いの熾烈さを伝える事件がある。1661年、ロンドンでフランスとスペインの使節団が馬車の順番をめぐって暴力事件を起こした。この争いはちょうど百年後に、ブルボン家内の格式の問題として解決された[4]。
こうした封建主義を根底から覆したのがナポレオン・ボナパルトであった。彼は神聖ローマ帝国を1806年に滅ぼした。最高位の外交官である大使の交換はフランス宮廷と大国とのものに限定し、ボナパルト家を頂点とする事実上のヨーロッパ帝国を築こうとした[5]。彼は旧外交のパーツを使って自らのピラミッドを組み立てたのである。しかし、家柄的には成り上がり者であり、また、国境を好き放題に改編したので、結局、旧勢力の包囲網によって彼は倒された。
ナポレオンの没落後、封建秩序が復古された。舞台となったのは1814年から翌年にかけてのウィーン会議であり、ナポレオンと戦った大同盟が戦後処理を行った。
物見遊山の客を含めるとウィーン会議のために10万人が押し寄せた。政府関係者だけでなく、今でいうNGOやロビイストも来ており、ドイツ書籍商組合は出版の自由や著作権の保護を訴えた[6]。
「会議は踊る」といった遊びにかまけたイメージがウィーン会議には付きまとう。ホストであったオーストリア外相クレメンス・フォン・メッテルニヒは次のように弁解する。
元帥リーニュ大公の言葉、「<会議>は踊る、されど進まず」は、当時の新聞がこぞって取りあげた。<会議>のあいだ、ウィーンの市中には大勢の供揃えを引き連れた多数の君侯とたくさんの観光客がいた。これらの客人に社交界の慰めと楽しみを供するのは帝国宮廷の義務だった。しかし、祝宴と<会議>の仕事とに共通するものは何もなく、祝宴によって仕事に支障が生じることなど少しもなかった。<会議>の期間が短かったことがその具体的証拠である[7]。
1931年のドイツ映画『会議は踊る』は、メッテルニヒが敵役のロシア皇帝アレクサンドル一世を遊興にうつつを抜かせるため、会議を踊らせた、という筋書きである。オーストリアとロシアが対立したことは史実である。では、何をめぐって対立したかというと、領土的解決の問題であった。
戦後処理の大方針は、戦争の惨禍と自由主義の蔓延を反省し、旧来の絶対君主に領土を回復させて安定したヨーロッパを再建することであったが、これにはコンセンサスが存在した。
細部で五大国の意見が鋭く対立したのは個別の領土的変更であった。ロシアはポーランドの領有を求め、プロイセンはザクセンを求めた。ザクセン王は親ナポレオンであったことがあだとなり、国を奪われようとしていた。
オーストリアとしては正統主義を貫くことで会議を成功させたかったので、正統な領土請求権があると考えられないロシアとプロイセンに屈するわけにいかなかった。思い通りにいかないロシア皇帝がメッテルニヒに決闘を申し込む、と噂さえ立った。ザクセンについては、策謀家として知られるフランス外相のタレランがザクセン王から金銭を受け取り、領土回復を取り計らったという[8]。
オーストリア、フランス、そしてイギリスは攻守同盟の三国秘密協定を結んで、ロシアとプロイセンに対抗した。結局、ポーランドはロシア皇帝を国王とする同君連合に組み入れられ、かろうじて国家体制だけが残された。ザクセンは北半分がプロイセンに割譲されることで妥協が成った。
高坂正尭は、会議は踊るとはコンセンサスができるまで「待つため」、全体会議を開催するかわりに舞踏会を開催したことであると解説する[9]。仲間割れにより会議が決裂することを避ける機能を舞踏会は担ったことになる。
ウィーン会議で合意された最終議定書は、正統主義に基づきながらも戦勝国に戦利品を与える領土的変更を主な内容とした。その一方で、附属書で定められたことにも、見るべきものがあった。ドイツ連合憲法、スイスの永世中立、アフリカ人奴隷貿易廃止列国宣言、国際河川の自由航行、そして外交使節席次規則がそれである。
外交使節席次規則は第1条において、外交使節を大使、公使、そして代理公使の三つの階級に分けた。席次もこの順を原則としつつ、同一階級内では着任が早い順とされた。つまり、同一階級内では王号の古さも宗教への信心も無関係とされた。
ただし、大国と小国との峻別は残った。そもそも、大使か、公使か、を決めるのは双方の合意によるのであるから、一方が他方に、あなたの国は大使を派遣する資格がない、と言えば、大使は派遣できないことになる。つまり、自他ともに大国と認める国どうしだけが大使を交換できる。ビクトリア朝の初め、イギリスはフランス、ロシア、そしてトルコのみからしか大使を接受しなかった。そして、大使会議が行われる場合には、公使は出席を拒否された。
メッテルニヒはウィーン会議について後年、「こうして、ヨーロッパは可能な範囲内で、恒久的な平和を保証されたのだ」と自画自賛した[10]。それは五大国によるコンサート、つまり協調、であり、1818年のエクス・ラ・シャペル(アーヘン)、1820年のトロッパウ(オパバ)、1821年のライバッハ(リュブリャナ)、そして1822年のベローナと一連の会議へと引き継がれた。
ウィーン体制はさまざまな部品からできているが、ドイツ連合もその一つである。フランクフルトに連合議会があり、「連邦」と呼んでしまいたくなる。実際、ドイツ語では連合と連邦の区別はない。
ドイツ連合の主な役割は、ナポレオンを生んだフランスからの防衛である。連合軍にはプロイセンのような軍事大国から、田舎町くらいの極小国までが兵力を出す。
他方で、ドイツ連合は自由主義思想に対する防波堤でもあった。1819年のカールスバート決議は、危険思想の教育者を解雇し、図書・新聞を検閲し、そして革命運動を監視する委員会を置くという内容であった[11]。
自由主義とは何か?、というと、政治的には、普通選挙で選ばれた議会の多数で法律を定める国家体制である。絶対君主の後継者たちは、身分制議会や制限選挙で自由主義の波をしのぎたかった。しかし、1848年にヨーロッパに広がった革命は容赦なく正統主義とウィーン体制を終わらせてしまった。
ところが、革命の波はロシアによって東から押し返された。そのロシアを西ヨーロッパの国々が負かしたのが1853年に始まったクリミア戦争である。聖地エルサレムの管理をめぐってロシアとオスマン帝国が対立し、オーストリアが仲介しようとしたものの、イスタンブールに駐在していたイギリスの大使がスルタンをたきつけて、ロシアとの軍事衝突が起きた。イギリス、フランス、そしてサルデーニャがオスマン帝国側に立って参戦し、勝負を付けた。
その講和会議が1856年のパリ会議である。結ばれたパリ条約は、オスマン帝国の独立と領土保全を他の締約国が保障し、さらにモルダビアとワラキアの自治が決められた。ロシアについては、黒海の非武装化が押し付けられた。パリ宣言という、交戦国と中立国との海洋における戦争法も作られた。
戦争の後始末という点では、1878年の第1回ベルリン会議も同じである。バルカン半島の領土をめぐって露土戦争が起きた。その講和であるサンステファノ条約では、ブルガリアの巨大な領土が構想されており、オスマン帝国が形だけの存在になる、とイギリスとオーストリアが危機感を持った。仲介人を買って出たのはドイツの宰相オットー・フォン・ビスマルクであった。当時の大国すべてがこの会議に参加した。オーストリアハンガリー、フランス、ロシア、ドイツ、イギリス、イタリア、そしてオスマン帝国である。これらはたがいに大使を送る大国クラブであった。こうして、オスマン帝国はふたたび救われた。
パリ会議と第1回ベルリン会議は東方問題、すなわちオスマン帝国の問題、を扱った。1884年から翌年にかけての第2回ベルリン会議は、アフリカ大陸の分割を議題とした。コンゴを植民地にしようとするベルギーのレオポル二世が、大陸南部を支配下に収めようとするイギリスおよびポルトガルの動きに危惧を抱き、ビスマルクを頼って開かれたものである。これをきっかけに、それまで沿岸部だけであったアフリカの植民地化が内陸にまで及んでしまった。
ところで、日本語では同じくベルリン会議と呼ばれるものの、英語では、第1回のものはコングレスで、第2回のものはコンファレンスである。20世紀初頭まで、コングレスのほうが平和条約の交渉といった重要な議題を扱い、威厳のある印象を与える会議であった[12]。第一次大戦後には、コンファレンスのほうが一般的になる。
以上のように旧外交は、国内では絶対主義、国際的には大国と小国の峻別、という身分制を前提とした。20世紀に現れる「新外交」は、ニコルソンによると、国民全体を代表しての外交であり、平等な主権国家間のフラットな関係を前提とする。二国間の外交でも、国際連合等の多国間の外交でも、現代では新外交が一般的である。 外交官の出自についても旧外交と新外交には違いがある。旧外交では外交官は貴族の職業であった。007ことジェイムズ・ボンドに出くわしそうなゴージャスなホテルやリゾートのイメージである。パーティは私費でまかなわれ、自邸に招待するものであったので、外交官になるには財産資格まであった。他方、現代の外交官は庶民でかまわない。ただし、積極的に庶民を採用するか、これまでどおり名家のお坊ちゃん、お嬢ちゃんを採用するか、は国により方針に違いがある。
[1] Jeremy Bentham, “Plan for an Universal and Perpetual Peace,” in Saint-Pierre, Rousseau, and Bentham, Peace Projects of the Eighteenth Century (New York: Garland, 1974), pp. 26-31.
[2] H・ニコルソン、『外交』、斎藤真、深谷満雄訳、東京大学出版会、1968年、54ページ。
[3] ニコルソン、『外交』、55ページ。
[4] Ernest Mason Satow, Satow’s Guide to Diplomatic Practice, edited by Lord Gore-Booth and Desmond Pakenham, 5th. ed. (London: Longman, 1979), pp. 21-22.
[5] 木下郁夫、『大使館国際関係史―在外公館の分布で読み解く世界情勢』、社会評論社、2009年、53-55ページ。
[6] 幅健志、『帝都ウィーンと列国会議』、講談社、2000年、136-137ページ。
[7] メッテルニヒ、『メッテルニヒの回想録』、安斎和雄、安藤俊次、貴田晃、菅原猛訳、恒文社、1994年、241ページ、原著者注。
[8] ジャン・オリユー、『タレラン伝』、下、宮沢泰訳、藤原書店、1998年、995ページ。
[9] 高坂正尭、『古典外交の成熟と崩壊』、第4版、中央公論社、1994年、358ページ。
[10] メッテルニヒ、『メッテルニヒの回想録』、252ページ。
[11] Frederick K. Lister, The Later Security Confederations: The American, “New” Swiss, and German Unions (Westport: Greenwood Press, 2001), p. 122.
[12] Ernest Satow, A Guide to Diplomatic Practice, vol. II (London: Longmans, Green and Co., 1917), pp. 1-2.
© 2026 Ikuo Kinoshita