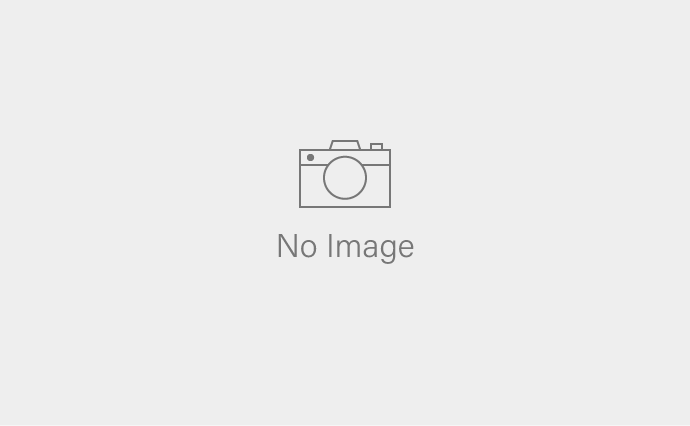なぜ存在するのか?、と、すでに存在する国家について問うのは哲学者くらいである。アリストテレスは、国家は人々が「よく生きるために存在する」と述べた。他の動物と違い、人間は、善と悪から善を、正と不正から正を選ぶことができる。そして、他人とその選択を共有することができ、国家を作る。ゆえに人間は政治的(ポリス的、国家的)動物である、と彼は導く[1]。
このように、古代ギリシャの国家には強い存在理由があった。個人の主体的な選択によるというのは一種の社会契約論であり、フィクションである。直接民主制に参加することによる一体感が、フィクションの契約を事実であるかのように錯覚させた。男性市民としての連帯責任が、悪法も法なり、と観念させたにちがいない。アリストテレスの師であるプラトンが記した『ソクラテスの弁明』から引用する。
―前略―祖国が忍従を命ずるものは、それが殴打であれ、投獄であれ、また負傷もしくは戦死のおそれのある戦場に我らを送ることであれ、黙ってこれに忍従しなければならない。これは為すべきことでありまた法の要求するところである。我らは逃亡したり退却したりその持場を棄てたりすることなく、むしろ戦場においても、法廷においても、またどこにおいても、およそ国家と祖国との命ずるところはこれを実行しなければならない[2]。
時代は下って、中世キリスト教世界においては、もはや住民全員がガバナンスに直接参加することはなかった。支配者と被支配者は分離された。民衆は無視されていたわけでない。トマス・アクィナスによると、統治の目的は死後の浄福、つまり天国に行くこと、である。しかし、役割を与えられるのはもっぱら聖職者と王である。王は、「神の法[神法-訳者注]に通暁し、いかにすればかれの治下にある民衆が善く生きることができるか、を主要な関心事としなければならない」。民衆の善き生活のために王が果たす役割は三つ、すなわち、平和、善き行為への導き、そして物資の充実である[3]。他方、民衆は導かれるまま、選択の余地はなく、受け身の存在であった。
今回のテーマは、近代国際システムの形成と国家理性の概念について論じなさい、である。国家理性またはレゾンデタ(raison d’État)とは、国家にとっての行動原則である。以下の議論は主にドイツ人政治学者フリードリヒ・マイネッケに依拠する。彼はベルリン大学教授などを歴任し、『近代史における国家理性の理念』を著した[4]。上の古代ギリシャと中世キリスト教世界の例は、それを補うために筆者が加えた。
国際システムを構成する単位は主権国家であり、それらが複数、存在してシステムを成す。主権には対内的なものと対外的なものの両面がある。中世の封建システムが崩壊し、近代の主権国家システムが形成されるには、その両方において変化が必要であった。すなわち、対内的主権では、王(主権者)に権力が集中しなければならず、対外主権では、帝権・教権が崩れ、外国の内政干渉が除かれねばならなかった。
日本とヨーロッパは似ているが、ここではヨーロッパを念頭に置く。一般民衆の上には世俗の権威と宗教の権威の二つが並び立った。世俗の権威では頂点に皇帝がおり、そのもとに王がいて、民衆の直接の領主である諸侯が皇帝を支えた。宗教の権威は教皇に発し、大司教、司教、司祭へと下り、民衆に到達した。
しだいに、帝権はオーストリア領内だけにしか及ばなくなった。その外では、別の世俗権力が他の権力を排除し、最終的に、国家を代表して外交を行うようになった。国家理性とは、この歴史的事業における試練に立ち向かい、運命を切り開いた主権僭称者たちの意識にほかならない。
皇帝を頂点とする世俗権力の崩壊が最初に起きたのはイタリアであった。小さな都市国家が分立し、それぞれが遠方の異国と通商をする経済力を持っていた。15世紀には、最初の外交使節と目されるニコデモ・ダ・ポントレモリがミラノを代表してフィレンツェに常駐した[5]。近代外交の特徴である相手国の首都に大使館または公使館を置くことがここに始まった。規模の小さな都市国家は絶えざる戦争に耐えきれず、ベネツィアと教皇庁(とサンマリノ)以外は滅びゆく運命にあった。
都市国家の一つ、フィレンツェ共和国、において名著が生まれた。ニッコロ・マキアベッリの『君主論』(1532年刊)である。宗教的な思考をした中世のアクィナスらと違い、彼は国家(stato)に注目した。国家は当時の語感では事実上の影響力・権威・権力といったものであったとされる。日本の戦国時代に喩えれば、役職の整った室町幕府というよりも、織田信長の上洛まえに彼の取り巻きであった家臣団といったところであった。ともかくも、同書は力の政治、すなわち「ライオンの力と狐の狡知」を指導者に教え、保身のためには軍事や策謀を駆使すべし、と勧めた。国際政治学における現実主義の始まりをマキアベッリに求める説がある。
マキアベッリの哲学は、当時の小君主が置かれた環境の厳しさを反映した。彼が求めたものは運命を克服するだけの力量を備えた君主であった。つまるところ、そうした人物は保身のためなら何も厭うものがない暴君である。人民は蹂躙されるだけの客体にすぎず、その幸福はまったく視野の外であった。こうした国家理性は教会勢力を敵に回した。『君主論』は暴君志願者の需要に応え、今なお出版部数を増やす。
そのころ、マルティン・ルターが95か条の論題(1517年)を示し、宗教改革が始まった。ドイツと北ヨーロッパのルター派、そして、スイス・オランダ・フランス・スコットランドのカルバン派が大きく勢力を伸ばし、カトリック教会と戦った[6]。
封建時代の紛争は家と家との対立から起きた。ウィリアム・シェイクスピアが書いた戯曲『ロミオとジュリエット』の悲恋を思い起こせば、何とものどかな紛争である。宗教改革の時代には、家と家との争いに神をめぐる争いが加わった。教会は仲裁者であることをやめ、最も強硬な当事者になった。大貴族ともなれば、領地の礼拝がどの宗派になるかは住民を巻き込む公的な争点である。国民の大多数がカトリックであったフランスにおいては、ユグノーすなわちカルバン派の代表であったアンリ四世さえ改宗しなければならなかった。
宗教和議のモデルは1555年におけるアウクスブルクの宗教和議である。要点は二つであった。一つは、君主が領土の宗教を決定できること、ラテン語ではクイウス・レギオ、エイウス・レリギオである。もう一つは、その領地の宗教が嫌である者は移住しなければならないことである。どの宗派を信じる者が正統な君主であるか決まって、はじめて宗教和議は真の和議になる。真の和議を平和的に決められないので、結局は戦争になる。
宗教戦争は血なまぐさい。フランスのユグノー戦争では1572年にサンバルテルミの大虐殺が起きた。ユグノー側は、後にフランス王アンリ四世となるナバラ王アンリを擁した大貴族ブルボン家を主な戦力とし、これにイギリスやドイツ諸侯といったプロテスタント諸国が加勢した。対抗するカトリック側の中心は、ギーズ公アンリを始めとする大貴族ロレーヌ家であり、教皇庁やスペインが応援した[7]。
では、その上に立つ王家はどうであったか? 王妃カトリーヌ・ド・メディシスが夫であり王であるアンリ二世の死後、摂政となり、家長となっていた。彼女は対立する両派のバランスを権力の基礎とするやじろべえ的な存在であった。それゆえ不安定で、無力であり、両派の妥協を目指した。
王に力がなければ主権の確立は夢物語である。それに気づいたポリティーク派という人々が現れ、国家の集権を第一に置く改革を主唱した。なかでもジャン・ボダンの『国家論六巻』(1576年)は「主権とは国家の絶対にして永続的権力である」と述べ、立法権、外交権、人事権、終審裁判権、恩赦権、貨幣鋳造権、度量衡統一権、そして課税権という固有の権限を挙げた[8]。ブルボン家がすったもんだの末、王位を得た後は、フランスは主権を強化し、絶対主義を打ち立てた。
同じころ、ヨーロッパ各地で軍隊の改革が行われた。長槍兵による槍衾の戦術が発達したことによって、騎士が没落し、傭兵であるフリーランサーが活躍するようになった。常備軍もマキアベッリによるフィレンツェでの導入は早すぎたものの、オランダではオラニエ公マウリッツ・ファン・ナッサウが行ったマスケット兵の軍事教練が成功した[9]。マスケット兵は金銭的費用はかかるものの、馬を養う広大な牧場は不要である。軍隊制度の変化は中央集権化に拍車をかけた。
ただし、神聖ローマ帝国だけは中央集権化に逆行した。一つの理由は、国家体制そのものの形骸化が進んでいたことにある。皇帝はハプスブルク家が1438年から1806年までほぼ独占した。これは権威が安定していたから、というよりも、帝位による特権はほとんどなかったために、多大な犠牲を払ってまで諸侯は独立戦争をする価値がなかったからである。帝国議会と帝国裁判所も、時とともに実質を失った。まるで室町幕府のようである。
権威失墜の一つの理由は、神聖ローマ帝国という名が示すように、帝国はカトリックと不可分の関係にあったことにある。宗教戦争である三十年戦争では、国教について妥協するつもりがないため、戦いは長期化した。
分権化したドイツを舞台とする三十年戦争は、内戦よりも国際戦争のイメージが合う。カトリック側の皇帝兼オーストリア大公はアルブレヒト・フォン・バレンシュタインに傭兵隊を指揮させ、同盟の主力となった。バイエルンとスペインがこれを支えた。対するプロテスタント側からはプファルツ、ザクセンバイマルなど多数の諸侯が参加し、ノルウェー、 スウェーデン、そして戦争後半のフランスと外国からの介入は間断なく続いた。長期化の原因は宗教の分裂だけでなく、国際的連帯にもあった。
内輪もめが果てしなく続いたドイツを尻目に、フランスは新しい歴史段階に入った。その大臣リシュリュー公は、カトリックの高位聖職者である枢機卿であったにもかかわらず、1635年に自国をプロテスタント側に立って参戦させた。中世においては十字軍がそうであったように、宗教的に正しいかどうかが理性の判断基準であった。ところが、リシュリューは徹底的な現実主義者であり、国家の行く末に思いをめぐらせた。リシュリューの言葉のなかから、ヘンリー・A・キッシンジャーは次のものを選んだ。
国家的な問題の中においては、力が持つ者がしばしば正しいのであって、弱い者は世界の多数を占める意見の中で何とか悪いと言われないようにすることのみが可能なのである[10]。
力が第一、宗教は二の次である。少数者はいじめられるという勢力均衡の見方をリシュリューは重んじた。同じ人物が国内ではユグノーを弾圧し、貴族の権限を削り、絶対主義を強化した。国家が宗教から自由に独自の理性を持ち、対外政策を決定する、という国家理性が確立したのである。
三十年戦争を終わらせるため、ウェストファリア(ベストファーレン)地方の二つの都市で講和会議が始まった。スウェーデンとは新教都市オスナブリュックにおいて、フランスとは旧教都市ミュンスターにおいて、ドイツ諸領邦は講和交渉に臨んだ。
ウェストファリア条約は他の平和条約同様、重要な領土的解決を伴った。スイスとオランダは独立が正式に認められた。フランスはアルザス・ロレーヌを蚕食し始めた。スウェーデンはバルト海南岸まで獲得し、北方の強国になった[11]。
より重要であったのは、条約が神聖ローマ帝国の国家体制を変質させたことである。ただし、帝国の主権が確立したのではなく、臣下である諸領邦の主権が確立した。いわば下剋上である。
まず、対内的主権については、宗教和議が成立した。領土の宗教は1624年1月1日の現状に固定し、君主も変更できない、というものである。ただし、住居のなかで私的に他の宗派を信仰することは自由である。帝国議会において宗教上の決定はコンセンサスに則って行うことが定められた。両宗派が対立する場合にはコンセンサスは不可能であるから、帝国は宗教的に意味あることはできなくなった、と解釈される[12]。
対外的主権についても、帝国は完全に無力化された。皇帝はあらゆる決定に議会の承認を要するということであるから、帝国としての行動の自由はないに等しい。さらに、諸領邦は外国と条約を締結することができることになり、勢力均衡のプレイヤーになった。
領邦はもはや主権国家と呼べるのでないか? 17世紀後半、国際法学者のザムエル・フォン・プーフェンドルフは自問自答した。ドイツは君主制なのであろうか? 貴族制なのであろうか? それとも、民主制なのであろうか?、と。出した答えは、「制限された君主制」と「主権国家のシステム」の間を揺れ動く「何かいびつなモンスターのようなもの」であった[13]。神聖ローマ帝国の紋章は双頭の鷲である。帝国は、広げたその翼に諸領邦の紋章を配して描かれる。1羽なのか、何羽なのか分からないそのさまがプーフェンドルフには「いびつ」と感じられたのである。
ウェストファリア条約の結末を要約すれば、次のようになる。すなわち、もはや、教皇もハプスブルク家も、カトリックの信仰を強制することができなくなった。教皇と皇帝の権力が他の主権国家の上に君臨するのではなく、主権国家が自らの意思で外部の主権国家と関係を取り結ぶようになった。最後に、主権国家間を結びつける最重要の手段は、それらの間の条約となった。いわゆるグロティウス的な国際法秩序が打ち立てられたわけである。
「朕は国家なり」とルイ十四世は言ったとされる。君主に対する貴族の抵抗は弱まり、絶対主義と呼ばれる自由な権力行使を君主たちは楽しんだ。ところが、外国に対しては自由はなく、諸国は領土をめぐって戦争を繰り返した。どの国も単独では優位に立てないゆえに、国益に基づき判断して、他国と連携する。それこそ勢力均衡である。
プロイセンのフリードリヒ二世(大王)は勢力均衡外交の優等生であった。ドイツに対するフランスの意図について、彼の分析を引用する。日本語訳は石原莞爾である。
ヴェルサイユの政府は、オーストリイの権力が破滅すること、しかもそれが永久に滅亡するものと堅く信じてゐた。オーストリイの廃墟の上に、フランスは互に均衡を保ち得る四つの君侯を造らうと考へてゐた。すなはちハンガリイ王国とオーストリイ、シュタイエルマルク、ケルンテンとクラインとを包含すべきハンガリイ女王、ボヘミヤ、ティロールおよびブライスガウの主君としてのバイエルン選定侯、ニイダア・シュレジヤを併合するプロシャ、それから最後に、オーペル・シュレジヤとメーレンとによつて強大になるザクセン選定侯、この四人の隣人は永久に和解しないだらう。そしてフランスは、仲裁者の役割を引受けて、自ら任じた主権者を思ひのままに支配しようと心構へてゐた。さうなれば、共和政治の最もかがやかしい時代の、ローマ式政治が復活しただらう[14]。
つまり、諸領邦をたがいに戦わせて漁夫の利を得ようとする分割統治がフランスの本意であった、と大王は見抜いた。オーストリア継承戦争(1740-1748年)では、プロイセンとフランスは共闘したものの、次の七年戦争(1754-1763年)では、オーストリアが宿敵フランスと組むという外交革命が起きたため、プロイセンはひるがえってフランスとザクセンに先制攻撃を加えた。対外政策における大王の国家理性とは、勢力均衡を正しく計算して勝利を収めることである。自ら陸軍参謀として満州事変を計画した石原はこれを訳して何を考えたか?
実はフリードリヒ二世は内政でも国家理性に大きな足跡を残した。上で見た好戦的態度に反し、王太子時代に『反マキアベッリ論』を著して、人民の幸福を顧みないマキアベッリを批判した。即位してはじめは「人民第一の従僕」と自称して人民に奉仕しようとしたが、宗旨替えして「国家第一の従僕」と唱えるようになった。「人民」と「国家」の間にはニュアンスの違いはあるが、被治者の幸福を国家理性の目的としたのは同じである。穿った見方をすれば、幸福とは何か?、を定義するのは君主である彼自身であるから、それらの標語は自己正当化以外の何物でもない。オーストリア継承戦争や七年戦争での戦いぶりを、どうしてマキアベッリ的でないと言えようか?
そうした絶対君主と国民とのギャップが許容できなくなるのは、フランス革命が起きてからである。国力を強くするには国民の団結が必要であると考えられた。それは自由を掲げて絶対君主たちを敗退させたナポレオンの記憶が鮮烈であったからであろう。そうした感覚をよく伝えるレオポルト・フォン・ランケの文章を引用する。
すべての国家成員の自由意志に拠る完全な一致団結無しに国運の偉大な伸展が獲得されるなんてことは断じて有り得ないよ。国家成員を一致団結せしめるような理念の隠れた働きがあってこそ始めて巨大な共同体が漸次出来上がって来るんだ。一人の天才が現れてこうした理念の活動を指導するなら、それはなんと言う幸運なことだろう[15]。
以上の歴史では、国家と人々との関係は、すべて国家の側から決められた。それにたいし、個人、すなわち下からのニーズにより国家は作られるとする弁証法を考案したのはゲオルク・W・F・ヘーゲルであった。家族では足りないものを市民社会で補い、市民社会では足りないものを国家で補う。こうして人間が倫理的に生きるために不可欠な共同体としての国家が誕生した。とはいえ、国家が国民の福祉を精力的に追求すると、他国との戦争が避けられなくなる[16]。 ヘーゲルの時代では、国家間の抗争は望ましいことであった。全世界の人々のためにグローバルガバナンスを実現しようという発想はなかった、とは言わないが、あくまで国家を手段としてそれは実行されるのである。カントは実在の国家によらず、超越論的な世界市民論に思いをはせたが、20世紀でも政治哲学の主流にはならなかった。
[1] アリストテレス、『政治学』、牛田徳子訳、京都大学学術出版会、2001年、8ページ。
[2] プラトン、『ソクラテスの弁明・クリトン』、久保勉訳、岩波書店、1964年、81ページ。
[3] トマス・アクィナス、『君主の統治について―謹んでキプロス王に捧げる』、柴田平三郎訳、慶応義塾大学出版会、2005年、84ページ。
[4] フリードリヒ・マイネッケ、『近代史における国家理性の理念』、菊盛英夫、生松敬三訳、新装版、みすず書房、1976年。
[5] Ernest Mason Satow, Satow’s Guide to Diplomatic Practice, edited by Lord Gore-Booth and Desmond Pakenham, 5th. ed. (London: Longman, 1979).
[6] 高沢紀恵、『主権国家体制の成立』、山川出版社、1997年、35ページ。
[7] 桐生操、『王妃カトリーヌ・ド・メディチ』、新書館、1982年。
[8] 佐々木毅、『近代政治思想の誕生』、岩波書店、1981年、39-40ページ。
[9] ウィリアム・H・マクニール、『戦争の世界史 技術と軍隊と社会』、高橋均訳、刀水書房、2002年、184ページ。
[10] ヘンリー・A・キッシンジャー、『外交』、岡崎久彦監訳、日本経済新聞社、1996年、73ページ。
[11] 高沢、『主権国家体制の成立』、51ページ。
[12] Stephen D. Krasner, Sovereignty: Organized Hypocrisy (Princeton: Princeton University Press, 1999), pp. 79-81.
[13] Samuel Pufendorf, The Present State of Germany, trans. by Edmund Bohun (London: Richard Chiswell, 1696), pp. 152-154.
[14] フリードリヒ二世、『我が時代の歴史』、石原莞爾、国防研究会訳、中央公論社、1942年、125-126ページ。
[15] ランケ、「政治問答」、『政治問答 他一編』、相原信作訳、岩波書店、1941年、35ページ。
[16] 岩崎武雄編、『ヘーゲル』、中央公論社、1997年。
© 2026 Ikuo Kinoshita