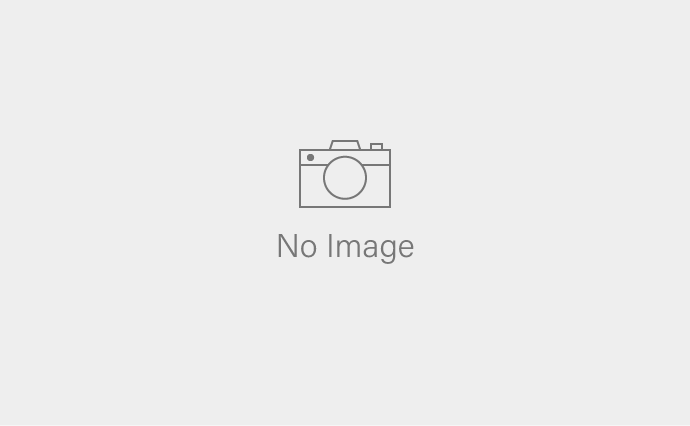カネは天下の回り物という。本来は、金銭は人々の手を転々と渡っていくものであるから、その持つ、持たないは時とともに変化する、という意味である。しかし、ここでは、金銭は人々の手を渡っていく中で、初めて付加価値の発生に貢献する、という意味で使っている。
経済学には、 流動性(リクイディティ)という用語がある。資産の処分しやすさ、というのがもともとの意味である。素人の描いた絵には値段が付かないが、名画ならばすぐに売れる。土地、金銀、あるいは現金の流動性はすこぶる高い。金銀を貯めこんでも宝の持ち腐れであるとはアダム・スミスが指摘したことである。経済を拡大したければ、カネを回すことを考えるべきである。流動性は実際には、マクロ経済学において通貨量のこととして使われる。経済の統計データには名目と実質があるが、名目の値を大きく左右するのがこの流動性である。
ここで、金本位制についての議論に入る。これまで人類が掘った金(きん)はプール数杯分、という言われ方をする。つまり、1年や2年でそれほど増えるものではない。となれば、金本位制を採用すると、通貨量という意味での流動性は増えにくいので、経済成長のボトルネックになる。大人が子供の服を着ているようなものである。そこで、金の量をドル紙幣で補い、各国国内ではそれぞれの不換紙幣が通用する金ドル本位制という方法が第二次大戦後は採られることになった。それも矛盾があらわになり、不換紙幣のみが使われる管理通貨制が現在の制度である。
21世紀には、ビットコインなど暗号資産というものが現れた。供給量が「採掘」によって増える点で金と似ているが、地質からの採掘でなく、実は電子計算である。難しいことは私にも理解できないが、資産として金とビットコインは米ドルをヘッジするものであるとはいえる。
それはともかく、金本位制は、金という世界共通の交換手段をつうじて国際決済ができる非常に便利な制度であった。金を自国の兌換紙幣と結びつけるには、中央銀行のコミットメントが必要である。コミットメントとは、兌換紙幣の価値を金の量に釘づけること、私人と無制限に金を売買すること、そして、金を法定の国際準備として保有すること、である[1]。このコミットメントによって、各国通貨間の相対的関係、つまり為替相場、はほぼ決定する。「ほぼ」というのは、金の輸送費を加味していないからである。下に金本位制のもとの為替相場の例を挙げる。
金1オンス=20.67米ドル
金1オンス=4.247英ポンド
1ポンド=4.866ドル[2]
為替リスクが小さいので、金本位制は国境をまたいだ貿易と投資を助長する。さらに、それには貿易収支を自動的に調節する機能があるとされる。輸出が増加すれば、または、輸入が減少すれば、金が国内に流入してその量が増え、物価は上昇する。他国は高い自国の品を買わなくなるから、今度は輸出は減少し、輸入は増加する。逆に、輸出減少や輸入増加で金が外国に流出すれば、物価は下がり、今度は輸出が増えて、輸入が減る。このように、金の輸出入は自然に収束していき、IMFのような国際機構が経済政策に介入しなければならないということはない、とされる。
もちろん、国際収支は貿易収支だけから成るのでなく、投資や利子・配当の収支もある。輸出が好調な産業に外国から投資が押し寄せれば、輸出はさらに伸びるであろう。また、国境を越えて移動するのはカネとモノだけでなく、移民もある。物価水準が高いということは賃金も高いということであるから、輸入品の代わりに移民労働者が来る。すると長期的には、輸入はあまり増えず、輸出も減らない。金本位制のもとでの貿易収支の自動調節は、あくまで理論的なものである。
今回のテーマは、ベルサイユ条約の「経済的帰結」と大恐慌後における国際協調の失敗を、通貨(金融)と貿易の側面に着目して論じなさい、である。
第一次世界大戦後の惨状は人的損失もさることながら、経済もひどいものであった。ハイパーインフレーションはよく例に出されるが、開戦から1923年11月までに、ドイツの貨幣の価値は1兆分の1に下落した。
ハイパーインフレーションは、生活を困窮させるだけでなく、貿易も難しくする。仮に、外国から商品を仕入れ、それを売った代金で支払いをするとしよう。外国通貨建てで振り出された手形に対して後日、銀行をつうじて支払いをすることになる。ところが、期日までに外国通貨の相場が倍になれば、売り上げで仕入れ費用をまかなうことはできない。輸入は止まることになる。
ただし、外国の通貨を借りることができれば、貿易決済の代金を支払うことはできる。紙幣を増刷して、インフレーションを加速することもない。これを実際に行ったのがフランスであった。大戦において勝利に貢献したことが英米に評価されていたからできたことである。しかし、借金がいつまで続けられるかは不安であった[3]。
当時、この指摘をしたのは、ジョン・M・ケインズであった。ドイツは賠償支払いのために、国際決済のための金を手放さなければならなくなった。他方、フランスはじめヨーロッパの国々は、戦費の調達を英米からの借款に頼り、返済の義務があった。ケインズは、立ち行かなくなると予言した。
―前略―満ち足りぬヨーロッパ諸国民が、ヨーロッパとアメリカ間のものであれ、ドイツと他のヨーロッパ諸国間のものであれ、自分たちの公正感や義務感から否応なく発しているのでもない理由に基づく外国への支払いのために、日々の生産物のかなりの部分を充当しうるように、今後一世代のあいだ自分たちの生活を律していこうなどという気に、いったいなるのであろうか[4]。
ケインズは第一次大戦のパリ講和会議では、イギリス大蔵省の代表を務めたが、連合国の対独賠償要求に反対して辞任した。その経験をもとに著したのが『平和の経済的帰結』である。平和というのは、ドイツとの講和のことである。「平和条約は、ヨーロッパの経済的復興のための条項を何一つとして含んでいない」と彼は告発した。さらに次のように戦勝国の指導者たちを皮肉っている。クレマンソーとは当時のフランス首相、ロイド・ジョージとはイギリス首相、そして、大統領とはアメリカ合衆国大統領T・ウッドロウ・ウィルソンのことである。
―前略―クレマンソーは敵国の経済生活を粉砕することに、ロイド・ジョージはうまく取引して、一週間ぐらいは国民の気持ちを宥めておけそうな何物かを自国に持ち帰ることに、大統領は公明正大でないことはいっさい何事もすまいということに、心を奪われていた[5]。
では、どうすれば経済は復興するとケインズは考えたのか? ベルサイユ条約を改正し、ドイツに対しては賠償を減額、ザール炭鉱を返還、上シュレジエンで住民投票、など報復色を薄める。連合国間では債務を棒引きする。アメリカ合衆国が世界各国に借款を与える。さらに、ソビエト連邦とは貿易を復活し、東ヨーロッパ・中央ヨーロッパにおいてドイツの経済的役割を認める、といった具合である。後世から振り返れば、穏当な提案であるものの、1919年当時においては寛大すぎた。
現実の世界は、時代の乱気流にもまれ、ついには統制を失った。1923年のルール占領は乱気流の一撃であった。賠償支払いが滞るドイツに対し、フランスとベルギーがルール地方を占領し、公私の財産を差し押さえ、その売却益を賠償の代わりとした。こうした経済生活の粉砕は憎しみを募らせるばかりで解決にならなかった。なぜなら、ドイツには金が本当になかったからである。
川に水を流そうとしても、源に水がなければ流れない。流れた先の海から水が蒸発し、雨になって源に降り注がなければならない。金は天下の回り物とはそのようなことで、どこかの国から金をドイツに持って行って、さらに世界経済のなかで幾度も回さなければ賠償は完済できなかった。
ルール占領の無益を知った1924年、恵みの雨をドイツに降らせる提案がアメリカ合衆国から発せられた。ドーズ案である。提案者のチャールズ・ドーズは後の副大統領であり、ノーベル平和賞にも選ばれた。ニューヨーク市場でドイツに対する公債を発行し、それを元手に稼いだ外貨で賠償の返済をさせる、というのが案の骨子であった。公債が募集されたニューヨーク外債市場は大いに発展した。
輸出の必要に駆り立てられるドイツにとって、ドーズ案は苦しかった。当時、ドイツのライヒスバンク総裁であったヒャルマル・シャハトは吐露している。
私には、ドイツがその産業を再建するには原料、食料、またある種の機械類を国外から輸入しなければならないことはよく分っていた。そのためには外国のクレディットを迎えることが絶対に賢明な策であった。―中略―ドーズ案によるわが国の支払年額は約二十億であった。これは外貨によらねばならなかった。その外貨の獲得は輸出超過による以外には道がなかった。さらに、今やこの新クレディットに対する利子と元金償却のための外貨を必要とするに到ったのであるから、わが国の対外債務は、あらゆる新外債をも含めて益々増大し、かくて我々の輸出努力の強化が益々必要となった[6]。
ドーズ案は1929年のヤング案によって改定される。大恐慌を受け、1931年のフーバー・モラトリアムによって賠償支払いは中断し、翌年のローザンヌ会議で消却された。この期に及んで、ケインズの言うことに耳を傾けなかったことを後悔した者もいたはずである。
希少な金をいかに確保するかは、日本にとっても課題であった。それは幣原外交の隠れた目的であった。幣原外交とは、1920年代から1931年まで外務大臣を務めた幣原喜重郎の政策である。国際協調路線などとくくられることもある。具体的には、中国に対する不干渉やロンドン海軍軍縮条約の締結のように、武力に訴えることを慎むことを基本とした。不干渉と軍縮によって、軍事費を削る経済的な意図があったとされる[7]。
このように、国家は輸出マシンとなって、たがいに金を奪い合った。金の量は決まっているので、勝者の影に必ず敗者がいるゼロサム・ゲームである。それでも、金本位制は貿易の復興に欠かせないとの認識に立ち、1922年のジェノバ会議は早期に金本位制に各国が復帰する指針を決めた。1925年に復帰したイギリスを皮切りに、主要国は1930年の日本を最後に金本位制に復帰した。これを再建金本位制という。
人類には、海に落ちるレミングの群のように恐ろしいハザードが待ち構えていた。1927年のポンドの危機がその始まりであった。イギリスはゼネストがあり、労働者の生活苦に目が行っていたため、自国通貨であるポンドの相場を下げたくなかった。フランスによる金買いは、過大評価されたポンドの相場を容赦なく下落させた。英仏独米の中央銀行は四か国会議を開き、アメリカ合衆国の金融緩和によって金を市中に吐き出させ、ポンドの下落を止めようとした。ところが、金融緩和の副作用として、ニューヨークの株式相場は高騰し、やがてはじけるバブルが膨らんだ。
ニューヨーク株式市場の暴落は、1929年10月の24日が暗黒の木曜日、29日が暗黒の火曜日と呼ばれる。58年後の1987年に起きるのはブラックマンデーである。ウォール街の惨状を伝える文章を引用する。
USスティールの暴落はひどいパニックを引き起こした。人々が口汚くののしり、突き飛ばしたり、小突いたり、ひっかいたりするので、ブリッジマンは第二ポストのなかに避難しなくてはならなかった。
あるメッセンジャー・ボーイは、群衆をかきわけていくうちに、不意に髪をぐいとひっぱられて動けなくなった。彼をつかまえている男は、破産したと金切り声をあげて、手を離そうとしない。恐ろしくなった若者はかろうじて身を振りほどいたが、つかまれていた髪の束は男の手のなかに残った。あまりの痛さに泣き叫びながら、メッセンジャーは取引所を逃げ出した。彼の髪の毛は二度とはえてこなかった[8]。
阿鼻叫喚の日から株価は各国で3年弱、下がり続けた。イギリスや日本は素早く戻したが、ほとんどの国は戦争が始まるまで回復しなかった[9]。これが大恐慌である。
長期的な不況の原因を、マネタリズムの指導者であり、シカゴ大学教授などを歴任したミルトン・フリードマンは金融政策の失敗という観点から説明する。すなわち、FRB(連邦準備制度理事会)の優柔不断、 銀行救済案の破棄、政府債の買いオペの拒否、そして公定歩合の引き上げである[10]。一言でまとめれば、市場に流動性を供給しなければならないところ、不足をもたらす真逆の政策を打ってしまった、ということである。
ケインジアンの説明を述べれば、有効需要を国家が積極的に作り出さなかったから長期的な不況になった、ということになる。その政策については「経済的ナショナリズム」の回で述べる。
これら経済学的な説明に対し、国際政治経済学は覇権安定論によって大恐慌を説明する。チャールズ・P・キンドルバーガーの有名な記述を引用する。
1929年不況が非常に広い地域に及び、著しく深刻であり、大へん長びいたのは、①投げ売りされる商品に対して比較的に開かれた市場を維持する、②景気調整的な長期貸付を行う、③恐慌のさいに手形を割引くという三点において、イギリスは国際経済を安定させるために責任を負う能力をもたず、アメリカはその責任を負う意思をもたず、そのため国際経済システムが不安定になったという理由によるものであった[11]。
①は売れない品物を誰かが買ってくれたら、生産者は被用者に賃金を払うことができ、経済全体が回復する、ということである。貿易の近隣窮乏化を不況の元凶と理解する。②の長期貸付は、例えば道路や鉄道といった大規模インフラストラクチャーのために資金を貸すことで、貸された国の労働者を失業から救うことができる。これはケインジアンの説明である。③は流動性の供給である。手形割引とは債権買い取りのことで、現金が今すぐ必要な事業者は倒産から逃れられる。関東大震災の際、決済が滞った手形が震災手形と呼ばれ、日本銀行が買い取ったが、これと同じ発想である。マネタリストの説明がこれである。以上は、諸学派の説を並べただけで、キンドルバーガーの独自性はない。
覇権安定論の特徴は、長期的不況からの救い手を覇権国、すなわちリーダー国家、に見いだす点にある。イギリスは金流出に悩んだのであるから、外国のモノを買ったり、カネを貸したりすることは不可能であった。アメリカ合衆国のほうは、ベルサイユ条約を蹴って、孤立主義のもとで繁栄していた。他国に手を差し伸べることが自らを助ける、と言われても、成功体験に反する余計なおせっかいであった。同国が孤立の誤りを反省して、世界を引っ張るのはヒトラーが世界征服に乗りだしてからのことであった。
大恐慌は供給過剰を招き、生産低下をもたらした。特にひどかったのはアメリカ合衆国であり、1929年から1930年の1年間と、1937年から1938年の1年間に、それぞれ約2割、低下した。ドイツとオーストリアも1929年からの1年間には1割を大きく超えて低下した。これに伴い失業率も、ドイツは3割を大きく超え、アメリカ合衆国も3割に近づいた[12]。
対策として多くの国では1930年代、経済的ナショナリズムの政策を採用した。それは大きく四つに分けられる。一つ目は. 近隣窮乏化あるいはブロック化によって貿易の扉を閉ざすことである。関税を上げて、他国の商品を自国で売れないようにする。具体例には、アメリカ合衆国のスムート・ホーリー法がある。自国通貨の為替を切り下げるのも、輸入品の価格を上げるので、同じ効果がある。いずれにせよ、他国は報復関税で応えるので、みるみる世界貿易は縮小した。キンドルバーガーが示したグラフでは、1929年1月から1933年1月までの4年間に世界貿易の金額は3分の1になった[13]。開かれた市場を維持する覇権国が存在しなかったからである。
ブロック化とは、自国の経済圏を拡大して自給自足を図ることである。もともと植民地を多く有していたイギリスは速やかにポンド・ブロックを築いた。すでに独立した元自治領との間でオタワ協定を施行して、低い帝国特恵関税を適用した。
ドイツと日本のブロックは、第二次大戦に直結した。ドイツはハンガリーやチェコスロバキアといった南東ヨーロッパに手を伸ばした。次の標的は東のポーランドであり、そこへの侵攻は世界大戦の序曲であった。日本はすでに植民地にしていた台湾と朝鮮に加え、満州と華北に侵攻した[14]。
近隣窮乏化とブロック化が大恐慌の原因であったことはまちがいない。しかし、それらをうまくやった国々は経済的に一息つくことができた。
ナショナリズムの二つ目は金本位制からの離脱であった。1931年にはイギリスはじめ多くの国が離脱した。大恐慌が始まってから金本位制に復帰(金解禁)した日本は金の流出が止まらず、1931年暮れに高橋是清が大蔵大臣に就いた翌日、慌てて金輸出を再禁止した。
世界経済の再建を目指した1933年のロンドン世界経済会議は失敗し、もはや、元に戻る筋書きは描けなくなった。すべての国が金を国外に出さないので、貿易は縮小するほかない。そうならないようにするには、ドイツがとった為替管理のようなやり方があるにはあった。次の引用は経済相を兼ねるようになったシャハトの回想である。バルカン諸国の農産物を高く買ってやって親独的にした、と述べている。
その後一連の諸外国との間に締結した貿易契約で、ドイツ側が輸入した代金はその国から借りた形に記入し、これでドイツの商品が自由に買えるようにしたのが清算勘定である。この方式は、とくにバルカン諸国や南米諸国に適用された[15]。
なぜ、金本位制から抜けなければならなかったか? 貴重な国際決済手段である金の流出を止めたいのはもちろんであるが、景気対策のためにも必要であったからである。金本位制のまま財政支出を増やすと、財政と貿易の収支が赤字になってしまう。金本位制から離脱すれば、不換紙幣を乱発し、財政赤字をインフレーションで軽減し、通貨安で貿易収支を改善できるからである。
高橋財政と呼ばれる日本の積極的な政策は、高橋是清の金輸出再禁止によって可能となった。低金利と日銀引受による国債発行によって流動性を供給したのはマネタリストの政策である。時局匡救と称する公共事業で有効需要を創出したのはケインジアンの政策である。これらはデフレーションからの脱却に一定の効果があった。ただし、国債でまかなわれた支出拡大のかなりの部分が軍事費に回され、対外関係の悪化という副作用まで生んだ。
他の二つのナショナリスティックな政策は、ニューディールまたはケインジアンの総需要政策と階級対立を緩和するための福祉国家政策である。繰り返すが、それらについては「経済的ナショナリズム」の回で述べる。
この回の最後に、カール・ポラニーの『大転換』(1944年)を取り上げ、大恐慌の意味を掘り下げる。その意味とは19世紀文明の崩壊である。
19世紀文明は四つの制度から成った。一つは勢力均衡であり、平和を望むロスチャイルド家などの金融業者が外交に影響力を行使し、平和の百年をもたらした。第2に、この回で論じた国際金本位制である。第3は自己調整的市場であり、商品価格・賃金・地代・利子といった諸価格が需要・供給で決まる。第4は自由主義国家である。
ポラニーによると、勢力均衡・金本位制・自己調整的市場・自由主義国家はユートピアであった。貿易ではゆっくりと保護主義が広がっていたが、ついに国際金本位制が崩壊すると、19世紀文明は次の文明へと大転換した。すなわち、勢力均衡は戦争へ、金本位制は国民通貨へ、市場と国家の自由主義は干渉主義・ファシズム・ニューディールへと移行した[16]。一言で表現するなら、市場の時代から国家の時代へと変わったのである。 若干、筆者の解釈を加えると、19世紀文明はユーロセントリズムであり、金地金はその上流階級の共有財産であった。ところが、ソ連の共産主義とアメリカ合衆国のパンアメリカニズムが台頭し、さらに労働者階級が政治進出を果たすと、平等な分け前を要求し、金本位制のルールは立ち行かなくなった。発言権を増した多種多様なアクターたちの利益を集約するメカニズムが本当は必要であった。ロスチャイルド家の広大な血脈でさえ不十分であり、国際連盟は各国の右翼に支持されなかった。新旧の勢力はそれぞれ共産主義とファシズムに身を投じ、新秩序を作ろうと企てた。そのさまを「経済的ナショナリズム」の回で見る。
[1] Paul R. Krugman and Maurice Obstfeld, International Economics: Theory and Policy, 4th (Reading: Addison-Wesley, 1997), p. 513.
[2] 山本栄治、『国際通貨システム』、岩波書店、1997年、9ページ。
[3] J・M・ケインズ、『平和の経済的帰結』、早坂忠訳、東洋経済新報社、1977年、154、191ページ。
[4] ケインズ、『平和の経済的帰結』、220ページ。
[5] ケインズ、『平和の経済的帰結』、143ページ。
[6] H・シャハト、『我が生涯』、上、永川秀男訳、経済批判社、1954年、421-422ページ 。
[7] 佐古丞、『未完の経済外交 幣原国際協調路線の挫折』、PHP研究所、2002年。
[8] G・トマス、M・モーガン=ウィッツ、『ウォール街の崩壊』、下、常盤新平訳、講談社、284-285ページ。
[9] C・P・キンドルバーガー、『大不況下の世界 1929-39』、東京大学出版会、1982年、98ページ。
[10] ミルトン・フリードマン、ローズ・D・フリードマン、『選択の自由 自立社会への挑戦』、西山千明訳、日本経済出版社、2002年、185-222ページ。
[11] キンドルバーガー、『大不況下の世界 1929-1939』、264ページ。
[12] キンドルバーガー、『大不況下の世界 1929-1939』、254ページ。Paul Bairoch, Economics and World History: Myths and Paradoxes (Chicago: The University of Chicago Press, 1993), p. 11.
[13] キンドルバーガー、『大不況下の世界 1929-1939』、148ページ。
[14] キンドルバーガー、『大不況下の世界 1929-1939』、253、255ページ。
[15] シャハト、『我が生涯』、下、118ページ。
[16] カール・ポラニー、『大転換―市場社会の形成と崩壊』、吉沢英成、野口建彦、長尾史郎、杉村芳美訳、東洋経済新報社、1975年。
© 2026 Ikuo Kinoshita