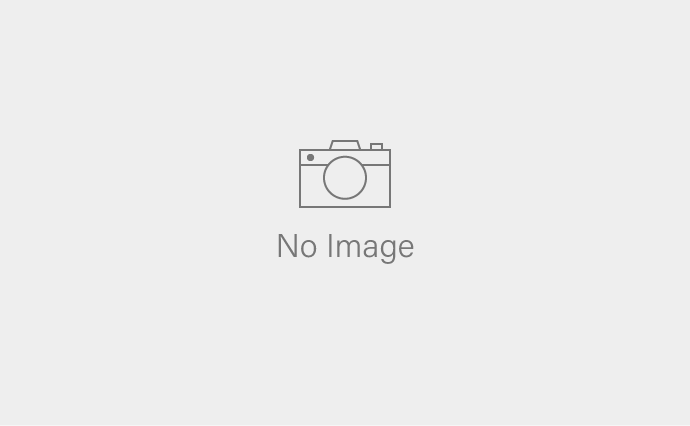人間の注意が自らの周囲にしか行き届かないのであれば、よその国まで経営する帝国主義は資源を有効活用できない。それゆえ、抑圧された人々が一斉に立ち上がることになれば、経営の損得勘定はたちまち行き詰まる。それにもかかわらず、一時代、世界を覆いつくしたのは、単に戦争に勝っただけでなく、経済的利益と政治的支配を巧妙に両立し、強者に都合よい思想、つまりヘゲモニー、を使って正当化したからである。今回のテーマは、帝国主義時代の植民地化について、武力行使をめぐる国際規範と経済的背景に言及しながら論じなさい、である。
列強による世界の分割は帝国主義の一面にすぎなかった。それは工業、資源、海軍、陸軍、そして貨幣を融通無碍に変化させる錬金術でもあった[1]。典型的な例はインド・ベンガルからの収奪であった。ナワーブという操り人形のインド人君主がいたものの、イギリスの東インド会社が防衛、徴税、警察、そして司法の実権を握っていた。彼らはインド人からの税収で物産を購入し、海外で売りさばいて会社の利潤にするノーリスクの事業を行った。イギリス政府は東インド会社に、40万ポンドを本国に納めることを1767年に命令した。
1858年に東インド会社は解散した。しかし、20世紀初めにおいても、イギリスの経常収支はインドでの収奪を前提とした。北米およびヨーロッパに対する赤字をインド、日本、オーストラリア、そしてトルコに対する黒字で補填していたのである[2]。
他方、投資という観点から見れば、ヨーロッパは必ずしも収奪ばかりをしたわけでなかった。ロンドンは一次産品の国際取引所となり、「世界の手形交換所」や「世界の銀行」と呼ばれた。銀行の間でも役割分担ができていた。例えば、ロスチャイルド家は外国政府のために外債を発行し、マーチャントバンクのベアリング商会は産業に投資する、といった具合である。イギリスは綿花についてはアメリカ合衆国とエジプトに、鉱業についてはラテンアメリカに投資した。フランスはシベリア鉄道をはじめ大陸ヨーロッパの事業に融資した。鉄道ネットワークは先進国だけでなく中南米やインドにおいても急速に広がった。
投資を受け入れた諸地域のうちでも、ラテンアメリカは19世紀後半、きわめて高い1人当たりGDP成長率を見せた。勢いはアジアとアフリカはもちろん、南ヨーロッパをはるかにしのいだ[3]。19世紀におけるカネのグローバリゼーションが途上国の開発に寄与した面もあった。
こうした経済現象を背景に進んだのが、植民地化、すなわち白人にとってのより快適な居住、であった。快適な居住というのは、気候風土に始まり、法制度、宗教を基盤とする習俗、新聞などのメディア、さらには競馬場といった娯楽に至る。夏の暑さが厳しければ、高原の避暑地や海辺のビーチを白人は開発した。
では、どのように白人は植民地を支配したのであろうか? 一つは操り人形の君主制である。現地人の支配階級は君主と一部官僚にすぎず、陰の実力者は宗主国の高等弁務官(あるいは大使・総領事・政務官・駐在官)と軍司令官であった。宗主国は利権と債権をつうじて財政までも支配した。もはや白人を脅かす現地勢力はなく、安心な暮らしが保証された。
快適な居住を約束する法制度は治外法権であった。白人には現地人と違い、文明世界のルールが適用された。白人の裁判が白人の領事官によって行われる領事裁判権の制度はとりわけ効果的であった。ほかにも、免税・不逮捕・国旗掲揚といった特権免除があった。これらは白人に雇われた現地人の被保護者(プロテジェ)にも、代理領事への任命をつうじて与えられた。不平等への憤りが、次世代のナショナリストたちを育てた。
中南米が植民地化されることなく、ほとんどが独立を保ちえたのは、比較的に小さな修正で白人が投資する環境が整えられたからである。スペインやポルトガルの植民地であった時代に、法制度や習俗の西洋化が進んでいた。たまに操り人形になるのを拒む大統領が現れ、ならず者の意味をこめてカウディーリョと呼ばれた。列強は砲艦外交によって紛争を解決した。
帝国主義の先触れはスエズ運河の建設である。それが所在するエジプトは形の上ではオスマン帝国の領土に含まれた。実際には、サイードというエジプト総督(後に副王)が支配者であった。彼はフランス人のフェルディナン・M・ド・レセップスに建設の特許状を発行した。運河が開通したのは1869年である。
サイード自身もスエズ運河会社の大株主であった。彼の死後、株をイギリス政府に売って後継者は自らの借金を返済した。時のイギリス首相デイビッド・ディズレイリは株を買い取る資金をロスチャイルド家から借り入れた。ウィットをきかせて、担保はイギリス政府である、と彼は伝えたが、政府を担保に入れるほど運河は重要であった。虎の子の植民地インドと地中海とをつなぐ大動脈が他国に支配されれば、インドの支配が脅かされるからである。イギリス政府は最大の株主となり、フランス人の小口株主たちとともにスエズ運河会社の経営権を握った。
運河の経営だけでイギリスは満足しなかった。1882年、エジプトで外国人が襲撃された。フランスが誘いに乗らなかったので、イギリスは単独で軍隊を派遣した。駐留軍が居座ったことで、エジプトの副王は操り人形になりさがり、イギリスの総領事兼外交事務官が真の支配者になった。白人の安心な暮らしとビジネスが保証され、綿花の生産がエジプトの主要産業に発展した。
第一次世界大戦でトルコが敵国になると、イギリスは遠慮なくトルコの宗主権を否認し、副王をスルタン(王)に昇格させた。真の支配者の階級も高等弁務官に格上げされた。その後、両国の関係は、保護権が廃止されて対等の主権国家になったり、同盟条約が結ばれたり、高等弁務官が大使に格上げされたり形は変わっても、エジプトは植民地のままであった。イギリス軍はカイロとアレクサンドリアに駐留し、運河地帯への駐兵権を持っていた。
スエズ国際海水運河株式会社の株主総会と理事会はパリで開かれた。しかし、特許状の定めにより、運河会社は1969年に解散され、資産はエジプトに移ることになっていた[4]。本当に運河はエジプトに返還されるのか? 1956年にスエズ戦争が起きるまえ、誰もこの疑問に答えられなかった。
植民地化のテクニックはこの事例で明かされている。1882年の外国人襲撃は決定的であった。白人を保護できなければ、国家責任を問うため武力行使するのが当時の常識であった。国家責任論、すなわち植民地化を「される側」が悪いという論理、が国際法の一部であった。国家は自らの不法行為、すなわち故意・過失による損害、に責任を負う。契約不履行、不法な殺傷・逮捕・財産権侵害、裁判拒否、そして反乱に対する相当な注意義務違反がそうした不法行為の典型的なものであった。債務不履行、公債不履行、そして役務代金不払も武力行使の理由になった。賠償金を払ったり、保護国化に同意したりすることが責任の取り方であった。
アメリカ合衆国はキューバでの武力行使の大義名分に圧制の除去と民主主義を挙げたが、付け足しの理由にすぎなかった。きっかけはスペインへの反乱から自国民を保護するために派遣された米国軍艦メイン号の爆発であった。原因は事故とも、スペイン側の仕掛けたものとも、アメリカ合衆国側の自作自演とも言われるが定かでない。イエロージャーナリズムと呼ばれた好戦的な世論が合衆国で高まり、ついに米西戦争(1898年)が勃発した。圧倒的な勝利の結果、合衆国はキューバを保護国化したのみならず、プエルトリコを属領化し、フィリピンを植民地化した。
義和団事件の端緒も自国民保護である。日清戦争以後、列強は鉄道敷設はじめ利権漁りを加速した。ドイツの場合は、ビールの名産地になる青島を含む山東省の膠州湾を自国民保護の理由で1897年に占領し、利益範囲とした。これが排外主義の火に油を注ぐ結果となり、義和団という武装勢力が宣教師や外交官を殺し、北京に迫った。清は義和団の側につき、列強に宣戦を布告した。列強の八か国連合軍は義和団と清を蹴散らし、翌1901年に北京議定書(辛丑和約)を結ばせた。
清が支払うことになった莫大な賠償額の算定に当たっては、清の関税徴収を取り仕切ってきたイギリス人官吏の意見を聴いた。つまり、いくらまでならば清は払えるかを見積もって、最大限、払わせたのである。まるで鶏が産む卵をことごとく横取りするようなもので、国家の家畜化であった。良心がとがめたのか、アメリカ合衆国は、受け取った額の一部を現在、中国一、二を争う名門である清華大学の設立に拠出した。
1902年のベネズエラ封鎖は債権回収を目的とした。ドイツは「威信」を守るためと称し、1898年以降の革命および反乱の期間に累積した債務不履行や損害の総額を請求した。大きなところでは、ドイツ国民が経営する食肉処理場とその債権者に対するカラカス知事の契約不履行や、大ベネズエラ鉄道をめぐる債務不履行といった経済取引をめぐるものがあった[5]。
これに対する反発は米州から起きた。かねてより、債権回収に武力が行使されたラテンアメリカでは、カルボ・ドクトリンが叫ばれてきた。カルロス・カルボというアルゼンチンの国際法学者・外交官は、私人は外国政府との契約上の紛争において自国政府に介入を求めない、ということを国際法の原則として唱えた。
カルボの後輩に当たるアルゼンチン外相ルイス・ドラゴはベネズエラ封鎖に対し、「政府の債務は武力干渉もヨーロッパの国による米州諸国領土の占領も招かない」という原則を声明した[6]。政府が自国民の保護のための外交をすることを外交的保護権というが、債権回収のために武力を使う外交的保護権を否定するのがドラゴ・ドクトリンである。
次の年、アメリカ合衆国の仲介により、ドイツにイギリスとイタリアが加わった請求国とベネズエラの間に議定書が結ばれた。やはり関税収入を支払いに充て、混合請求委員会による仲裁で私人への分配額を決定することになった。
アメリカ合衆国大統領はシオドア・ローズベルトであった。前政権で海軍次官を務めていたところ米西戦争が起き、志願兵としてキューバに渡り、ラフライダーという部隊で戦った。大統領となってからの棍棒外交というあだ名からも知られるように、彼にはタカ派のイメージがある。ベネズエラ封鎖事件では、1904年暮れにローズベルト・コロラリーと呼ばれることになる発言をした。
慢性的な不法行為や無能が文明社会の絆にひびをいれれば、米州であれ、どこであれ、最終的にはどこかの文明国による干渉を必要とすることもある。合衆国は西半球でモンロー・ドクトリンを奉じており、こうした不法行為や無能が目に余れば、不本意ではあるが、国際警察権力の行使を余儀なくされるかもしれない[7]。
これは単に不法行為や債務不履行を許さないということだけではない。モンロー・ドクトリンはヨーロッパによる米州の植民地化を禁じており、それにつながりかねない列強の干渉は好ましくない。よって、アメリカ合衆国自身が干渉をするというのである。いわば、米州を自らの勢力範囲であると宣言したようなものであった。一方で、ラテンアメリカがキューバとプエルトリコを除き植民地化を免れたのはこの原則の成果と言って過言でない。
モロッコにも列強は手荒く圧力をかけ、責任を果たせないと認定して独立を奪った。1905年にドイツ皇帝ビルヘルム二世はタンジールに上陸した。翌年、フランスは国政の改革を求めてアルヘシラス会議を開いた。次の年に外国人が襲撃され、フランス軍が居留民保護のために上陸したカサブランカ事件が起きた。これでモロッコはフランス保護領、スペイン保護領、そしてタンジールに三分割されていく。
露骨な帝国主義に対抗し、国際法で武力行使を禁止しようとする運動が高まりを見せた。1907年、ポーター条約(契約上の債務回収の為にする兵力使用の制限に関する条約)が結ばれた。契約上の紛争にかぎり武力行使を禁じたものである。実際の効果は疑わしく、適用範囲が契約に限定されたばかりか、第2条で、仲裁で解決する努力をすれば、それがうまくいかなくても武力行使をしてもよい、という抜け穴が用意されていた。
別の動きにカルボ条項があった。これは上のカルボ・ドクトリンを進出企業と現地政府との契約のなかに明記するものである。あらかじめ、自国政府に頼らないことを企業側に約束させて、外国の干渉を阻止しようと現地政府は企んだ。しかし、国際法の学説では、私人の利益を外交的に保護する権利は国籍がある国家の側にあり、国家の権利は私人により放棄できるものではない、とカルポ条項の効果を否定する意見がある。
より決定的な動きは1945年の国際連合憲章である。その第2条4に、「すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。」とある。国家責任を問うための武力行使は国際連合の目的と両立しないであろうから許されないし、植民地化の結果も当然、政治的独立を奪うことになる。
さらに、外国人への特別扱いを否定する動きがあった。1974年に国連総会で決議された国家の経済的権利義務憲章(A/RES/3281)がそれである。総会決議であるため、それ自体で法的拘束力があるわけでないが、国際世論の状況を示すものではある。第2章第2条2(a)に、「いかなる国家も外国投資に対し特恵的待遇を与えることを強制されない。」という文言がある。つまり、自国民に与えないものを、なぜ外国人に与えなければならないのか、という国内標準主義の主張である。帝国主義時代に列強が、これはあなたの国の責任であるから償いなさい、と文明国標準主義に拠って弱者に押し付けたことを想起すると、弱者の意見に耳を傾けさせるこの条項は隔世の感がある。
これまで見てきたような帝国主義の原動力とは何であったのか?
古典中の古典と言うべきジョン・A・ホブソンの『帝国主義論』(1902年)は、帝国主義の原因は私的な特殊利益である、と論じる。具体的には、牧場経営者、銀行家、高利貸し、投資家、醸造業者、鉱山所有者、製鉄業者、造船業者、海運業者、輸出品製造業者、貿易商、宣教師、学校、労働組合、陸海軍人、在外公館員、そして技術者など得をする者たちが団結した結果とする[8]。
ホブソンの説としてほかに有名であるのは、帝国主義は過剰生産のはけ口という理論である。国内の富裕層は消費性向が低いので、国外に市場を作って買わせなければならない。市場を求めて、という点は、カルテルやトラストが国内の独占・寡占を維持しながら外国で商品を売りさばく必要を論じたヨゼフ・A・シュンペーターの説明と共通する[9]。
経済的利益のなかでも、金融資本を帝国主義の元凶とする見方が根強い。金融資本の影響があったことは事実である。帝国主義末期に「ドル外交」という言葉が流行した。そのころのエピソードに次のようなものがある。ちなみに、シフは日露戦争の際、高橋是清の融資依頼に応じたユダヤ人として有名である。
―前略―クーン・ローブ商会が関税を担保にドミニカ共和国への融資を検討した際、同商会のジェーコブ・シフがロンドンの業務提携先に「向こうが借金を返さない場合、誰がこの関税を徴収するのだ?」と問い合わせたら、「お宅の国か、わが国の海軍さ」と答えが返ってきたという[10]。
金融資本への警戒は古くからあり、1879年、世界一周中のユリシーズ・S・グラント前アメリカ合衆国大統領が明治天皇に謁見した折、次のように助言した。
凡そ国の最も厭うべきは外国に債を負うより大なるは無し―中略―誠に埃及西班牙又は土耳古を見よ其景況実に憐む可し一国の財源は皆悉く外国の抵当と為り一も我所有と称するを得へきものなきに至る而て埃及の藩王は外国に其譲位を迫られ又西班牙の如きは莫大なる外債の為に各種の内国税を非常に増収し加之上下の税吏私曲を逞し堂々たる富国も殆ど将に衰亡せんとするの勢なり[11]。
ウラディミル・レーニンの壮大な理論も金融資本を重視する。1916年に書かれたものであるから世界大戦はすでに始まっていたが、世界の分割を金融の論理がもたらしたと彼は説明する。国内への投資ではもはや利潤率が低下したため、金融資本は高い利潤率を求めて外国に出ていかなければならない。投資は保護されなければならないので政治的な支配が必要になる。こうして、資本主義の最終段階としての帝国主義が進んでいく[12]。
投資と政治的な支配との関係が強く主張された分野といえば鉄道の敷設である。ドイツの帝国主義として知られる3B政策は、ベルリン、ビザンティウム(イスタンブール)、そしてバグダッドを鉄道で結ぶ構想であった。第一次世界大戦においてドイツ、オーストリアハンガリー、そしてトルコは中央同盟諸国としてともに戦うことになった。
オーストリアハンガリーは仮想敵国ロシアの友邦セルビアを通らずに、ヨーロッパとトルコを結ぶ計画を立てた。その路線は1908年に併合したばかりのボスニアヘルツェゴビナを通って、コソブスカ・ミトロビツァからテッサロニキに至るものであった[13]。次の皇帝となる予定であったフランツフェルディナント大公が暗殺された場所がボスニアヘルツェゴビナのサラエボであったことはよく知られる。同国が無理をしてでもボスニアヘルツェゴビナを支配する必要があった理由が鉄道計画の存在であったとしても不自然でない。
投資ではなく、資源獲得の必要が、国家を対外進出させ、紛争につながるという学説もある。アメリカ合衆国では、ナズリ・シュクリとロバート・C・ノースが計量分析を行った。人口でも、GDPでも、エネルギーでも、国家の成長は資源需要を増大させる。するとその国は対外進出を図り、軍事力を増強する。国々は衝突し合うようになり、ライバルの国も軍事力増強によって応える。シュクリとノースは、ドイツの成長とその結果としての第一次大戦に注目した[14]。
以上のように、帝国主義においては、巧妙に経済的利益と政治的支配が両立される。日清戦争後、帝国主義に参加した日本はどうであったか? 必死に政治的支配を確立しようとしたが、それで多くのものを失ってしまった。韓国併合を振り返ってこの回を締める。
日清戦争によって朝鮮を清の属国から独立国にする目的を果たした日本であったが、陸奥宗光外相が『蹇蹇録』でどう述べようと、それが真の最終目的であったかは疑わしい。清に代わって、ロシアという強敵が現れた。親ロシアの王妃である閔氏を三浦梧楼公使が首謀者となって殺害したことで、王はますますロシアに頼ることになってしまった。さらに、ロシアは義和団事件に世界が目を奪われている間に、満州を占領し、軍事圧力を強化した。
対する日本はイギリスと同盟を結び、どうにか日露戦争に勝利できた。戦中に第一次日韓協約、戦後に第二次日韓協約で保護権を確立した。
ところが、朝鮮の支配は完成しなかった。保護権にもかかわらず、韓国皇帝は独自外交を目指し、第2回ハーグ平和会議に代表を送ったのである。日本はこれを残念として、第三次日韓協約を押し付け、統監を送って直接統治に切り替えた。さらに、統監の伊藤博文が暗殺されると、韓国を併合した。李氏の王朝を操り人形にすることに失敗したのである。 その後も宣川事件や三一事件といった抵抗は収まらなかった。以上の歴史は、政治的支配と経済的利益を両立させる帝国主義の目標を日本が達成できなかったことを物語る。
[1] See Paul Kennedy, Strategy and Diplomacy, 1870-1945 (London: Fontana Press, 1984).
[2] S・B・ソウル、『イギリス海外貿易の研究』、久保田英夫訳、文真堂、1980年、81ページ。
[3] アンガス・マディソン、『世界経済の成長史1820-1992年』、金森久雄監訳、政治経済研究会訳、東洋経済新報社、2000年、9ページ。
[4] 今尾登、『スエズ運河の研究』、有斐閣、1957年。小林元、『国際政治と中東問題』、故小林元教授遺著刊行会、1964年。
[5] Holger H. Herwig, Germany’s Vision of Empire in Venezuela, 1871-1914 (Princeton: Princeton University Press, 1986), p. 99.
[6] The United States Department of State, Papers Relating to the Foreign Relations of the United States, with the Annual Message of the President, 1903 (Washington: Government Printing Office, 1904), p. 4.
[7] Theodore Roosevelt’s Annual Message to Congress, December 6, 1904.
[8] ホブスン、『帝国主義論』、上、矢内原忠雄訳、岩波書店、1951年。ホブスン、『帝国主義論』、下、矢内原忠雄訳、岩波書店、1952年。
[9] ホブスン、『帝国主義論』、上。ホブスン、『帝国主義論』、下。シュンペーター、『帝国主義と社会階級』、都留重人訳、岩波書店、1956年。
[10] ロン・チャーナウ、『モルガン家』、上巻、青木栄一訳、日本経済新聞社、1993年、176-177ページ。
[11] 外務省編、『日本外交年表並主要文書 上』、原書房、第5版、1988年、76ページ。カタカナはひらがなに、旧字体は新字体に改めた。
[12] レーニン、『戦争と平和、帝国主義』、平野義太郎編、大月書店、1970年。
[13] ハーバート・ファイス、『帝国主義外交と国際金融 1870-1914』、柴田匡平訳、筑摩書房、1992年、238ページ。
[14] Nazli Choucri and Robert C. North, Nations in Conflict: National Growth and International Violence (San Francisco: W. H. Freeman and Co., 1975), p. 29.
© 2026 Ikuo Kinoshita