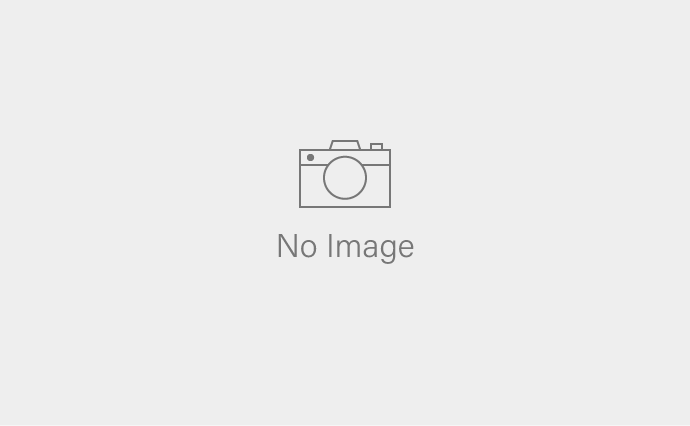幸福も、自由も、ともによいものである。哲学者も、政治家も、宗教家も、皆、よいと言うものであるから、もはや、ほめられも、けなされもされなくなった。しかし、よいものはよいものである。問題は、幸福と自由では、いずれがよいか?、である。グローバルガバナンスについて論じる本書は、その指針としてすぐれているのはいずれか?、の問いに答える義務がある。
今回は、幸福をガバナンスの指針とすることの長所と短所を吟味しなさい、がテーマである。
国家の目的は、福利とか、福祉とか、英語のウェルフェアから訳されるものを増進することである。そのように諸国の憲法には書いてある。もちろん日本国憲法にも、である。1787年のアメリカ合衆国憲法が最初であろう。この理念は君主制をとる国も巻き込んで広がった。
ジェレミー・ベンサムはイギリス人であったが、彼の『道徳および立法の諸原理序説』は1789年に公刊された。執筆はアメリカ合衆国憲法の制定やフランス革命とほぼ同時期である。
「最大多数の最大幸福」という『道徳および立法の諸原理序説』の一句は功利主義のスローガンとして有名である。「最大多数」が王侯貴族以外の平民を加えたなかでの多数であることは明白である(もっともはじめは財産資格が課された)。立法は国民の代表である議会で行われることであるから、功利主義は到来した議会制民主主義の要請に応えた思想であった。
分かりやすい「最大多数」に対して、「最大幸福」のほうは当時はもちろん、今日でも分かりにくい。幸福とは快楽から苦痛を差し引いたものである、とベンサムは説明する。功利主義という呼び名は功利性(ユティリティ)という用語に由来する。同じ単語が経済学では「効用」と訳され、基本概念として扱われる。彼は次のように解説する。
功利性の原理とは、その利益が問題となっている人々の幸福を、増大させるように見えるか、それとも減少させるように見えるかの傾向によって、または同じことを別のことばで言いかえただけであるが、その幸福を促進するようにみえるか、それともその幸福に対立するようにみえるかによって、すべての行為を是認し、または否認する原理を意味する[1]。
つまり、事物が幸福をどれだけ上げるか、下げるか、が功利性である。経済学では、人は効用が高い財やサービスを選好する、という言い方をする。しかし、ここでは経済学の語感を弱めるために、人は功利性が高い事物から幸福を得る、と表現したい。図式化すると次の流れになる。経済学を学んだ人は括弧内の用語のほうがなじみ深いであろう。
事物(財) → 功利性(効用) → 幸福(厚生) → 行為(経済活動) → 事物(財)
人間はこうした高い幸福を与える事物を得るために行為をする。逆に言えば、高い幸福を与えるにもかかわらず、ためらったり、やりすごしたりして、その事物を得るために行為することを怠ることはない。ベンサムにとっては、人が功利性の高い事物を得るために行為をすることは自明の理である。本能と呼んでもよい。受け入れがたいかもしれないが、この方法論は、個人主義とか、合理主義とか呼ばれ、社会科学全般の基礎になっている。彼自身、これが論争の的になることに気づいていたらしく、開き直る。
その原理について、なんらかの直接の証明ができるであろうか。それは不可能であるように思われる。なぜならば、他のすべてのことを証明するために用いられる原理は、それ自体としては証明不可能のものであり、証明の連鎖は、その出発点を別のところにもたなければならないからである[2]。
筆者も、功利性原理を正面から証明することは避けておく。自明の理や本能的なことはトートロジーであって、定義のなかに証明されるべきことが含まれてしまっているからである。
さて、これまでは個人の幸福の話であった。一つ前の「功利性の原理」で始まる引用のなかに、「すべての行為」という言葉が出てきた。実は、この言葉は下の引用の伏線である。
私はすべての行為と言った。したがって、それは一個人のすべての行為だけではなく、政府のすべての行為をも含むのである[3]。
ようやく、政府が実現すべき目標である最大多数の最大幸福につながった。ベンサムにとっての政府とは、特権階級の道具でなく、代議制民主主義のものであることははっきりしている。全国民に幸福を与える立法を行うことが政治家の義務とされる。これが彼の革命性であり、19世紀にわたって信奉者を得た理由であった。では、最大幸福を実現するため、政府はどのような手段をとるのか?
政府の仕事はガバナンスと言い換えられる。つまり、ガバナンスの手段は刑罰と報償である。刑罰、すなわち否定的制裁、は苦痛を与えることによって、人々の行為を抑える。他方、報償、すなわち肯定的制裁、は快楽を与えることによって、人々の行為を促す[5]。大ざっぱであるが、無機的な機械ではなく生身の人間にとってのガバナンスとは何か?、の本質を突いている。
こうした功利主義を世界に拡大して、グローバルガバナンスの指針として採用することは無理ではない。例えば、国際連合が人類の最大多数の最大幸福のために制裁を発動するというイメージは、理想としては通用する。また、功利主義をマクロ経済学的に解釈すれば、最大多数の最大幸福は人々の消費の総額によって近似されよう。世界銀行の統計に表れる世界総消費の成長率をグローバルガバナンスの目標にすればよく、実際、似たことが行われてきた。
このように、ベンサムの理論は230年あまりまえのものであるにもかかわらず、直観的にはそれほどおかしなものではない。しかし、功利主義はさまざまな問題点が指摘されている。人間だけでなく、環境のことも考えるべきでないか? 立法に携わる政治家たちは、現実には、最大多数の利益を第一にしていないのでないか? さらに冷笑的に問えば、立法というものは社会の現実を変える力を持たないのでないか?
早い批判者の一人が功利主義の継承者であるジョン・スチュアート・ミルである。日本語の訳にも問題があるのではあるが、「快楽」というと、刹那的で肉体的なものが連想される。ミルは、ギリシャの快楽主義者であるエピクロス派が「豚」とあざけられた故事を引き、同派が、そしてミル自身も「精神的な快楽を肉体的な快楽以上に尊重した」と反論する[6]。そして、あの有名な、しかし、見下した感じのする対比を言い放つ。
満足した豚であるより、不満足な人間であるほうがよく、満足した馬鹿であるより不満足なソクラテスであるほうがよい。そして、もしその馬鹿なり豚なりがこれとちがった意見をもっているとしても、それは彼らがこの問題について自分たちの側しか知らないからにすぎない。この比較の相手方は、両方の側を知っている[7]。
この議論は、幸福や快楽にはさまざまな次元があって、集計したり、合成したりするのは一筋縄ではいかないことを明らかにした。かのエイブラハム・H・マズローによる基本的欲求のヒエラルヒー説は、こうした多様性を咀嚼・吸収する名案といえるであろう。低次ではあるが、生存には欠かせない生理的欲求が最も強い。安全の欲求や所属と愛の欲求も、誰もが持つものである。さらに、承認の欲求、自己実現の欲求へと高次になるにつれて、満たされた一部の者だけが経験しうる境地へと上っていく[8]。
衣食住はまぎれもなく生理的欲求の対象である。1970年代に世界銀行は、それらを教育などと並んで基本的人間ニーズ(BHN)と呼んで重点的に援助した。貧しい開発途上国では、低次の欲求が満たされていないことを直視した結果である。開発途上国の人々の幸福は最低限の生活を保障することである、という議論には説得力がある。
これと似た考えをしたのがノーベル経済学賞を受賞したアマルティア・センである。次の引用で「生活の良さ」と訳されるウェルビーイングは、心身の調子が良いことであるので、最低限度の健康な生活と言い換えられる。
個人の福祉は、その人の生活の質、いわば「生活の良さ」として見ることができる。生活とは、相互に関連した「機能」(ある状態になったり、何かをすること)の集合からなっていると見なすことができる。このような観点からすると、個人が達成していることは、その人の機能のベクトルとして表現することができる。重要な機能は、「適切な栄養を得ているか」「健康状態にあるか」「避けられる病気にかかっていないか」「早死にしていないか」などといった基本的なものから、「幸福であるか」「自尊心を持っているか」「社会生活に参加しているか」などといった複雑なものまで多岐にわたる。ここで主張したいことは、人の存在はこのような機能によって構成されており、人の福祉の評価はこれらの構成要素を評価する形をとるべきだということである[9]。
彼の言う「機能」というものは何か目的の役に立つというより、心身が障害なく作動していることを表現している。この引用の部分を受けて、有名な概念であるケイパビリティ(潜在能力)が説明される。栄養、健康、病気、幸福、自尊心、そして参加といった、上で挙げられた各機能のリストとその達成度は、皆が画一的でなければならないわけでなく、個人が選択する自由がある。引用する。
これは、人が行うことのできる様々な機能の組合せを表している。従って、潜在能力は「様々なタイプの生活を送る」という個人の自由を反映した機能のベクトルの集合として表すことができる。財空間におけるいわゆる「予算集合」が、どのような財の組合せを購入できるかという個人の「自由」を表しているように、機能空間における「潜在能力集合」は、どのような生活を選択できるかという個人の「自由」を表している[10]。
つまり、ケイパビリティは実現可能な諸機能の組み合わせの範囲であり、センにとっての自由とは機能間の配分が選択できるということにすぎない。喫煙のようにウェルビーイングに寄与するとは考えられない行為は、彼の定義する自由の範囲外にある。いくらセンが選択の自由を強調しようとも、その長いリストに喫煙は入りそうもない。
ある種の福祉の分析(例えば、発展途上国における極度の貧困を取り扱う場合)において、比較的少数の中心となる重要な機能(および、それに対応する基本的な潜在能力、例えば、栄養状態が良いこと、風雨をしのげる住居に住んでいること、予防可能な病気にかからないこと、早死にしないこと、など)だけで、かなりのことを主張することができる。経済開発におけるもっと一般的な問題を含めた他の文脈では、対象とすべき機能のリストはずっと長く多様なものになるだろう[11]。
国連開発計画(UNDP)の人間開発指数(HDI)は、生命・教育・所得の指標から合成され、人々のウェルビーイングを国別に比較する人気のあるツールになっている。具体的には乳幼児の死亡率は身体的な、就学率は精神的な、年間所得は物質的な達成度がバランスよく配置されている。実際、HDIはセンのケイパビリティ論を基礎にして構築された。ただし、彼自身は、それがあまりに単純化されていると苦言を呈した。機能のリストは扱う問題によって増減すると書いている。生命・教育・所得だけのHDIは彼の想定よりもいっそう単純化されたものであったため、彼は不満であった。
このように、ケイパビリティ論の焦点は、物欲にまみれた通俗功利主義とは違い、人間の達成度に置かれるものの、幸福への一つのアプローチという点では類似している。そして、ここにも二つの問題点がある。
ケイパビリティ論が含む問題の一つはウェルビーイング、つまり心身の健康、が途上国の開発にテーマを絞るにせよ、ガバナンスの適切な目標か?、ということである。人間開発に寄与する物資を送ったり、施設を建てたりすることは、人道的に正しい行動であると映る。大地震などの災害では日本のような先進国であっても人道援助を受けとる。それにたいし、受けとらない中国のような国は哀れみや慈悲だけでなく、誇りや静穏を求めているであろう。貧困でなく不平等が問題だ、という孔子、マルクス、あるいはロールズといった大哲学者たちの声も無視できない[12]。
二つ目の問題は、援助の計画が現地から遠い国際機構や各国の援助機関で計画されることである。援助対象の普通の人々の生の声はどうなっているのであろうか? 主権国家の代表というエリートたちに独占された外交も、時代遅れではなかろうか?
実はベンサムの功利主義の弱点も同じである。最大の幸福を生み出す最適な財とサービスはこれこれの種類、これこれの数量であるので、資源をこれこれだけ工場に配分し、最終消費者にこれこれのように分配しなければならない。こうした投入と産出の計画を立てることができて、初めて、最大多数の最大幸福という大風呂敷を広げることができるはずである。
これは重要な問題である。政府の「刑罰と報償」によって不幸になる個人がいるからである。そうした不幸は十分に補償や賠償をされるはずである、というのが功利主義の約束である。補償や賠償が行われるには、社会全体の幸福と個々人の幸福が正確に計算されなければならない。しかし、いいかげんな統計を持ち出し、政府は個人の犠牲を当然の義務であると言い張らないであろうか? 功利主義には、国民を奴隷としてこき使う国家の言い訳に利用される危険がある。
ここでオーストリア出身の経済学者、フリードリヒ・A・フォン・ハイエク、に登場してもらう。彼は市場重視の立場から功利主義者の大風呂敷を批判した。
私が常々驚かされてきたのは、真面目で精神のある人びとが、疑いもなく功利主義者はそうであろうが、どうして大部分の特定の事実にかんするわれわれの必然的な無知というこの決定的事実を深刻に受けとめずにすますことができたのかということである。また、かれらが説明しようと企てた現象の全存在、つまり行動ルールのシステムの全存在が実際にそうした知識の不可能性に依拠しているときに、われわれの個人的行為の特定の効果にかんする一つの知識を前提とする理論をどうして提案することができたのかということである[13]。
人類における最大多数の最大幸福を構想することはあまりに壮大なプロジェクトであるがゆえに、人間の手に余ることである、と考えた先達がいたということである。
センのケイパビリティ論は対途上国援助については真価を発揮するかもしれないが、それ以外のテーマではうまくいくであろうか?
例えば、国連の2030年目標である持続可能な開発目標(SDGs)は、この弱点を克服しようとしている。それは先進国にも適用できる。なぜなら、貧困削減はもちろん、環境、ジェンダー、健康など、豊かな社会が取り組む課題が取り入れられているからである。その一方で、環境やジェンダーのようなリベラルな価値観こそ最優先の課題でなければならない、とは、途上国の多くの人々は認めないであろう。
最大多数の最大幸福とSDGsとの間には大きなズレがある。なぜなら、開発途上国と先進国、女性と男性、あるいは若者と中高年齢者といったグループ間のパートナーシップは、多数決原理ではなく衡平によってつながれなければならないからである。衡平というのは金銭のような単一尺度の価値によって一方的に補償されて成立するバランスではなく、あくまで、諸グループ間およびそれら内で納得して得られるコンセンサスである。そのようなコンセンサスをグローバルに達成できるのは、地球上のすべての主権国家を巻き込む集団交渉の場である国連総会しかない。実際、SDGsはA/RES/70/1という国連総会決議である。
ところで、客観的に幸福は測定できる、という前提に功利主義は立つ。その最たるものがあらゆるものを、交換される商品、として理解する経済学である。これにたいし、主観的な幸福感に注目するアプローチがあり、近年、力を増している。それはアンケートによって、自分はどの程度、幸福であるかを答えてもらい、国なり、地域なりでその結果を集計したものである。
所得の高い人が幸福感の強い人とはかぎらないし、所得の低い人が幸福感の弱い人ともいえないことは、生活体験から推測がつく。ある研究者は、所得が低いのに幸福感が強い人と所得が高いのに幸福感が弱い人との組み合わせを、悲惨な農民と不幸な億万長者、と呼ぶ。その原因の一つは「不幸な成長のパラドックス」であると結論づけられた。
このケースでは、自分たちの一人あたりGNPの平均水準について説明を受けた後、高成長率の国の回答者は平均して、低成長の国の回答者よりも幸福ではありませんでした(一人当たりGNPの水準と変化を区別するのは重要です。一人当たり所得が高い国の人々は平均して、より幸福だからです)。こうした結果を説明するものとして、経済成長の高まりに応じて頻繁に現れる不安定性と不公平性が挙げられます。
実際、人々は、不確実な状況よりも、良好な水準とはいえないまでも安定した状況に対して、より適応することができるようです[14]。
生活の安定が幸福感を増すというのは興味深い。東洋の格言を引けば、恒産なくして恒心なし、ということであろう。ほかの研究では、貧しい人には宗教が、豊かな人には健康が幸福感を増す、という結論もあるそうである[15]。主観的幸福論が知的関心を刺激してくれることを否定するつもりはない。 本人が幸せならいいじゃないか、と日常的に言われる。しかし、グローバルガバナンスは幸福感の上昇を主な目的とすべきかといえば、ためらわざるをえない。主観的幸福を目的とするならば、悲惨な農民でなく、不幸な億万長者に手を差し伸べなければならない。この億万長者は自らの財産を費やすことによって、内面に隠れる不幸を追い払えばすむことである。家族や友人との関係という変数が主観的幸福感の要因であれば、公的支援にできることはかぎられる。自助というのもガバナンスの方法である。自助は本人が自由であれば実現する。ならば、自由をグローバルガバナンスの目的にすればよい。
[1] ベンサム、「道徳および立法の諸原理序説」、山下重一訳、関嘉彦編、『ベンサム J.S.ミル』、中央公論新社、1979年、82ページ。
[2] ベンサム、「道徳および立法の諸原理序説」、84ページ。
[3] ベンサム、「道徳および立法の諸原理序説」、82ページ。
[4] ベンサム、「道徳および立法の諸原理序説」、148ページ。
[5] ベンサム、「道徳および立法の諸原理序説」、109ページ。
[6] ミル、「功利主義論」、伊原吉之助訳、関編、『ベンサム J.S.ミル』、468ページ。
[7] ミル、「功利主義論」、470ページ。
[8] A・H・マズロー、『改訂新版 人間性の心理学』、小口忠彦訳、産業能率大学出版部、1987年。
[9] アマルティア・セン、『不平等の再検討』、池本幸生、野上裕生、佐藤仁訳、岩波書店、1999年、60ページ。
[10] セン、『不平等の再検討』、60-61ページ。
[11] セン、『不平等の再検討』、64ページ。
[12] 国際政治学では次のものが知られる。C・ベイツ、『国際秩序と正義』、進藤榮一訳、岩波書店、1989年。
[13] F・A・ハイエク、『法と立法と自由Ⅱ 社会正義の幻想』、新版、篠塚慎吾訳、春秋社、1987年、32ページ。
[14] キャロル・グラハム、『幸福の経済学』、多田洋介訳、日本経済新聞社、2013年、48-49ページ。
[15] グラハム、『幸福の経済学』、73-74ページ。
© 2026 Ikuo Kinoshita