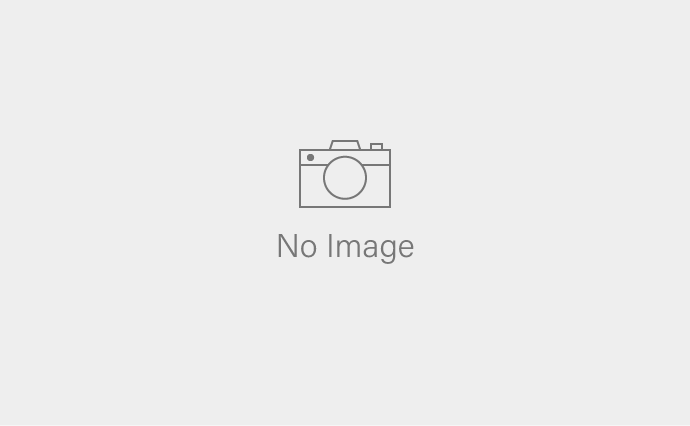『宋名臣言行録』の話題を続けたい。今日は寇準について語ろう。
中華帝国の統治は中原と辺塞との両面がある。後者は外敵を防ぐために不可欠であるのはもちろん、中原の安寧にとっても決定的だ。なぜなら、兵馬を養う、というように、優秀な兵士と馬は辺塞でしか得られないからだ。
その意味で、北宋の統治は変則的だった。モンゴル系の遼が支配する燕雲十六州こそ、良質な兵馬の産地である3つの地域のうち、燕(現河北省)と雲(現山西省)の2つだった。残りの1つは隴(現甘粛省)であったが、チベット系の西夏と宋に分断されていた。
宋は軍事力の弱さを補うため、遼に貢いで平和を購った。その約束が1004年の澶淵の盟であり、立役者が寇準なのだ。
いきさつを朱熹の『宋名臣言行録』はこう描く。
――遼が侵入した、と矢継ぎ早に報せがあった。翌日、宰相の寇準は皇帝の真宗に奏したところ、真宗は早く解決したいと御意を伝えた。
寇準
陛下、了せんと欲せば、五日にすぎざらんのみ。その説は澶淵に幸せんことを請ふ。(朱熹、諸橋轍次、原田種成、『宋名臣言行録』、第3版、明徳出版社、1980年、p.59)
「陛下が解決したいのでしたら5日もかかりません。澶淵に行幸なさいませ。」と彼は真宗を促したものの、真宗は黙ったままだった。
他の高官は恐れて退出しようとした。寇準はそれを遮って言った。「君も帝に随行して北へ行くのだ」
――と、澶淵の盟は彼の気魄のなした偉業だった、と朱熹は言わんばかりだ。しかし、私は性格でなく計算高さがこの物語の真価だと思う。
真宗が行幸して遼軍に対峙したのは虚勢だった。遼が戦争を選んだらどうなったか? これは私もわからない。天子の車は、ほうほうのていで退かなければならなかったかもしれない。
一方、行幸はまちがいなく盟約の交渉を有利にした。ここぞ、というとき、度胸と労苦は惜しんでならない。それらがなければ腰砕けになり、宋は領土まで奪われたのでなかろうか。
日本の政治家に、こうした外交の大一番を張ることはできるか? と反語的に問うて締めとする。