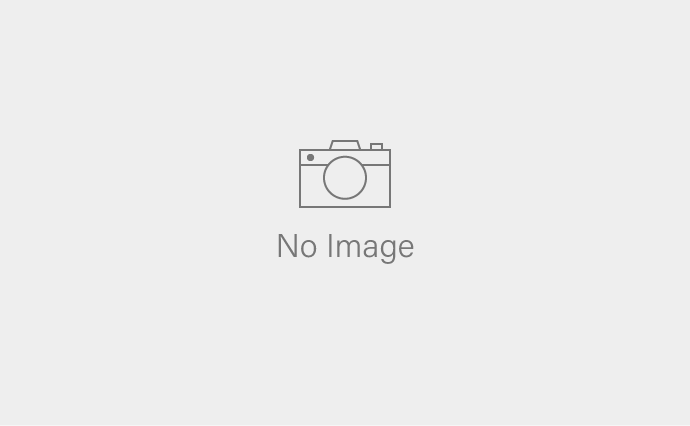関税は商品の代金とは別にかかる費用である。関税を下げれば、国境を越えて商品は移動しやすくなる。これが自由貿易の考え方である。自由貿易が行われる国々の住民は、余計な費用をかけずに商品を売ったり、買ったりでき、選択の自由は飛躍的に増す。
しかし、同じ商品を国内で作っていた業者にとっては、外国からより低い価格で商品が買えるとなると、自分が作ったものが売れなくなってしまう。輸入を減らして国民の仕事を守れ、という保護主義の要求は、選挙をつうじて意思決定者に直接、伝えられる。市場メカニズムのメリットが保護主義のそれに勝ることを国民に説得するのも政治家の責任であるが、これがなかなか行われない。
今回のテーマは、19世紀中葉、自由貿易がいかなる歴史的過程を経て実現し、またそれが契機となって生まれた相互依存をめぐる言説がいかなる展開をたどったか、である。
保護主義の例としては穀物法が引き合いに出される。ナポレオン没落後、大陸封鎖が崩壊したことにより、イギリスへのヨーロッパ大陸からの穀物輸入が再開され、地代に依存する地主には生産物の値崩れが懸念された。そこで1815年に穀物法が定められ、外国産穀物に輸入制限を課した。穀物価格の高値安定は、中産階級と労働者階級には不評であった。家計の消費支出に占める飲食費の割合をエンゲル係数といい、家計の貧困度合いを示す指標として使われる。食費が上がるとエンゲル係数は上がる。
ちょうどそのころ世に出たのが、デイビッド・リカードの比較優位説または比較生産費説であった。『経済学および課税の原理』から、ポルトガルとイギリスの分業が有利であると論じる該当の部分を引用する。
イギリスは、毛織物を生産するのに一年間に100人の労働を要し、またぶどう酒を醸造しようとすれば、同一期間に120人の労働を要するような事情のもとにあるとしよう。したがって、イギリスは毛織物の輸出によってぶどう酒を輸入し、購入することが、自国の利益であるとみなすであろう。
ポルトガルは毛織物を90人の労働で製造しうるにもかかわらず、その生産に100人の労働を要する国からそれを輸入するであろう。なぜなら、ポルトガルにとっては、その資本の一部分をぶどう栽培から毛織物製造へと転換することによって生産しうるよりも、一層多くの毛織物をイギリスから交換入手するぶどう酒の生産にその資本を投下する方が、むしろ有利だからである[1]。
リカードが言う通りかどうか、厳密には、通貨の交換レートや人口比の情報を教えてもらうまで結論を持ち越すべきである。しかし、ここでは彼に敬意を払い、ポルトガルはぶどう酒に特化し、イギリスは毛織物に特化すると双方に便益がある、と信じよう。関税を下げて貿易を活発にすれば、国際的に、最適化、すなわち最善な選択肢の探索、が進む。国民単位で物事を見れば、消費を最大にするのはいずれの国民にとっても自由貿易である。
その一方で、イギリスの土地貴族たちは地代が下がれば、少ない所得しか手にすることができなくなる。現実には、その心配はなかった。なぜなら、議会には多くの土地貴族が選ばれており、穀物法を守ることができたからである。カール・マンハイムは、イデオロギーを観念の存在拘束性の一例とした[2]。地主としての存在に拘束された土地貴族たちは、都合のよいイデオロギーを世間に広め、穀物法を続けさせた。
イデオロギーであるという点では、マンチェスター学派の経済学も異なるところはない。穀物すなわち飲食費が安くなれば、労働者の賃金も安くなる、と彼らは主張した。当然、賃金が安くなれば企業の利潤は大きくなる。現代における最低賃金の制度を知る者には理解しがたい考え方ではあるが……
マンチェスター学派の代表は、キャラコ捺染業を営み、庶民院に選出されていたリチャード・コブデンである。彼の拠点がマンチェスターであった。同じくこの工業都市に拠点を置いたジョン・ブライトとともに、反穀物法同盟の中心人物となった。コブデンとブライトはブルジョワジーを代表するといえる。中産階級、とも呼ばれるが、それは王侯貴族から見ればそうなるというだけで、実際には富裕層である。
最後に、労働者階級のイデオロギーはどうであったろうか? 貴族という共通の敵がいたために、19世紀前半にはブルジョワジーとプロレタリアートは共闘の関係にあった。カール・マルクスは当時を振り返って、次のように書く。
―前略―工場主であるコブデンやブライトを先頭に立てた穀物法反対同盟が世間にまき散らしたあつかましいパンフレット類でさえ、土地所有貴族にたいするその攻撃によって、けっして科学的ではないにしても歴史的ではある関心を示した[3]。
ブルジョワジーと労働者の共闘といえば、選挙法改革の争点もそうである。国民の多数派が支持する候補者が議員に当選し、議会の多数派が法律を改廃するようになれば、穀物法もなくなるであろう。それは最大多数の最大幸福にはちがいないが、土地貴族という敗者が明らかにいた。
自由貿易への最後のひと押しとなったのは、じゃがいも飢饉、つまり1845年から1846年にかけてのアイルランド大飢饉であった。国内で飢えている人がいるのに、穀物輸入に制限を課し続けることはできなかった。風刺漫画の雑誌には、長身のコブデンが子供姿のロバート・ピール首相を自由貿易に連れていく姿が載った。ついに、穀物法は廃止された。今度は、自由貿易によって肥え太ったライオンの姿、つまり王者イギリスの数年後を描いた漫画がそこに載った[4]。
ここまでは、国内政治の話である。つまり、イギリスが一方的に外国からの穀物輸入を増やした。次は、二国間条約が自由貿易を推し進めた話である。
フランスのナポレオン三世は戦争によって多くの敵を作り、イギリスとの友好を必要としていた。そこで、イギリスとの関税引き下げ協議に着手し、フランスはミシェル・シュバリエを、イギリスはコブデンを代表に選んだ。1860年に結ばれたのが英仏通商条約の特恵貿易協定である。これはコブデン条約とも呼ばれ、自由貿易のシンボルとして人々の心に刻まれた。新たな関税率は両国の産業構造に変化をもたらし、イギリスは工業に、フランスは農業に特化した。
自由貿易は最盛期を迎えた。通商条約は全ヨーロッパ大陸とアメリカ合衆国に伝播し、1870年代には40本を数えた[5]。1875年には工業製品に対するイギリスの関税は0パーセントに低下した[6]。これこそ19世紀のグローバリゼーションであった。
ただし、通商のグローバリゼーションは、主権国家の自由意思だけに基づき、広がったわけでない。半文明国、例えば当時の中国や日本、にとって、自由貿易は押し付けられたものであった。自由貿易帝国主義という用語でそれが解説されることがある。なぜなら、砲艦外交という軍事的な脅迫によって、国家主権を奪ったからである。
中国の場合、アロー戦争が行われ、その講和のために、1858年の天津条約が結ばれた。日本においてこれに対応する内容を持つのは、黒船来航の翌年に結ばれた日米和親条約とアロー戦争を見ながら交渉された日米修好通商条約である。後者は天津条約同様、片務的最恵国待遇、領事裁判権、そして協定関税を伴う不平等条約であった。半文明国と文明国との関係は、文明国どうしのものとは異質であった。
自由貿易は有無を言わせぬ勢いで広がったが、自国産業を守る動きも広がった。経済学における国民学派、すなわちナショナリスト、の興隆である。ドイツでは、ゲオルク・フリードリヒ・リストが1841年に『政治経済学の国民的システム』を書いた。そこで説かれた幼稚産業の保護を目的とする輸入代替工業化は、工業を農業より優先し、完全な農業国が、いかに外国工業品を締めだし、国内工業品を輸出するまでになるか、を段階を追い描く[7]。
リスト自身、ドイツ関税同盟を設立するために奔走した経験があり、輸出大国のイギリスから国内市場を守るため、関税同盟が大きな役割を果たすことを知っていた。ドイツの諸国は関税同盟を結ぶだけでなく、1871年にはプロイセン王国を中心とする統一国家に合体した。ドイツ帝国は1879年に新関税政策を採用し、保護主義を強化した。これに追随して、他の国々も工業製品の関税率を上げ、自由貿易の時代は終わりを告げた[8]。
話題を相互依存、英語でインターデペンデンス、に転じよう。それは自由貿易の状況を国際関係に応用した理論である。次のコブデンの手紙において、理論としてすでに完成している。
―前略―ヨーロッパの植民地政策は過去150年の間、戦争の主要な源泉であったのです。他方、自由貿易は交流を促進し、国々が互いに依存する(mutually dependent)ことを確かにすることによって、必然的に、政府から人民を戦争に駆りたてる力を奪います[9]。
相互依存論は、貴族主義に対抗してブルジョワジーが作ったイデオロギーであった。貴族主義は保護関税によって国富を減少させる。貴族の子弟である軍人は戦争を起こす。植民地は増え、防衛費がかかり、関税を上げねばならない。国富はさらに減少する。
それにたいし、民主主義は自由貿易をもたらして、国富を増大させる。国際紛争を仲裁によって平和的に解決する不干渉政策を貫けば、自由貿易は維持できる。平和は軍縮による減税を可能とし、国富は増大する。
第一次世界大戦のころ、相互依存を宣伝したのがジャーナリストのラルフ・ノーマン・エンジェルであった。彼は「大いなる幻想」(1910年)において、領土を増やせば富も増える、と見るのは楽観的な幻想である、と唱えた。ところが、時を置かずに世界大戦が起きたことで、現実主義者の引き立て役として教科書に登場させられることになった。
しかし、エンジェルはまちがえていたわけでなかった。例えば、ドイツは征服しても損をする、と書いているが、理由はもっともなことばかりである。敵の人命を奪うことは、自らの市場を破壊することである。敵の財産を差し押さえても、こちらの被害を償えるわけでない。敵の領土を併合しても、その土地の富の所有者はその土地の住民のままである。敵の領土を植民地にしても、それを防衛するのに費用がかかり、経済的には損である。エンジェルは、戦争は起きない、と言ったわけではない。戦争は損である、と言ったにすぎない。
エンジェルは1933年にノーベル平和賞を贈られた。次の文章は複合的相互依存という概念を説明したものであるが、現在でも色あせない。
―前略―近代金融の複合性はニューヨークをロンドンに依存させ、ロンドンをパリに依存させ、パリをベルリンに依存させたが、それは史上かつてない程度である。この相互依存は以下のような昨日できたばかりの文明の利器を日常で使用した結果である。それらは、速達、電信による金融・商業情報の即時伝達、そして一般的に通信速度の信じられない進歩であり、百年も経っていない前のイギリスの主要都市間よりも半ダースのキリスト教国の首都を金融的により密接に連絡できるようにし、相互に依存させている[10]。
日本の自由貿易論者といえば、東洋経済新報社主幹で、戦後、内閣総理大臣になった石橋湛山が挙げられる。満州事変に際して彼が書いた記事は、資源確保が軍事活動の目的である、という論拠の弱点を見抜いていた。
そしてわが国には鉄、石炭等々の原料が乏しいから、満蒙の地を、その供給地としてわが国に確保することが、国民経済上必要欠くべからざる用意だと称うる。これも現在までの事実においては全く違う。満蒙は何等わが国に対して原料供給の特殊の便宜を与えていない。が仮に右の説が正しとするも、もしただそれだけの事ならば、敢て満蒙にわが政治的権力を加うるに及ばず、平和の経済関係、商売関係で、優々目的を達しえる事である[11]。
コブデンから石橋湛山に至る考え方は、古典的自由主義と称される。その特徴は、国家は国内の支配的集団に代表され、その利益が満たされれば国際関係は調和する、と見ることである。支配的集団とはベンサムのいう「最大多数」であり、具体的には中産階級である。国家は力関係で競うことはない。戦争は一部の特殊利益が自分たちの利益だけを図った結果である。
それにたいし、20世紀末にアメリカ合衆国で広まったのが新自由主義である。利己的な国家どうしも自己利益のためには協力する、というのがその中心的な主張である。古典的自由主義が前提とした個人や集団、あるいはマルクス主義が依って立つ階級ではなく、新自由主義は国家そのものを単位とみなす。また、国家間に対立が存在する場合でも、国際法や国際機構といった制度によって協力するよう仕向けることができる、と考える。後者の立場は新制度主義と呼ばれる。
新自由主義と学界の支持を競ったライバルの新現実主義も、国家中心の見方をする。違いは、国際制度を重視するか、軍事力を重視するか、といった程度しかないという議論さえ出た[12]。相互依存に対する見解をめぐっては、古典的自由主義と新現実主義とが対極にあり、新自由主義は折衷的な位置にある。
新現実主義の代表はケネス・N・ウォルツである。彼は相互依存を「神話」と呼んで批判する。それは平和につながるのでなく、国どうしの接触や交流が増えることで、偶発的な紛争を起きやすくする。相互依存という言葉そのものにも欠陥がある。それは国力が不均衡であるのを曖昧にし、互恵的な相互依存関係が存在するかのような幻覚を与えてしまうからである[13]。
要するに、強者は依存せず、依存は弱者だけがするものである、とウォルツは言いたい。大国は外国に対して統制力を行使しうると同時に、自国を隔離することもでき、それが国際関係の安定を実現する。地理的に広大で経済的にも先進国である国は資源が一時的に不足しても、速やかに自足体勢を整えることができる。供給元の多様さ、備蓄、そして技術進歩といったものは大国のほうが勝っている。例えば、アメリカ合衆国は天然ゴムの供給が滞った時に、技術力によって、合成ゴム産業を育成できた[14]。
新自由主義は、新現実主義の主張を一部認めつつ、強者はつねに有利、というような結論は巧みに避ける。ロバート・O・コヘインとジョセフ・S・ナイに、『力と相互依存』という共著がある。わざわざ、力、という言葉を題に入れ込んで、新現実主義と折り合いをつけるかのようである。
コヘインとナイが考案した概念が「脆弱性(バルネラビリティ)」である。それは、政策変更が可能という条件下で、国外に起因する費用の影響、と定義される。政策次第で外国の影響を緩和できる国、例えば大国、は脆弱でない、つまり、依存はしていないことになる。ただし、「敏感性(センシティビティ)」、つまり、政策変更が不能という条件下で、国外に起因する費用の影響、は、大国であっても小さくないかもしれない[15]。その場合、短期的に敏感性が大きくても、長期的には非脆弱であり、依存とはいえない。
天然ゴムの供給が止まった時、合成ゴム産業を育成する政策で切り抜けた、というウォルツの挙げる例は、アメリカ合衆国が脆弱でなかったことを示す。また、ウォルツの挙げる例ではないが、原油価格が上昇した場合、産油国の王様に、増産をよろしく、と電話をかけたり、中東に空母を派遣して力を誇示したりして価格高騰を抑えることは、同国の大統領がよく使う手である。こうした対策をとる時間がなく、ショックで一時的に価格が高騰している状態が敏感性である。脆弱性と敏感性という概念は巧妙に練られている。
つまり、新自由主義は非脆弱性という意味での大国の力については新現実主義にたいして異論はない。脆弱性や敏感性は国際協力でカバーできると主張する点が違うだけである。そうした共通性から、両者を「総合」して一本化する可能性がしばしば唱えられてきた。しかし、それで統一理論ができあがると考えるのは早計である。それぞれが関心を寄せる軍事力の世界と国際制度の世界がそもそも違う。研究関心が異なれば、理論も異なってしかるべきである。
最後に相互依存論の二つの亜種を紹介する。一つは天谷直弘の「町人国家」であり、1980年に発表された。彼は通商産業審議官であり、エネルギー問題に造詣が深かった。当時は高度成長を遂げた日本を経済大国ともてはやす風潮もあったが、日本の限界をわきまえた謙虚な所説を述べた。
今日の国際社会を見ると、そこには徳川社会の構造と一脈相通じるものがあるように思われる。たとえば、日本は商工をもって立ち、米国やソ連は士農工商を兼備し、多くの発展途上国は農をもって立っている[16]。
必要あれば、産油国に対して「油乞い」もしなければならず、時には七重の膝を八重に折っても「武士」に許しを乞わねばならぬこともあるであろう[17]。
もう一つは、リチャード・ローゼクランスの「貿易国家」(1986年)である。
一方には、ソ連と(ある程度)までアメリカを主役とする、ルイ十四世の時代にまでさかのぼる領土主義の世界があり、他方には、大西洋と太平洋の周辺に形成された、一八五〇年代のイギリスの政策に由来する海洋主義と貿易の世界がある。―中略―海洋主義と貿易の世界に属する国々は、自給自足が幻想であることを認識している。貿易が比較的自由で開放的でありさえすれば、経済を発展させ生活の必需物資を手に入れるのに新しく領土を獲得する必要はない、と考えている。今日の西ドイツと日本は、一九三〇年代に武力で獲得しようとした原材料と石油を、国際貿易で手に入れ、平和のうちに繁栄している[18]。
いずれの考察も米ソの衰退が喧伝されていた1980年代に発表された。当時は、軽武装で経済を優先するいわゆる吉田ドクトリンの立場から、軍事偏重の米ソを冷ややかに見る風潮が特に日本で強かった。その一方で、非大国が協力して、良いグローバルガバナンスが維持できるかには戒める意見があった。「フリーライダー(ただ乗り)」と日本は批判され、ウォルツが説くような大国の統制力への畏敬が残っていた。21世紀の今日においても、大国によるガバナンスか?、小国によるガバナンスか?、という問いは未解決である。
[1] リカードウ、『経済学および課税の原理』、上巻、羽鳥卓也、吉澤芳樹訳、岩波書店、1987年、191-192ページ。
[2] カール・マンハイム、「イデオロギーとユートピア」、『マンハイム オルテガ』、高橋徹訳、第4版、中央公論社、1988年。
[3] カール・マルクス、『資本論』、1、岡崎次郎訳、大月書店、1972年、33ページ。
[4] ジャグディシュ・バグワティ、『保護主義』、渡辺敏訳、サイマル出版会、1988年、23、35ページ。
[5] David Lazer, “The Free Trade Epidemic of the 1860s and Other Outbreaks of Economic Discrimination,” World Politics, 51 (4) (1999), p. 473.
[6] Paul Bairoch, Economics and World History: Myths and Paradoxes (Chicago: The University of Chicago Press, 1993), p. 40.
[7] フリードリッヒ・リスト、『経済学の国民的体系』、小林昇訳、岩波書店、1970年、60ページ。
[8] Bairoch, Economics and World History: Myths and Paradoxes, p. 40.
[9] Cobden to Henry Ashworth, April 12, 1842, quoted in John Morley, The Life of Richard Cobden, 13th ed. (London: T. Fisher Unwin, 1906), pp. 230-231.
[10] Norman Angell, The Great Illusion: A Study of the Relation of Military Power in Nations to Their Economic and Social Advantage, 1911 (New York: Garland Publishing, 1972), pp. 46-47.
[11] 石橋湛山、『小日本主義 石橋湛山外交論集』、増田弘編、草思社、1984年、108-109ページ。
[12] Robert O. Keohane, “Institutional Theory and the Realist Challenge After the Cold War,” in David A. Baldwin, ed., Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate (New York: Columbia University Press, 1993). Joseph M. Grieco, “Anarchy and the Limits of Cooperation: A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism,” in Baldwin, ed., Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate.
[13] ケネス・N・ワルツ、「国家間の相互依存という神話」、C・P・キンドルバーガー編、『多国籍企業―その理論と行動』、藤原武平太、和田和訳、日本生産性本部、1971年。Kenneth N. Waltz, “The Myth of National Interdependence,” in Charles P. Kindleberger, ed., The International Corporation (Cambridge: M.I.T Press, 1970), pp. 205-223.
[14] ワルツ、「国家間の相互依存という神話」。Waltz, “The Myth of National Interdependence,” pp. 205-223.
[15] Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, Power and Interdependence, 2nd ed. (New York: HarperCollins, 1989), p. 14.
[16] 天谷直弘、『日本町人国家論』、PHP研究所、1989年、45ページ。
[17] 天谷、『日本町人国家論』、48ページ。
[18] リチャード・ローズクランス、『新貿易国家論』、土屋政雄訳、中央公論社、1987年、25-26ページ。
© 2026 Ikuo Kinoshita