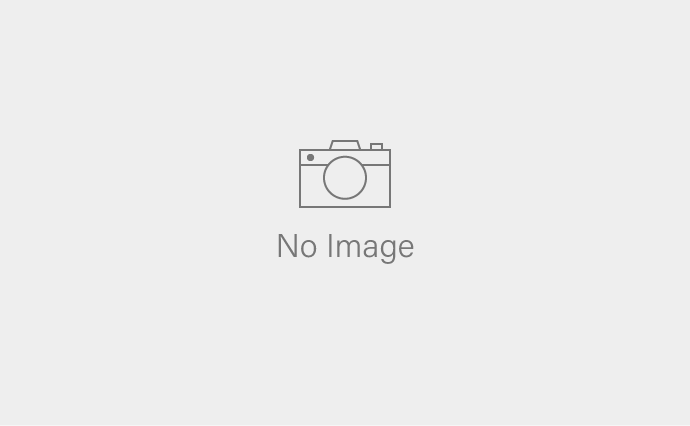集団安全保障がない国際平和は、警察がない治安と同じである。その心は、非常に危うい、ということである。集団安全保障の本質は、武力行使の違法化とその違反に対する社会からの制裁にある。
集団安全保障の発案者は、18世紀初めのフランスの学者サンピエール神父である。彼が構想したことはこうであった。ある国が違法に武力を行使したとする。その国はヨーロッパ社会全体の敵とみなされる。交戦状態はこの敵が武装解除されるまで続けられる。
国際連盟ができるまでの二百年間、そのような国家間の連合が本当にできるのか?、は人類最大の難問であった。これに、可能である、と納得できる説明を与えたのがカントである。
1795年に公刊されたカントの『永遠平和のために』は社会契約論における「自然状態」の論法を利用する。自然状態というのは架空の世界であり、この場合、諸国家はいまだに社会を成さず、ゆえに法も秩序もなく、ただ、にらみ合っている。自然状態では、国家はいつも戦争の口実を探している。理性が命じるのは、戦争を断固として処罰することを諸国家の義務とすることである。よって、すべての戦争を永遠に終結させる平和連合が存在しなければならない[1]。
ここで注目すべきであるのは「理性が命じるのは」というくだりである。カントは以上の論理が理想にすぎないことを自覚している。しかし、彼は太陽系の起源について星雲説を唱えた科学者であったように、単なる理想主義者でない。
国家を強制して平和連合に加盟させることはできない、とカントは認めて、それが形成される別の過程を考える。平和連合に喜んで入る国は本性上、平和を愛する国である。そのような国は共和国である。こうした共和国が中心となって、諸国家が数珠つなぎになって平和連合を形成していく。共和国だけでなく、君主国も加わっていくであろう。こうして、平和連合は遠くにまで広がっていく[2]。これは現実に平和連合が形成されるであろうシミュレーションにほかならない。
1冊の『永遠平和のために』が二つの意味を持つことが分かったろう。一つは集団安全保障の理想であり、多国間の国際機構を作って、違反国を制裁する構想である。これは国際連盟や国際連合の設計図となった。もう一つは「民主主義の平和」であり、民主国間の同盟により侵略を抑止する構想である。こちらはNATOや日米安全保障条約の理念である。
今回のテーマは、同盟の問題点と集団安全保障の理想との関係について第一次世界大戦前後の例を引きながら論じなさい、である。国際連合の時代については「集団安全保障と自衛権」の回で扱われる。
国際連盟の設立に至るまでには、第一次世界大戦とそれに先立つ外交があった。19世紀後半、ドイツ宰相オットー・フォン・ビスマルクは巧みな外交手腕を発揮し、フランスを孤立させることに成功した。彼は1872年の三帝同盟によりロシアとオーストリアハンガリーを味方とし、1879年の独墺二国同盟でオーストリアハンガリーとのきずなを深め、1882年の独墺伊三国同盟をつうじイタリアをフランスに対抗させた。オーストリアハンガリーの同盟国であるドイツは、この同盟国がロシアと仲違いすると、巻きこまれないよう、1887年にロシアと再保障条約を結んだ。
ところが、辞任したビスマルクに替わって外交の指揮を執った皇帝ビルヘルム二世は成果を台無しにした。露仏同盟が1894年に結ばれ、逆にドイツは包囲される側になった。19世紀末に日本公使としてロシアに駐在した林董は次のように振り返る。
仏露同盟は、久しき前より世に聞こえたる所なるが、仏大統領訪問の時露帝が仏艦にて午餐の饗応を受けられし際の演説に於て、初めて我同盟国の語を公に用いられたりと云う[3]。
つまり、露仏同盟は秘密条約であった。秘密といってもバレバレなのではあるが、秘め事を作る行為によって、国家間の疑心暗鬼を深めた。その後、林董は駐英公使になり、日英同盟を1902 年に締結することになる。なぜ、イギリスとの同盟が必要であったのか? 林は自らが清に赴任した際に起きた三国干渉に、その理由があるとした。彼の解説を引用する。
我輩は、日清戦争後、欧羅巴の列強合縦の結果が、極東に影響を及ぼし、三国干渉となって我に圧迫を加えたことを、直接に経験したのであるから、日本の孤立が到底不可能であるを感ずるの念も、特に痛切であったから、是非とも合縦の策を講ずるの必要を認め、―中略 ―「外交の大方針を定む可し」と題する一篇の論説を起草し、―中略―『時事新報』の社説に載せられたのである[4]。
20世紀に入ると、同盟をめぐる世界の動きは激しくなった。1904年に英仏協商が結ばれた。日露戦争後に日本とロシアは接近し、1907年の日仏協商・日露協商・英露協商によって、露仏同盟と日英同盟が合流する形になった。これで第一次世界大戦の協商国対同盟国の対立構図ができあがった。
サラエボ事件と七月危機は外交史で最もよく取り上げられるテーマの一つである。オーストリアハンガリーの帝位継承者フランツフェルディナント大公がサラエボの町で、セルビア人青年により射殺された。オーストリアハンガリーにとっては、帝位継承者が暗殺されただけで屈辱である。オーストリアハンガリーは、犯行に使われた銃はセルビア軍将校から供与されたものと主張し、陰謀加担者を裁判し、それに自国の代表も参加させることなど要求した。セルビア側がこの要求を拒否したために、戦争の危機におちいった。
7月28日、オーストリアハンガリーはセルビアに宣戦布告をした。セルビアはヨーロッパの片隅である。なぜ、ここから世界大戦に発展したのか?
セルビアはロシアと同じスラブ民族であり、ロシアとしては見捨てるわけにいかなかった。ロシアとオーストリアハンガリーが戦争になれば、後者はドイツの同盟国であるので、今度はロシアとドイツが戦争になるであろう。実際、ドイツが、同盟責務を果たすつもりだ、とオーストリアハンガリーに伝えたのは、早くも7月5日であった。オーストリアハンガリーに和戦の選択を委ねたので、歴史家はこれを「白紙委任状」と呼ぶ。
ドイツとロシアが戦争になれば、後者との同盟義務にしたがい、フランスがドイツと戦争になる。全ヨーロッパを爆発させた火薬庫の導火線がサラエボ事件であったのはこうした理由による。
とはいえ、セルビアが攻撃されて、すぐにロシアは戦争にとりかかったわけでなかった。局地戦争で止めようと思えば、どこかで止められたかもしれない。それを妨げたのは、同盟の義務と軍事計画であったとされる。同盟の義務とは上で述べた「白紙委任状」のことである。軍事計画の弊害については、ドイツのシュリーフェン・プランの問題が知られている。
ドイツ陸軍の参謀総長アルフレート・フォン・シュリーフェンは露仏同盟に対応した作戦を立案した。ロシアも、フランスも、世界屈指の軍事大国であった。いくらドイツといえども、それらを一手に引き受けるのは容易でなかった。歴史家バーバラ・W・タックマンの文章を引用する。
彼が引退した一九〇六年に立案を完了したシュリーフェンの計画によると、戦争の期間は六週間とし、ドイツ軍の八分の七をフランス粉砕につかい、仕事がすんでこのドイツの大軍が引き返して来るまで、ロシアという第二の敵を東部戦線にくいとめておくために、残り八分の一を割り当てようというものだった。―中略―ドイツもフランスも動員完了には二週間あれば足りる。動員第五日目には大攻撃戦を開始できる態勢にある。―中略―ロシアは面積が広く、人口が多いうえに鉄道が少なく、大攻撃を開始するまでに六週間はかかる。それまでにはフランスを負かすことができるというのである[5]。
実際には彼の引退後、シュリーフェン・プランは本来のものから手直しされた。とはいえ、ドイツが、難事業を遂げるためには先手を打たなければならない、と思いつめていたことは変わらない。
ロシアの立場になってみれば、国土が広大であるがゆえに、兵隊を動員して前線に連れてくるまでに長い時間が必要である。それゆえ、やはり先手先手で動かざるをえなかった。
7月31日にロシアが総動員令を発したことは、ドイツにとってはロシアを急いで片づけなければならないことはもちろん、その同盟国であるフランスとの戦争が不可避になることをも意味した。それゆえ、ドイツは8月1日にロシアに、同3日にフランスに対して宣戦布告した。「動員は戦争を意味する」、すなわち、ロシアの総動員がヨーロッパ大戦を決定づけた、と言われるのはこのためである。
イギリスは日英同盟以外では、戦争に参加する義務を負わなかった。それにもかかわらず、イギリスは第一次世界大戦に引きずり込まれることになった。理由は意外なところにあった。ドイツがベルギーの中立を侵した、というのである。フランスとドイツが直接、国境を共有しているところでは、ドイツの侵攻に対してフランス軍が迎え撃とうと身構えていた。そこで、ドイツ軍は守りが手薄なベルギーを横断して、フランス領に侵入した。
確かに、ベルギーを永世中立国としたのは、1839年に結ばれたロンドン条約であった。その名称からも分かるように、オランダから独立したばかりのベルギーに、イギリスが肩入れして結ばれたものであった。名誉を傷つけられたというのは、当時の感覚では戦争事由になりえた。ただし、数百年前からこのかた、大陸ヨーロッパの統一を防ぐのがイギリスの勢力均衡政策であったから、中立侵犯は後付けの理由であった。
8月7日にイギリスと同盟を結ぶ日本が参戦した。真意は疑いなく、ドイツがアジアと太平洋に持っていた領土と利権を奪うためであった。ヨーロッパへの派兵は申し訳程度に行われた。
ドイツのシュリーフェン・プランは、パリを目の前にしたマルヌでの戦闘でドイツが敗れたことで挫折した。ロシアには、タンネンベルクの戦いにおいてドイツ軍が勝利を収めたものの、全体の戦況は膠着した。1916年におけるソンムの戦いは決戦というにふさわしい大会戦であったものの、イギリスの攻勢は死体の山を築いただけで、勝敗を決するには至らなかった。
こうして、セルビアに対する局地戦争は全ヨーロッパを巻き込む大戦争へと拡大した。
アメリカ合衆国が1917年、参戦して、ヨーロッパ大戦は名実ともに世界大戦になった。合衆国の戦争事由は、貨物船ばかりか旅客船をも含むUボート、すなわちドイツの潜水艦、による無差別攻撃であった。戦況は協商国側に有利に傾き、話題は戦後構想に移った。
T・ウッドロウ・ウィルソンは、再選を賭けた1916年の大統領選挙で、ヨーロッパの戦争に自国を加わらせないために市民が選んだ候補者であった。翌年、ウィルソンが探し出した戦争に介入する口実が「勝利なき平和」であった。彼は、勝者と敗者の不平等な講和でなく、軍縮のような永遠の平和をもたらす講和を提案した。自陣営の英仏はすでに多くの兵士が命を失っていたのに、「勝利なき平和」で両国民は納得できたであろうか?
ウィルソンの提案は1918年、14か条にまとめられた。その1は公開外交であり、「公開の平和の規約」を求めた。その4は「各国の軍備が国内の安全を満たすだけの最低限度に削減される十分な保障の取り決め」である。最後の14番目は「大国か小国かを問わず、政治的・経済的独立と領土保全の相互保障を与える目的で具体的な規約のもと作られる諸国民の一般的結びつき」である。これらが国際連盟規約と軍縮条約をもたらすことになる。
ウィルソン的な理想主義はアメリカ外交全般の傾向であるとも言われる。有名なのはジョージ・F・ケナンの『アメリカ外交50年』における解説である。
外国政府に勧めて、崇高な道徳的・法律的原則の宣言に署名させることによって、われわれの外交政策上の目的を達成しようとする傾向は、アメリカの外交のやり方に強力かつ永続的な力を及ぼしているように思われる[6]。
実際には、ウィルソンの理想主義は他の交戦国との交渉が始まる前から後退していた。彼はハウス大佐という個人的な友人を対外的な交渉者に任じた。停戦の直前、ハウスは14か条の後退を許してもらおうとウィルソンに問い合わせた。公開の規約は秘密交渉を排除しない、とか、公海の自由といっても封鎖はよい、とかは残念ではあるが後退が必然的な事項であった。しかし、イタリアに南ティロルを、イギリスにパレスチナ・アラビア・イラクを、ギリシャにイズミルを、といった他国の領土要求の容認は「勝利なき平和」の大義名分を台無しにした[7]。
パリ講和会議は1919年の1月から6月まで開かれた。議事を牛耳ったのは戦勝国の諸大国、すなわちアメリカ合衆国、イギリス、フランス、イタリア、そして日本であり、最高理事会と称された。その他22の主権国家も会議に参加した。交渉はケドルセー、すなわちパリのフランス外務省、で進められたものの、合意の署名式は郊外のベルサイユ宮殿「鏡の回廊」で行われた。
平和の基盤となるべきベルサイユ条約は15編から成る。第1編は国際連盟規約であり、以下、ドイツとヨーロッパに関する規定が続き、第13編にILO(国際労働機関)の憲章が組み込まれた。
集団安全保障という観点では、ベルサイユ条約のなかでも国際連盟規約、特に戦争の違法化と制裁に関わる部分が問題となる。「締約国は 戦争に訴へさるの義務を受諾し」という一節があるのであるが、それは前文、つまり法的拘束力がないところ、に書かれている。これが当てにならないということが、後に不戦条約が作られる原因となった。
他方、侵略を許さない、ということであれば第10条が国際連盟のバックボーンである。条文を示すと、「聯盟国は、聯盟各国の領土保全及現在の政治的独立を尊重し、且外部の侵略に対し之を擁護することを約す」とある。確かに、後段は違反国への制裁を約束している。
この規約第10条が積極的に適用されれば、満州事変も、エチオピア侵攻も、チェコスロバキア解体も、連盟は対応できたはずである。それができなかったのは、軍事力が心もとなかったからで、連盟規約そのものの問題ではなかった。軍事力が足りなかったのは後で見るようにアメリカ合衆国が加盟しなかったからである。
連盟規約の特徴の一つは、平和的紛争解決のために第12条から第15条までの条項を充実させたことである。ただし、それらは加盟国間の紛争にかぎられた手続きである。
国際連盟による紛争の平和的解決は、外交交渉がうまくいかなければ仲裁または司法的解決に、それらもうまくいかなければ理事会による審査で解決する、というものである。理事会の審査においては、その場で解決できなければ、報告書に勧告を記す。勧告は紛争当事国以外の全会一致によって合意あるものとなり、それを遵守する国と戦争することは禁じられる。紛争当事国のいずれかが要求すれば、紛争の審査は総会に回される。当事国は仲裁判断・常設国際司法裁判所判決・理事会報告書が出てから3か月間は戦争に訴えてはならない。
以上のとおり、連盟による平和的紛争解決の手続きは窮屈なくらい緻密に作られていた。理想主義が法律主義的と評されるのはこのためである。
リットン審査委員会、またはリットン調査団、は満州事変に関しての理事会審査の過程で設けられた。1931年9月18日に柳条湖事件が起きた。南満州鉄道の線路が何者かにより爆破されたと伝えられたが、実は日本の関東軍による自作自演であった。これに乗じて、関東軍は翌日、大都市の奉天を占領した。日本は当初、こうした軍事行動は領土獲得を目的としたものではないとし、撤退の方針を明らかにしていたため、連盟の理事会はその主張を承認した。
ところが翌年、満州国が樹立され、紛争は長引いた。リットン審査委員会の報告書は1932年9月に署名された。内容は、第1に線路の爆破は軍事行動を正当化しない、第2に連盟の指導のもと満州の自治と中立を実施する、というものであった[8]。その趣旨は満州を国際管理下に置くことにあり、中国側による主権の主張とも完全には一致しなかった。
満州事変の審査は理事会から総会へと移されていたが、リットン報告書よりも厳しい決議が1933年2月に採択された。それが不満で、日本代表の松岡洋右は退場した。数日後に、日本は連盟からの脱退を通告した。
当時の日本は大国とみなされていたが、大国を一方の当事者とする紛争解決は連盟でなくても簡単でない。連盟の対応で問題であったのは、極東情勢への介入をその後やめてしまったことである。連盟から脱退した国との紛争解決やそうした国への制裁がやりにくい、という規約の欠陥を、悪しき形式主義が助長してしまった。
平和的紛争解決が失敗すれば、制裁を国際連盟はすることになっていた。それが定められた連盟規約第16条は問題が山積であった。まず、制裁の対象は紛争解決の手続きを守らずに戦争した国だけであった。紛争解決の義務があるのは加盟国だけであるから、非加盟国は制裁の対象にならない、とも主張できてしまう。つぎに、制裁の内容である。きちんと書かれているのは通商・金融関係の断絶と交通の防止だけであり、腰が引けた印象を与える。そうした関係断絶や交通防止に使う兵力の分担は理事会が勧告することになっていたが、海軍と空軍で往来を遮断する程度の、とても全面戦争とは呼べない制裁が想定されていた。
これらの懸念が現実になったのがイタリアへの制裁であった。イタリアは現在のソマリアの南部を植民地としていた。そこと境を接するエチオピアは当時、アビシニアと呼ばれ、連盟国であった。
1934年、ソマリアとエチオピアの境界付近でイタリアとエチオピアの武力衝突が起きた。これをワルワル事件という。翌年、両者に事件の責任はない、という仲裁判断が出た。真の紛争解決は、ワルワルがどちらの領土に属するか?、を判断するものでなければならなかったはずである。
このように中途半端な解決が図られた挙句、その2か月後にイタリアはエチオピアに侵攻した。ただちに、連盟総会は、経済制裁を調整する委員会の設置を勧告した。その結果、金融制裁とゴム・すず・アルミ・マンガンの禁輸が実行された。禁輸品目には、鉄、石炭、そして石油といった本当の意味での戦略物資は入っていなかった。制裁の効果はなく、1936年にエチオピアは併合されてしまい、連盟の制裁は終了した[9]。
以上のように、国際連盟の集団安全保障は、とりあえずは実行されるものの、手心が加えられ、実効性に乏しいものであった。仏作って魂入れず、の喩えどおり、大切であるのは手続きよりも意志であり、それがあれば第10条によって侵略に立ち向かうこともできたであろう。
サラエボ事件後の七月危機を反省して国際連盟規約は作られた。七月危機の原因である同盟政治は繰り返してならない過ちであった。規約の第20条は規約と両立しない連盟国間の条約は今後は結ばず、以前のものは廃棄する、と定めた。
例えば、A国とB国に紛争があって、これから理事会で審査しよう、という状況になったとする。本来は、現場や書類を調べて報告書に公正な勧告を書き込むべきである。しかし、第三者のC国がA国の同盟国であったとすれば、C国は審査結果を待たずにA国の味方となろう。A・C同盟が十分に強ければ、連盟は制裁を思いとどまるか、負け戦覚悟で制裁しなければならない。
このように、集団安全保障と同盟とは並び立たない。同盟を禁止するか、集団安全保障を同盟より優先するかしなければならない。連盟規約第20条の「功績」は、しいて言えば日英同盟を廃棄させたことにある。第二次世界大戦後、国際連合が同盟をどう扱ったかについては「集団安全保障と自衛権」の回で述べる。
2度目の世界大戦を国際連盟が防げなかった最大の原因は、提唱者であり、最強の国でもあったアメリカ合衆国が加盟しなかったからである。では、なぜ加盟しなかったかというと、上院に反対派がいて規約を批准できなかったからである。反対派の一部はベルサイユ条約に留保を付して骨抜きにしようとした。その代表は孤立主義者として知られたヘンリー・C・ロッジ上院議員であった。さらに極端に、国際連盟自体が許せない、という和解不能派という議員たちもいた。代表はウィリアム・E・ボーラ上院議員であった。
孤立主義者たちがロッジ留保と呼ばれる留保を付けようとした条項はいくつもあった。なかでも、侵略に対して領土および独立を守るという第10条が激しく批判された。なぜなら、それは連盟理事会に侵略から守る手段を具申するように求めるからである。孤立主義者にとっては、戦争を宣言するのはアメリカ合衆国の連邦議会の権限であり、軍隊の最高司令官はアメリカ合衆国の大統領であることは自国憲法に書いてあって、妥協できなかった。言い換えれば、連盟が勝手に戦争を命じたり、軍事作戦を立てたりすることは国家主権の侵害であった。
第10条をめぐるもの以外でロッジ留保が要求された条項には、委任統治、国内管轄権、そして山東半島の権益があった。山東半島のものは、ドイツから奪った権益を日本が得ることに中国が不満で、アメリカ合衆国に働き掛けた結果であった。ウィルソンが任期を終えたのち、ボーラ議員が提案して開かれたワシントン会議で問題は話し合われ、日本は権益を返すことになる。それはともかく、ウィルソンがベルサイユ条約を守るために留保を許さなかったため、批准できなかった。
アメリカ合衆国が連盟に入らなかったせいで、軍事力による制裁の実効性は怪しくなった。「仲裁、安全保障、軍縮」の平和殿堂の三本柱が唱えられ、基本戦略の練り直しが行われた。このうち「安全保障」を強化しようとした1923年の相互援助条約草案が失敗してからは、「仲裁」に期待が寄せられた。仲裁に国際法上の紛争だけでなく、あらゆる紛争を付託するのを国家の義務としよう、というジュネーブ議定書が1924年に作成された。エドワード・H・カーは手厳しく当時の雰囲気を書いている。
抽象的な合理主義が優勢になり、だいたい1922年からはジュネーブの潮流はユートピア的な方角に力強く向いた[10]。
もちろん、ジュネーブは国際連盟の本部があった町である。
国際連盟における集団安全保障の問題点を復習する。第1にアメリカ合衆国の不加盟、第2に理事会と総会の間の任務の重複である。満州事変とエチオピア侵攻の決議がともに総会で行われたように、何のために理事会が置かれているのか分からなくなった。第3に全会一致の議決である。もっとも、国際連合でも、安全保障理事会での拒否権によってしばしば決定が妨げられる似た問題がある。第4に脱退が容易であること、第5に軍事的な制裁が限定的であることである。これらの結果、加盟国は集団安全保障に不安を感じ、ふたたび同盟に頼っていくことになった。
その一方で、同盟にも欠点がある。ジョン・H・ハーツという学者が言った「安全保障のディレンマ」がそれである。ある国が軍拡に励んでも、他国も軍拡でそれに応じ、世界全体の軍備支出と戦時の犠牲者は増大する。あるいは、ある国が同盟の構築に励んでも、他国もまた対抗する同盟を構築する[11]。 やはり集団安全保障や軍縮は必要なのである。国際連盟の失敗を理想主義者の愚かさと片づけられない理由がそこにある。
[1] カント、『永遠平和のために』、宇都宮芳明訳、岩波書店、1984年。
[2] カント、『永遠平和のために』。
[3] 林董、『後は昔の記他―林董回顧録』、由比正臣校注、平凡社、1970年、284-285ページ。
[4] 林、『後は昔の記他―林董回顧録』、306ページ。
[5] バーバラ・W・タックマン、『八月の砲声』、上、山室まりや訳、筑摩書房、2004年、6-7、61-62ページ。
[6] ジョージ・F・ケナン、『アメリカ外交50年』、近藤晋一、飯田藤次、有賀貞訳、岩波書店、2000年、67ページ。
[7] Harold Nicolson, Peacemaking 1919 (Safety Harbor: Simon Publication, 2001), pp. 13-15, 34.
[8] 臼井勝美、『満洲国と国際連盟』、吉川弘文館、1995年。
[9] F. P. Walters, A History of The League of Nations, reprint (London: Oxford University Press,
1969).
[10] Edward Hallett Carr, The Twenty Years’ Crisis, 1919-1939: An Introduction to the Study of International Relations (London: Macmillan and co., 1940), p. 40.
[11] John H. Herz, “Idealist Internationalism and the Security Dilemma.” World Politics 2, no. 2 (1950): 157–80.
© 2026 Ikuo Kinoshita