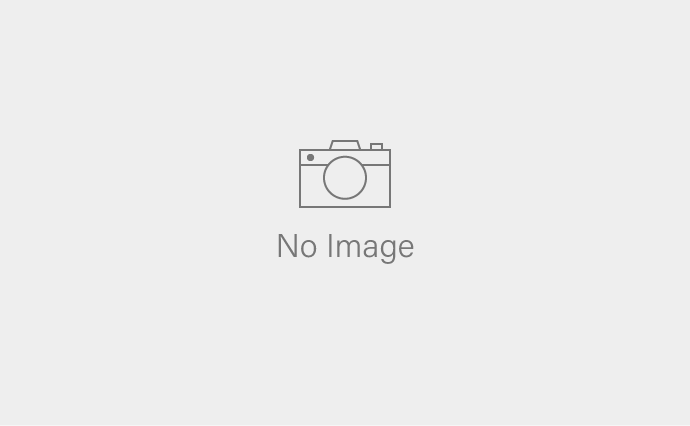国家主権は至高の権利である。では、それをそなえた主権国家は上位の権威に服さないのか? 服する場合もある。五大国が一致した国連安全保障理事会の決議は加盟国に対して法的な拘束力がある。しかし、今回は安保理の話でなく、仲裁や司法の話である。神の裁きであれば受けなければならないと感じるかもしれないが、国際社会の法廷の言うことに服さなければならないであろうか? 今回のテーマは、国際裁判所の管轄権と国家主権との関係を国際制度の変遷に言及しながら論じなさい、である。
国際の平和と安全を危うくするおそれがある紛争は平和的に解決しなければならない、と国連憲章第6章第33条1は定める。当事者どうしの交渉で解決できればよいものの、たがいに妥協を拒否してしまうとうまくいかない。そこで、第33条1は「審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的解決、地域的機関又は地域的取極の利用その他」を挙げて、平和的解決を催促する。これらはいずれも第三者を交えた過程である。それに続く第33条2・第34条・第35条・第36条は、安全保障理事会に第三者として紛争解決に関わってもらおうと設けられた仕組みである。
国際裁判の起源は諸説ある。古代ギリシャのアンピクテュオニアは有力候補の一つである。それは神殿への信仰に基礎を置くポリスの集団であり、日本語で「隣保同盟」と訳される。古代ギリシャの神殿というと、その一つで開かれたオリンピックを思い出す。諸ポリスは競技大会の開催中には休戦をした。また、デルポイのアポロン神殿は神託によってギリシャ世界の政治に大きな影響を与えた。日本の神社が祭りや武芸の奉納とならんで、神託や氏子の紛争解決を行ったのと同類のことである。アンピクテュオニアは確かにポリス間の紛争を仲裁した。しかし、宗教的な権威を背景とする点で現代の国際裁判と本質的に異なる。
中世の仲裁としては、ローマ教皇が行ったものが知られる。1493年、教皇のアレクサンデル六世は大西洋上に教皇子午線を引いた。「余は、福者ペテロにおいて余に与えられし全能の神の権威と、余が地上において執行するイエス=キリストの代理者職の権威において」、と彼はスペイン王に土地を与えた[1]。これに従うと、全アメリカはすべてスペイン側に入るはずであった。
ところが、海の覇者であったポルトガルは教皇子午線を認めなかった。1494年、ポルトガルとスペインはトルデシリャス条約に合意した。この条約はブラジルをポルトガル側に組み入れた。ブラジルでポルトガル語が話されるのはこれが原因である。教皇の神通力はルネサンスによって衰え、近代の国際裁判は宗教的要素を極力、排することになった。
最初の近代的な国際裁判は1794年のジェイ条約によって付託された。英米間で委員会が作られ、領土紛争や個人の賠償事件を解決した。ただし、この「裁判」は今日的意味でのそれと趣を異にする。私たちは裁判というと、裁判所が存在し、裁判官がいて、そこに当事者が事件を持ち込めば手続きが始まり、法律に基づいて判決が出て、判決に当事者が従い、公的機関がそれを執行する、と考える。これは国際裁判においては司法的解決と呼ばれる方式に近い。
ジェイ条約に基づく国際裁判は司法的解決でなく、仲裁という方式のものであった。仲裁には大きく二つの特徴がある。第1に、事件の付託には当事国の同意が必要である。付託合意のことを、コンプロミーとフランス語起源の用語でいうことがある。第2に、常設的な裁判所に訴えるわけでなく、アドホックに、すなわち付託合意のたびに、裁判所が組織される。この二つ目の特徴は、仲裁人または仲裁裁判官は付託合意のたびに選ばれる、と言い直せる。ジェイ条約に基づく英米間の委員会は実はこの点で例外的であった。なぜなら、国際仲裁の場合は中立的な第三国の仲裁人にキャスティングボートを持たせるのが普通であるが、この委員たちは当事国である英米の国民であったからである。
仲裁の意義を世界に認めさせたのはアラバマ号事件であった。アラバマ号は南北戦争で合衆国の船を60隻以上も仕留めた南部連合の軍艦である。南部連合の軍艦は、リバプールなど中立であるはずのイギリス本国で建造されていた。アメリカ合衆国はこれを中立義務への違反と非難し、賠償を請求した。
英米は戦争の危機に瀕した。両国は1869年にジョンソン・クラレンドン条約を結んで、事件を仲裁に付託しようとした。ところが、条約は批准されなかった。合衆国の上院外交委員長であったチャールズ・サムナーが条約に反対したからである。
背景には、カナダがイギリス領であり、そこと接するアメリカ合衆国の北東部ニューイングランドに根強い反英感情が存在したことがあった。サムナーはマサチューセッツ州選出であった。
手詰まりを打開したのは政治情勢の変化であった。イギリスのウィリアム・E・グラッドストン首相は、普仏戦争に伴う他国の勝手な動きに対応できずにいた。他方、アメリカ合衆国ではユリシーズ・S・グラント大統領が目ざわりなサムナーの追い落としを狙っていた。政敵たちを出し抜こうと、グラッドストンとグラントはワシントン条約を1871年に締結した。
1871年のワシントン条約は領土、漁業権、私有財産、そして中立法に関わる事件を、ジュネーブに置かれた国際仲裁法廷に付託した。アラバマ号事件に対する仲裁判断は1,550万ドルの賠償金をイギリスに科した。参考までに、ロシアからアラスカを1867年にアメリカ合衆国が購入した代価は720万ドルであった。賠償額は戦争を防いだ「道徳的価値と比べれば、天秤のうえのホコリのようにつまらぬもの」とグラッドストンは自画自賛した。アラバマ号事件に触れた冒険小説の『八十日間世界一周』は、事件がいかに話題になったかを描く。
この「世界一周の件」は、あたかも新たなアラバマ号事件でも起きたかのごとき情熱と熱狂をもって論じられ、語られ、解剖された。ある者はフィリアス・フォッグの側についた。他の者は彼に反対の立場を表明し、この人々がほどなく圧倒的多数となるのだった[2]。
ワシントン条約の成功は、国際仲裁への付託を増やした。1880年代から1930年代まで、それは主要な国際制度であり、戦争を避けることに貢献した。
日本もそうしたグローバルな傾向から自由でなかった。仲裁における日本の履歴は、苦力貿易の違法性を争った1873年のマリアルス号事件に始まった。これは勝訴と評価される。事実上の奴隷貿易を取り締まった行為はロシアの皇帝によって、合法と認められた。
続く1902年の家屋税事件は図らずも、外国人に対する不信感を生む結果になった。有能な外交官であった石井菊次郎は後年、回想して、「之より我国に於ては内外紛争を仲裁裁判に付託するも公平なる裁判は得られないとの感想が起こった」と述べる[3]。
外国人を居留地に閉じ込めていた時代、外国人に土地所有権を認めなかったかわりに、永代借地権を認め、その土地の上に建てられた家屋での収入を非課税とした。明治政府は宿願であった条約改正を果たし、居留地を廃止して、外国人に土地所有権を認めることになった。もはや土地所有権も認められるので、日本政府は永代借地上の家屋に課税を始めた。意外にも、ヨーロッパ諸国はこれに異を唱えた。勝訴する自信があった日本が常設仲裁裁判所に付託したところ、敗訴してしまった。それから一世紀近く、日本は仲裁から遠ざかった。
1999年のみなみまぐろ事件は、国際海洋法裁判所における手続きと仲裁裁判所における手続きの二つがともに国連海洋法条約に基づき、同時に進んだので混乱しやすい。みなみまぐろは高度回遊性の種であるので、日本は生息域に近いオーストラリアおよびニュージーランドと、みなみまぐろ保存条約を結んだ。この条約のもと、調査漁獲の計画を作ることになったが、計画ができないまま、日本は調査漁獲を行った。オーストラリアとニュージーランドは国際海洋法裁判所と仲裁裁判所に訴えた。国際海洋法裁判所は日本の調査漁獲は違反であると暫定措置を出した。ところが、仲裁裁判所のほうは、自裁判所は日本の調査漁獲を扱う管轄権を持たないとし、国際海洋法裁判所の暫定措置は無効と判断した[4]。日本が勝訴であったか、敗訴であったか、判断しがたい。
さて、武力紛争は非武力紛争がエスカレートして起こるものである、という前提に立てば、非武力紛争を仲裁によって解決できれば、戦争は起こらない。この観点を平和的紛争解決という。
平和的紛争解決の難点は、非武力紛争を仲裁に付託する合意がなかなかできないことである。逆に言えば、付託合意が容易になれば、平和的紛争解決は成功しやすくなる。義務的一般仲裁条約では、一方の締約国が訴えれば、自動的に他方の締約国との仲裁手続きが開始されることにして、紛争解決の難点をとり除く。19世紀の終わりから、たくさんの義務的一般仲裁条約が結ばれた。
付託合意ができたならば、第2段階として仲裁裁判所が組織されねばならない。その制度化のために結ばれたのが国際紛争平和的処理条約であった。この条約は1899年の第1回ハーグ平和会議で採択された。この会議はオランダのハーグ市にある宮殿ハウステンボスにおいて開かれたが、ロシア皇帝ニコライ二世の呼びかけにこたえたものであった。
国際紛争平和的処理条約に基づいて、常設仲裁裁判所(PCA)が設立された。その仲裁裁判官は固定しておらず、次のように選ばれる。締約国が出した候補者の名簿があり、そこから紛争当事国が各2名の仲裁裁判官を選ぶ。この4名が1名の上級仲裁裁判官を選ぶ。選ばれた5名の仲裁裁判官がその事件の裁判部を構成する。常設仲裁裁判所は、「常設」でも、「裁判所」でもない、と皮肉られるが、それは当たっている[5]。
第1回ハーグ平和会議は、戦争法と人道法の進歩でも大きな成果を上げた。ハーグ陸戦条約、ジュネーブ条約を海戦に適用する条約、そして、交戦手段に関する三つの宣言(毒ガス・ダムダム弾・気球からの爆撃)が採択された。
ところが、第1回ハーグ平和会議の3か月後、イギリスはボーア戦争を始め、平和の理想は傷ついた。会議に参加していたアメリカ合衆国の海軍教官、アルフレッド・T・マハン、は義務的一般仲裁条約に反対した。それは自国の国益に反するから、という理由であった[6]。
PCAはピースパレス(平和宮)というマンションのような名前の建物に入居している。このハーグに建てられた城館風の擬古的な近代建築は、アメリカ合衆国の鉄鋼王にして慈善家のアンドルー・カーネギーによる150万ドルの寄付をもとに建てられ、1913年に彼も参列して開館した[7]。
PCAは21世紀になっても注目される。南シナ海問題では、中国が岩や暗礁を占拠し、領有を主張する。フィリピンは国連海洋法条約に基づき、常設仲裁裁判所に付託した。2016年、ミスチーフ礁など中国が「島」と称して領有を主張するものは「低潮高地」であり、領海および排他的経済水域を設定できない、とPCAは判断を示した。
第一次世界大戦の結果、国際連盟が設立され、やや遅れて常設国際司法裁判所(PCIJ)が開廷した。PCAと違い、PCIJでは固定した裁判官たちがピースパレスで勤務した。その意味で、真に「常設」的な「裁判所」であり、仲裁と司法的解決の違いはここにある。
国内システムの裁判所と似てきたが、一方の当事者が訴えても他方が裁判所の管轄権を受け入れなければ、審理が行われない問題が解決されたわけでない。PCIJの設立に伴い、義務的一般仲裁条約と同じように義務的一般司法的解決条約を結んで付託の自動化を約束する国々が現れた。
それとともに、PCIJ規程では新しい自動化の方式が発明された。特別議定書の手続きを定めるその第36条2にしたがうと、紛争が発生する以前に、裁判所の権限を受け入れる旨の宣言を特別議定書でした国は訴訟の被告となった時に裁判を拒めない。
PCIJの後身である国際司法裁判所(ICJ)においても、やはり規程の第36条2に、強制管轄権受諾に関する宣言の定めがあり、それを受諾し、他国に訴えられた国はICJの管轄権に服することになる。日本は1958年にこの宣言をした。
国際連盟によって平和的紛争解決は「平和殿堂の三本柱」の一つとされた。三本柱とは、紛争解決(仲裁)、安全保障、そして軍縮である。紛争が起きたならば、まずは仲裁など平和的解決の努力をする。仮にそれが失敗しても、軍縮をしていればすぐには侵略はできない。それでも情勢がよくならないならば、連盟の加盟国が力を合わせて侵略を制裁――集団安全保障――する。
平和の三本柱を組み込んだものが、1924年に署名されたジュネーブ議定書、すなわち国際紛争平和的処理議定書、であった。しかし、この議定書はイギリスが批准しなかったため反故になり、平和殿堂は幻と消えた。
審査と調停は、仲裁および司法的解決と同様、第三者による紛争解決手続きである。審査は合法や違法を判断せずに、事実認定のみを行う点が両者と異なる。
1904年のドガーバンク事件は日露戦争中、バルティック艦隊が日本海に来る途中に起きた。同艦隊が北海でイギリスの漁船を日本の水雷艇と誤認して撃沈したのである。イギリスと日本には日英同盟があったので一時は英露関係のゆくえが心配された。両国を周旋したフランスの努力のかいあって、国際審査委員会が作られ、砲撃を正当化する事実はなかった、と審判した。ロシアは賠償し、事なきを得た。
ドガーバンク事件の解決により、審査が平和のために有用であると分かり、注目された。ブライアン条約は第一次世界大戦の直前、アメリカ合衆国の国務長官ウィリアム・J・ブライアンがワシントン駐在の外国使節団に呼びかけて結ばれた一連の条約である。それは常設の審査委員会を締約国間に設置する、という内容であった。二十いくつも、この提案に応じる国があったが、平和には貢献しなかったと考えられる。
調停は第三者が調停案を勧告する方式である。家庭裁判所の調停ならば、知っている人は多いであろう。調停案には仲裁判断と違って法的拘束力がない。調停役を買って出る国はあまりない。紛争当事者の恨みを買うことがあり、また、よほどの威信や権威が調停役にないと、せっかくの案が尊重されないからである。それゆえ、世界機構にこそ調停役を果たすことが期待される。国際連盟規約の第15条と国連憲章の第36条は、それぞれ連盟理事会と安全保障理事会による勧告について定める。
「1丁目1番地」という言葉は「第1の前提」や「最優先されるべきこと」といった意味である。国連憲章の第1条1は何であろうか? それは国連の目的の第1である国際の平和および安全の維持である。その方法の一つが「平和を破壊するに至る虞のある国際的の紛争又は事態の調整又は解決を平和的手段によって且つ正義及び国際法の原則に従って実現すること」という条文である。このように高い期待が寄せられる国際司法裁判所(ICJ)は十分に活用されてきたか?
第二次世界大戦後、国際連盟が国際連合に取って代わられたのと対応し、PCIJはICJに置き換えられた。PCIJの日本人裁判官のなかには裁判長を務めた安達峰一郎がいた。ICJの裁判官には、前職が最高裁判所長官の田中耕太郎、同じく東北大学教授の小田滋、国連大使の小和田恒、そして東京大学教授の岩沢雄司がいる。
国際司法裁判所の15人の判事は加盟国が指名した候補者の名簿から、安保理と総会によって選挙される。裁判所の最終的な決定には判決と勧告的意見がある。判決は、当事国により付託される争訟事件に対してのものである。勧告的意見は、総会や国連専門機関によって尋ねられた問題へのものである。以下では、判決と勧告的意見の実例をいくつか見る。
初めての争訟事件はコルフ海峡事件であった。事件は1946年に起きた。イギリスの軍艦がアルバニアの領海であるコルフ海峡を通った際に、機雷に触れて爆発した。国際司法裁判所は1949年に、イギリス軍艦による無害通航権を認めてアルバニアに賠償を命じた。その一方で、イギリスがアルバニア領海の機雷を掃海する権利は認めなかった[8]。当事国が出るところに出て、解決できた、という点では国際裁判所の役割が果されたと評価できる。
領土紛争の例としてプレアビヒア寺院事件を取り上げる。これはタイとカンボジアとの争訟であるが、カンボジアがフランスの植民地であった1904年に、タイとフランスとのあいだで条約が結ばれ、これに基づき作成された1908年の地図では、プレアビヒア寺院の遺跡はカンボジア側に含まれた。この遺跡に対して、タイが領有権を主張した。
タイは1954年に遺跡を占拠し、そこにあった骨董品を移動させてしまった。国際司法裁判所は1962年、寺院はカンボジアに帰属し、タイは骨董品を返還しなければならないと判決した。ところが紛争は収まらず、武力衝突さえ発生した。2011年、カンボジアは1962年の判決の意味と範囲を説明するよう国際司法裁判所に要請した。2013年の判決は、遺跡周辺の土地の帰属については裁判所は判断しない、というものであった[9]。
2025年、カンボジアとタイのあいだに大規模な国境紛争が起きた。国境問題そのものを解決することが重要であるが、これまでタイはその問題での管轄権を国際司法裁判所に認めていない。
1984年に提訴されたニカラグア事件は、超大国がICJを侮辱して痛々しい記憶を残した。アメリカ合衆国は自国が過去に行った強制管轄権の受諾をいとも簡単に覆した。
ニカラグアの左翼政権を揺さぶるため、アメリカ合衆国はニカラグアの領海と内水に機雷を敷設するなど主権侵害を行った。両国は国際司法裁判所の強制管轄権を受諾していたため、前者が提訴しようとしたところ、その間際にアメリカ合衆国が受諾を撤回した。それでも、裁判は始まり、機雷敷設等の行為を集団的自衛権の発動とするアメリカ合衆国の主張をICJは認めなかった。
日本が当事者となった争訟に、南極海捕鯨事件がある。国際捕鯨委員会(IWC)は商業捕鯨を禁止したため、日本は科学的研究のための調査捕鯨としてクジラを獲っていた。捕鯨の禁止を主張するオーストラリアは2010年、日本が科学的調査と称しているものは商業捕鯨であるとして、南極海での捕鯨を中止させるよう国際司法裁判所に訴えた。国際司法裁判所は2014 年、オーストラリアの主張を認め、日本に中止するよう命令した。2019年、日本は国際捕鯨委員会を脱退した。
勧告的意見については、パレスチナ占領地壁構築事件を取り上げる。ヨルダン川西岸地区は第三次中東戦争の占領地である。2000年のインティファーダ、すなわち人民の武力闘争、はその土地のユダヤ人の安全を脅かした。イスラエル政府は2002年、ユダヤ人居住地を囲うフェンスや有刺鉄線を建設した。しかし、これは、壁によってユダヤ人の土地とパレスチナ人の土地を分割し、イスラエルによる領有の主張を既成事実にする企てではないか?、と危惧された。そこで、国連総会は国際司法裁判所にその違法性について勧告的意見を求めた。国際司法裁判所からの答えは、壁は違法であり、すべての国は壁を承認しない義務を負う、というものであった[10]。 国際司法裁判所の紛争解決はつねに明快な結果をもたらしたわけでない。仮に判決や勧告的意見にたどり着いたとしても、紛争の根源は未解決であったり、不満な当事国は回避策を探したりしたからである。
[1] 大沼保昭、藤田久一訳、『国際条約集 2003年度版』、有斐閣、2003年、757ページ。
[2] ジュール・ヴェルヌ、『八十日間世界一周』、鈴木啓二訳、岩波書店、2001年、74ページ。
[3] 石井菊次郎、『外交余録』、岩波書店、1930年、256ページ。
[4] “国際海洋法裁判所 (ITLOS:International Tribunal for the Law of the Sea),” 外務省, January 4, 2024, https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kaiyo/itlos.html, accessed on February 15, 2025.
[5] Edward Hallett Carr, The Twenty Years’ Crisis, 1919-1939: An Introduction to the Study of International Relations (London: Macmillan, 1940), p. 246.
[6] バーバラ・W・タックマン、『世紀末のヨーロッパ―誇り高き塔・第一次世界大戦前夜』、大島かおり訳、筑摩書房、1990年。A. T. Mahan, Armaments and Arbitration, or the Place of Force in the International Relations of States (New York: Harpers & Brothers, 1912), pp. 93-94.
[7] アンドリュー・カーネギー、『カーネギー自伝』、坂西志保訳、中央公論新社、2002年、288-289ページ。
[8] 松井芳郎編、『判例国際法』、第2版、東信堂、2006年、150-155ページ。
[9] 松井編、『判例国際法』、136-140ページ。
[10] 松井編、『判例国際法』、630-635ページ。臼杵陽、『イスラエル』、岩波書店、2009年、201ページ。
© 2026 Ikuo Kinoshita