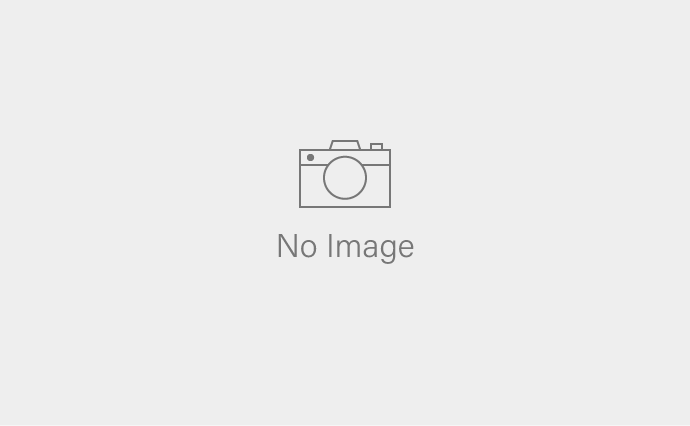グローバルガバナンスについて語ることは、神や仏を語ることと、さほど変わらない。災害、貧困、病気、あるいは戦争などの苦しみを人類はまだ克服していない。数千年間、神や仏の救いを求める人々が聖像に託したものを、現在、グローバルガバナンスの概念が引き受けようとしている。
一握りの人々にとっては、グローバルガバナンスは理想主義的な国際連合のイメージである。それは慈悲深く、人類を救う世界政府である。理事会、総会、事務局、そして専門諸機関が描かれた機構図は、ありがたい現代のマンダラである。実際は、社会科学の概念にすぎないグローバルガバナンスに人間を救う力はない。
理念(イデア)を究めることによって、グローバルガバナンスの実像に迫ることはできないか? ガバナンスはコーポレートガバナンスが企業統治と訳されるように、統治を意味する。もともとは船のかじ取りを意味するギリシャ語がその語源であった。目的地に向かうにせよ、魚を釣るにせよ、船にはかじ取りが必要である。
船のかじ取りとガバナンスはたしかに似ている。船に目的地があるように、ガバナンスには目的がある。そこに到達するために、船は舵を取り、ガバナンスは意思決定をする。船はスクリューで進み、ガバナンスは官公庁などが推進する。
ジェイムズ・N・ローズノーという学者の場合は、「秩序プラス意図性」であるとガバナンスを解説した[1]。秩序とは、物事が規則に従っていることである。規則といっても、法律のような静的で画一的なものばかりでなく、物価・所得・出生率など統計諸指標をバランスをとりつつ管理する動的過程も含まれる。他方の意図性は機能や目的適合性と言い換えられる。どの目的や価値観を志向するかにはじまり、それを実現するためにはどの手段や指標を選ぶべきかが問題になる。
よって、本書は次のようにガバナンスを定義する。共同体において定められた意図または目的に注目し、現実がそれにどの程度、または、どのように従っているかがガバナンスである、と。
グローバルは地球的という意味であるから、グローバルガバナンスは地球統治という意味の空間的概念である。ただし、それをグローバルガバメント、すなわち地球政府や世界政府、ととり違えてはならない。
世界政府論の典型は、戦争をなくするには主権国家を廃止することが必要である、という主張である。ヒロシマ・ナガサキの翌年である1946年に論壇をにぎわさせたのはその一種であった。原子爆弾の製造を禁止することは国家主権に基づく国際連合にはできず、世界政府の手によらなければならない。ソビエト連邦に世界政府への加盟を要求し、拒まれれば戦争も辞さない。そう乱暴に議論したのはバートランド・ラッセルやアルバート・アインシュタインといった知の巨人たちであった[2]。
このように、世界政府論は人類が理性を失った時代に唱えられる傾向がある。ソ連との第三次世界大戦にならず、本当によかったと思う。
現実のグローバル社会を見すえれば、最有力なアクター(行為主体)は世界政府や国際機構でなく、主権国家である。地球儀を眺めると、陸地を仕切るものは国境線であり、それらにとり囲まれたものが200ちかくの主権国家である。これら国家のネットワークが、グローバルガバナンスの空間的な骨組みまたは構造である。国際連合をはじめとする国際機構も、国家間の条約によって設けられた主権国家ネットワークの一部である。
グローバルガバナンスは、国際政治やグローバル政治とは違う。政治といえば、選挙や政治家に関わる権力闘争を指すのが一般的である。国際政治において、この見方は現実主義という学派によって代表される。その論者ハンス・J・モーゲンソーは教科書の題に『諸国民間の政治』と付けた。副題は「力と平和を求める闘争」である[3]。力だけでなく、平和も求めているのでグローバルガバナンスの観点は組みこまれている。
平和にせよ、繁栄にせよ、持続可能な開発にせよ、目的や意図性は人間が決める主観的なことである。それらは個人や集団により異なることもあれば、共通することもある。異なる場合はグローバルガバナンスという言葉より、権力政治という表現のほうがしっくりいく。
国際ガバナンスとグローバルガバナンスにも違いがある。国際ガバナンスは、国家間のネットワークだけであり、国家を固い殻に覆われたボールに見立て、その内部がどうなっているかを問わない、いわゆるビリヤードボール・モデルである。
国家の内側における統治であるナショナルガバナンスは国際ガバナンスと判然と区別される。ただし、ユニラテラリズムといって、一国だけでの政策が平和・繁栄に貢献することもあるので、かならずしもグローバルガバナンスと相反するわけでない。
これらとは別に、戦地における赤十字の人道活動のような非政府アクターによるトランスナショナルガバナンスもある。政策の参考にされるという点では、ニュースサイトの情報や大学等での研究もグローバルガバナンスに貢献する。
つまり、グローバルガバナンスは国際、ナショナル、そしてトランスナショナルの空間的なレベル、またはレイヤー、のガバナンスが合わさったものであり、下のように定式化される。
グローバルガバナンス
= 国際ガバナンス
+ ナショナルガバナンス
+ トランスナショナルガバナンス
+ α
αは念のために加えた。月など天体を含む宇宙、国家領域に含まれない南極や深海底、あるいは近年はサイバースペースといった諸空間も近年、無視できなくなってきたからである。
空間的には四つのレベルに分けられても、ガバナンスのメカニズムまで異なる本質を持つわけでない。近代社会で発達したメカニズムは、市場、政府、そして人権である。ただし、世界の文化や地域によって、どれが強く、どれが弱いかについては差異がある。アメリカでは市場と人権、社会主義国では政府が強い。伝統的な社会では家族や宗教が根強く、封建主義や神権政治が支配的である。
市場、政府、そして人権のメカニズムはナショナルなレベルで進化し、まとめて自由主義国家のモデルを形作った。グローバルガバナンス全体を理解するための土台として、この回ではそれぞれのメカニズムを解説する。なお、市場・政府・人権はおおむね経済学・政治学・法学の学問分野に相当することにも留意してほしい。
自由主義国家のモデルは市場・政府・人権を調和させることを求める。すなわち、政府は秩序を守り、政策を施行する。市場は財産権に基礎を置き、資源配分を効率化しつつ、人々の選択を多様化する。人権は政府の圧制と市場の暴走から個人の生活を守るだけでなく、政府そのものが民主的な投票によって組織されることを保障する。
古代から絶対主義にいたるまで、政府はともすれば個人を抑圧した。自由主義国家の特徴は、政府の力を制限し、個人の自由を十全に働かせ、市場と人権による幸福を促す点にある。
市場は自由な選択、つまり最適化、を実現する分権的なメカニズムである。いかなる財を、いかなる量、生産・取引・消費するか、の決定はそれぞれの経済主体に委ねられる。各自が利潤を極大化しようとした結果、分業と交換が行われ、社会全体の生産は効率的になり、拡大する[4]。アダム・スミスは分業の端緒を次のように想像する。
たとえば、狩猟民または牧羊民の種族のなかで、特定の者が他のだれよりも手ばやく巧妙に弓矢をつくるとしよう。かれは、弓矢をその仲間の家畜やしかの肉としばしば交換し、そうするうちに、けっきょくこういうふうにするほうが自分で野原にでかけて行ってそれらを捕えるよりもいっそう多くの家畜やしかの肉を獲得できる、ということを発見するようになる。それゆえ、自分自身の利益に対する顧慮から、弓矢の製造ということがだんだんとかれのおもな仕事になるのであって、そこでかれは一種の武器製造人になる[5]。
貨幣が発明されると、商品には価格が付いた。価格、または価格体系という数字のセット、は比較と演算が可能である。そうした情報の重要性を唱えたのがフリードリヒ・A・フォン・ハイエクである。
価格に反映されたり凝縮される情報の全体はまったく競争の産物である。競争は特別な諸事情を探求する機会をもつ人に有利にそれをおこなう可能性を与えるだけでなく、そのような機会があるという情報を他の当事者に伝達することによって、一つの発見的手続きとして作用する。市場ゲームの競争的努力が広範に保有されている知識の活用を保証するのは、コード化された形でのこの情報伝達によるのである[6]。
価格という情報に基づいて、参加者は相互作用する。シナリオがあるわけでない。強制があるわけでない。この意味で市場は分権的で自生的な秩序である。なければならないのは、何よりも、競争を阻害しないためのルールである。
商品が安く買えて、高く売れるということは、それまで以上に消費できることにほかならない。生産、支出、そして所得の拡大をもたらすメカニズムは「神の見えざる手」[7]とたたえられる。なかには市場の動きについていけず、非情にも失業する者もいる。それでも、大きくなった社会全体のパイから失業者に補償すれば問題は解決する。
「最大多数の最大幸福」という意味での功利主義は市場メカニズムとは本来、異質の思想である。それは設計を伴うからである。市場が自然発生的とすれば、設計は人為である。ハイエクが主張するのは、政府は設計には手を染めず、市場競争が持続可能であるためのルールの管理に徹するべきである、ということである[8]。
スミスもまた、投資に関して、資本家は「どのような政治家または立法者などがこの個人のためにそうしうるよりもはるかによく判断しうる」と資本家の役割を評価する[9]。なぜ、資本家は政治家よりも資本の管理にすぐれているのか? 投資は、値上がりしそうな商品を先読みし、その生産に資本を投じておいて多くの配当を得る行為である。個人が排他的に資本を占有し、処分する権利を有することにより、最も注意が行き届き、最も適切な判断ができ、最も迅速に行動することができる。古くはアリストテレスが妻子を共有すること(!)を批判したことにさかのぼる私有財産擁護論の一つがこれである。
最大の人数の人に共通なものは。最小の配慮しか得られない。なぜなら人びとは私的なものは、これをもっとも気遣うけれども、公共のものは、これを顧みることが少ないか、各人に割当てられた分しか関心をもたないからである。他の理由はさておき、他人が気遣っていると思うと、人はもっと軽んじるようになる[10]。
以上をまとめると、個人の関心、情報、そして財産を基本要素として作用するのが市場である。他人のものや公共のものを管理する際、政府は脇役に徹するべきである、とスミスとアリストテレスは言っている。なぜなら、自分のものほどの関心を他人や公共のものには持てないからである。
ハイエクは自分が関心を持てることは身の回りのものだけであると言う。
すなわち人間の精神が事実上理解できることのすべては、自分を中心とする狭い範囲の事柄であるという事実、そしてたとえかれが完全な利己主義者であろうと、またはこの上もなく完全な利他主義者であろうと、かれが事実上関心をもつことができる[傍点-訳者注]人間の必要は社会のすべての構成員の必要のなかではほとんど無視しうるほど小さい部分に過ぎないという事実がこれである[11]。
事情を最もよく知る当事者間で、売買はじめ諸契約は交渉されるのが理想であるというハイエクの見方では、政府が社会のすべてのことを決めることは好ましくない。なぜなら、政府の担当者もまた、身の回りのことしか知らないからであり、世界中に散らばっている現場の情報のほとんどについて無知であるからである。
政府の役割は市場メカニズムへの信奉が強い近代では皆が大賛成というわけでない。より辛辣な政府に対する見方は、そもそも政府は特定集団による不当な私物化によって脅かされている、というものである。ハイエクの場合、マルクス主義のように政府をブルジョワジーによる「搾取の道具」と決めつけない。しかし、その危険があると見るのは、次の一節から明らかである。
民主的諸制度の発展史全体は、特定集団が自分たちの集合的利益に利するように政府装置を誤用するのを妨げるための、不断の闘争の歴史である。この闘争はもちろん終止符をうったわけではなく、組織化された利害関係者の共謀によって形成される多数派が決めるものを一般的利益と定めるのが今日の傾向である[12]。
最大多数の最大幸福は多数者の専制を正当化する思想である。多数者も、少数者も、自由になるための方法の一つは、合意できる部分だけに政府の役割を制限することである。ここまでは筆者もそのとおりであると考える。
合意できる部分だけに政府の役割を制限する方法として、ハイエクが勧めるのは結果でなく手段、つまりルールについてだけ、政府が調整することである。
どの特定利益が他の利益より選好されるべきかということにかんする合意が必要であるということになれば、利害の一致ではなく、あからさまな対立が存在することになろう。そのような社会における合意や平和を可能にするには、個々人に目的についての合意を求めることなく、多種多様な目的に貢献できて、自分自身の目的追求の助けになると各人が考える手段についての合意だけを求めることである。そして、特定目的についての合意が可能な小集団を越えて、そうした合意の不可能な大きな社会[強調-訳書]の構成員にまで平和的秩序を拡張できるかどうかは、目的についてではなく手段についてだけ合意すればいいような協力方法を発見できるかどうかにかかっている[13]。
ルールについてだけ合意し、結果を放任するという解決策は、実行可能でないと筆者は考える。あるルールからどのような結果になるか、だいたい予想が付くからである。弱肉強食にも、悪平等にも、ルールのさじ加減によって、どうにでも結果は動かせる。公正さを装いつつ、実際は結果を予想しながらルールを考案するのは、わが国では霞が関の官僚たちが得意とすることであろう。ハイエクはアメリカ合衆国の立法府と司法府を信頼しているので、日本の立法過程がいかに官僚主義に都合がよいか、には思いいたらない。
それより、市場を信奉するスミスやハイエクさえ喜んで受け入れる政府の役割があることに注目したい。
私的なインセンティブだけでは必要な供給がなされない場合、政府を含む公的なガバナンスが求められる。寄付と料金だけで、道路や軍隊はまかなえない。災害や感染症流行の時には、正確な情報を伝え、場合によっては強制しながらも、個人の行動を導かなければならない。犯罪には刑罰で、腐敗には綱紀粛正で報いるべきである。選択できない規格品であっても、すべての人に供給されなければならない財やサービスがあるのであれば、その供給を優先する制度を作らなければならない。例えば健康保険である。ましてや、緊急事態になればあらゆる選択機会は失われるから、そうした事態への対応はすべてに優先する。
外部性という経済学の概念は、公的介入が必要な多くの場合を説明できる。教科書はこの概念を次のように定義する。
外部性は、経済活動により、第三者にスピルオーバーする費用または便益が生まれることである[14]。
道路はライフラインと呼ばれるほど広い範囲に便益を与える。学校は卒業生の生涯所得を上げるだけでなく、技術や社会慣習など文明そのものをレベルアップする。国家安全保障や災害対応は、ふつう個人が認識しないリスクを社会全体で計算に入れて、はじめてなりたつ。
アダム・スミスも国家の義務として、国防費、司法費、公共事業費、教育費、宗教費、そして、元首の威厳を維持する経費を挙げた。最後のものは宮殿などである[15]。ハイエクも、ルールの調整だけを政府の任務と考えるわけでない。スミスが挙げたものに加えて、治水、度量衡、土地登記、地図、統計、品質証明を並べる[16]。
スミスとハイエクが挙げた政府活動は公共財の一種である。公共財とは便益、すなわち正の外部性、を社会に与えるものであり、自然環境や健康もそのうちに数えられる。社会資本やグッドガバナンスといった人間活動を含める場合もある。これらに政府が介入するべきであることにはコンセンサスがある。
他方、経済活動が第三者に、費用すなわち負の外部性を与える場合、例えば工場が有害ガスを出すような場合にも、政府が規制、補償、課税、仲介、さらには直接供給などで関わらなければならないことがある。
正負の外部性に対処するために政府は必要である。確かにハイエクは、人間の関心と知識は身の回りの狭い範囲にしか及ばない、と見抜いたものの、政府をなくすわけにはいかない。
社会のネットワークをイメージしよう。直接つながっている相手を1次の距離、一つ空けると2次の距離……、と呼ぶと、人間の関心が及ぶ狭い範囲とは、せいぜい3次か4次くらいまでの、次数が低い相手までのネットワークである。家族関係では3親等のいとこくらいまでである。
霞が関の官僚はどのくらいの人々まで、関心と知識が及ぶであろうか? 永田町の政治家、都道府県・市町村の地方公共団体、外国政府、そして各種団体あたりは日常の接触があろう。しかし、都心から離れた辻々や津々浦々の庶民生活までは目が行き届かない。こうした一極のネットワークでは不可視の部分が大きくなるので、地方自治が必要になる。さらに遠く、外国のジャングルや砂漠で生きる人々のことなど見当もつかない。それゆえ、グローバルガバナンスはナショナルガバナンス以上に多数の中心に分散してネットワークを張りめぐらさなければならない。
中心からは不可視の場所にも有権者(コンスティテュエンシー)がいる。そこの有権者たちが自由な選択を共同的に行う状況にない、という事態はあってならない。ナショナルなレベルの選挙で民主主義が達成されていても、それで終わりではない。辻々や津々浦々の有権者の声を聴くためには地方自治が最も確かである。ハイエクは次のように言う。
ある特定の地域や地方の住民の必要だけを満たす多くの集合財の場合には、サービスの管理および課税も、中央当局ではなく地方当局の手に委ねられるならば、いっそうきめ細やかにこの目標に接近できる[17]。
有権者とは、守られるべき基本的な権利を有し、それを実現するためにガバナンスに参加する人または集団である。ギリシャ語のかじ取りを意味する語源には船員しか有権者はいなかったが、現代のガバナンスは、政府と住民とそれらを取り囲む人々がセットになってはじめて成立する。不可視の有権者がなくなるようにガバナンスのネットワークを張りめぐらせることが要請される。連邦国家は、州を中央政府と併存させて、この課題に応える。
また、ヨーロッパの国際統合においては補完性(サブシディアリティ)の原則がある。EU(欧州連合)は、国・地域・地方では十分になしえないことだけを行う国際機構である[18]。ブリュッセルの欧州委員会は加盟国の多くの有権者にとっては遠いところであって、その指揮下にあるエリートたちにガバナンスのすべてを委ねてしまうことに不安がある。
ガバナンスのネットワークというイメージは、古くはアナーキズムの一派が掲げてきた。ロバート・ノジックは、守るべき権利を生命・財産・賠償取り立ての「自然権」に絞り込み、個人がそれらだけを相互に扶助しあう保護協会を構想した。ノジックやハイエクの1世紀まえに、国家主権を主張せず、自発的契約を基礎とするガバナンスを唱えたのはピエールジョゼフ・プルードンである[19]。『連合の原理』から引用する。
―前略―連合した諸国家に対し、それらの主権、領土、市民の自由を保証し、それらの紛争を調整し、全般的な措置によって安全と共通の繁栄にかかわる一切に備えることを目的とする契約、この契約は責任を負う利害の大きさにもかかわらず、本質的に限定されたものである。―中略―私は連合の権限は、実際に量的に、村や地方の権限を超えることは決して許されない、といいたい。同様に村や地方の権限は、人間や市民の権利や特典を超えることは許されない。そうでなかったら、村は共同体となろう。連合は君主制的中央集権に戻ることとなろう。単なる代理人であり、従属的な役割である筈の連合の権威は、優越するものとみなされることであろう。―中略―連合した諸国家は、県に、州に、支部ないし出先機関に変わることであろう[20]。
もちろん、ネットワークを分散する方法は、地理的なものだけでなく、機能的なものもある。実際、執行府では省庁や大臣に責任を分散させることが広く行われている。1960年代には、ロバート・ケネディがアメリカ合衆国の対外政策について次のように書いた。
国務省以外の多くの政府機関や省庁が、外交分野で主要な責任および権限をもっている。そのなかにはペンタゴン(国防総省)、CIA(中央情報局)、AID(国際開発局)、さらに関与の度合いはそれらより小さいが、USIA(海外情報局)その他の独立あるいは半独立の省庁が含まれている[21]。
外交官のネットワークである国務省とは別に、ペンタゴンは世界に軍人のネットワークを持ち、CIAは公安関係者の、USAIDは援助関係者とのコネを持つ。そうした省庁によるサービスの対象には企業や業界団体や専門家といったクライアントがぶら下がる。
こうしたクライアントが政治過程に組み込まれることを職能的な代表制と呼ぶ。それをさらに発展させるべきかどうか、は議論あるところである。なぜなら、コーポラティズムという職能的代表制がファシズムの政治体制に採用された過去があるからである[22]。とはいえ、円滑なガバナンスの遂行には、一般市民の声と同様、業界団体や労働組合といったクライアントの声を吸い上げるほうがよい場合がある。賃金の水準は、経営者の代表と労働者の代表の意見を政府が聴きながら決められることはまれでない。
これまで、市場と政府について見た。最後は人権である。選択の自由に不可欠であるのは自由権と財産権であり、市場取引の基礎でもある。有権者の立場でガバナンスに参加するには、選挙権、請願権、そして表現の自由が保障されなければならない。生存権や教育を受ける権利は、人権の根底にある人間の尊厳を実質的なものにする。
日本のような所得水準が高い自由主義国家では、人権は守られて当たり前である。しかし、世界中で人権は守られているのか?、つまり普遍的人権は達成されているのか?、と問うと、不安になってくる。
とはいえ、この思想そのものの歴史は古い。240年前、ドイツの哲学者イマヌエル・カントは「世界市民的見地における普遍史の理念」という遠大な構想の論文を著した。自由の濫用による人間間の敵対を止めるため、法はまず、国家の内部で作られた。しかし、この結果、国家の間で敵対が始まってしまった。戦争を止めるためには、国際同盟を結んで共通の法を作らなければならない。これは人類によって最後に解決される問題である、というのが内容である[23]。
カントはあまりに時代に先行しすぎた。1784年には、フランス人権宣言も発せられていなかった。
1941年に、アメリカ合衆国大統領、フランクリン・D・ローズベルト、が「四つの自由」について演説した時、世界は自由の勢力とそうでない勢力とで真っ二つに割れていた。7年後の国連総会における世界人権宣言が初めてグローバルな機関が人権を数え上げた。そのことをハイエクは次のように批判した。
そこでは最初の二一カ条のなかに古典的な市民の権利を列挙した後に、新しい「社会的・経済的権利」を表現することを意図した七項目の保障がさらにつけくわえられている。これらの付加条項のなかで、提供する義務また負担を誰にも負わせることがないままに、「社会の一構成員として、あらゆる人に」特定の利益にたいする積極的な請求権の充足が保障されている。またその文書は、裁判所が特定の事例についての内容が何であるかを決定できるような仕方でこれらの権利を定めることに完全に失敗している[24]。
つまり、誰も給付の責任を負わないままに、それを受け取る権利の理想だけを国連総会が謳ってみせたとしても、絵に描いた餅である、と言う。これが書かれた1970 年代における最貧国の実情を想像すると、援助国にも、援助機関にも、絶望的な貧困をすぐに根絶する力はなかった。実際、「国連開発の十年」というキャンペーンは冷笑の的であった。当時の人々がグローバルガバナンスという言葉を知っていたとしても、恥ずかしくて口に出せたか分からない。
21世紀の今日では、事情は違うはずである。経済学者のハイエクが経済的権利を標的にしたのは、高福祉は自らの信条に反するからであったろう。しかし、生存権をつうじて最低限度の健康な生活を保障することは人間の尊厳を守ることであり、人間の尊厳こそ人権の実質である。給付を頭ごなしに否定すべきではない。
人権を実現するには、そのためのメカニズムが整っているほうがよいのは確かである。アマルティア・センは、民主国では飢餓は起きない、という言説で知られる。
もしその政府が、選挙、自由な報道や検閲されない公然の批判を通じて公衆に責任を負うことになったとすれば、政府もまた――非難、そして最終的には否認を避けるために――飢饉を撲滅すべく最善を尽くす十分な理由を持つことだろう[25]。
同じことは、伝染病や犯罪にも言える。民主主義がガバナンスにとって重要であるという命題からは、少なくとも二つの結論が導き出される。一つは植民地では対策が遅れることである。植民地政府にとっては、本国政府との関係が最重要である。現地住民に対する関心は低く、情報収集や分析に思い込みや偏向が交じりやすい。独立を勝ち取ることによって、住民はようやく有権者となり、自分たちのガバナンスを持つことができる。奴隷制、モノカルチャー、虐殺、自然破壊などの害悪が植民地統治下では避けられない。
もう1点は、検閲を受けないニュースメディアの重要性である。センが指摘するのは、民主主義のもとでは政府を非難する野党が存在しており、それが政策を正す圧力となることである[26]。事実に基づく情報はデマや噂に対する有効なワクチンである。
内心の自由と表現の自由は報道の前提である一方で、進歩の必要条件でもある。飛行機、原子力、そしてロケットの技術は、いずれも民間での自由な研究開発がなければ、孵化し、巣立つことはなかった。仮に、独裁国家が官僚組織や政府資金を駆使して開発したようにみえても、実は自由な社会からスパイや連行によって盗まれたものである。表現の自由では、完全な真理に対してであっても、異議をさしはさむことには意味がある。そう断言したのはジョン・スチュアート・ミルであった。異議こそ逆に真理の根拠を明らかにし、真理を生き生きとしたものにするからである[27]。
実際、全体主義の国では、科学は政治に従属させられ、ゆがめられる。DNAの二重らせん構造の発見がノーベル賞を受けて十年がたった1960年代前半、ソビエト連邦ではルイセンコ学説というものが支配的地位を占めていた。この学説は発芽後に植物が獲得した形質が次世代に遺伝するというものである。トロフィム・ルイセンコは全連邦農業科学アカデミー総裁として君臨した。彼はマルクス・レーニン主義の名を借りて、自説に従わない学者たちに弾圧を加え、逮捕までさせた。検閲と外国からの隔離がルイセンコ学説を生き永らえさせ、その権威が失墜したのは、擁護者であったニキータ・フルシチョフ共産党第一書記が失脚してからであった[28]。 以上が自由主義国家をモデルとしたナショナルガバナンスである。もちろん、世界の国々はすべてが自由主義国家というわけでない。異質な体制の国家をどう評価すればよいか? 非自由主義国家と自由主義国家との間では、戦争など、国際関係はどのようになりやすいか? 問われるべき問題は枚挙にいとまがない。
[1] James N. Rosenau, “Governance, Order, and Change in World Politics,” in James N. Rosenau and Ernst-Otto Czempiel, eds., Governance without Government: Order and Change in World Politics (New York: Cambridge University Press, 1992), p. 5.
[2] Emery Reves, The Anatomy of Peace, 9th ed. (New York: Harper & Brothers, 1946). バートランド・ラッセル、「戦争の防止」、モートン・グロッジンス、ユージン・ラビノビッチ編、『核の時代』、岸田純之助、高榎尭訳、みすず書房、1965年、96-103ページ。アルバート・アインシュタイン、『科学者と世界平和』、井上健訳、中央公論新社、2002年、11ページ。
[3] Hans J. Morgenthau, Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace, 5th ed. (New York: Alfred A. Knopf, 1973), p. 27.
[4] アダム・スミス、『諸国民の富 (一)』、大内兵衛、松川七郎訳、岩波書店、1959 年、98ページ。
[5] スミス、『諸国民の富 (一)』、120ページ。
[6] F・A・ハイエク、『法と立法と自由Ⅱ 社会正義の幻想』、新版、篠塚慎吾訳、春秋社、1987年、162ページ
[7] アダム・スミス、『諸国民の富 (三)』、大内兵衛、松川七郎訳、岩波書店、1965年、56ページ
[8] ハイエク、『法と立法と自由Ⅱ 社会正義の幻想』、11ページ。
[9] スミス、『諸国民の富 (三)』、57ページ。
[10] アリストテレス、『政治学』、牛田徳子訳、京都大学学術出版会、2001年、 53ページ。
[11] F・A・ハイエク、「真の個人主義と偽りの個人主義」、嘉治元郎、嘉治佐代訳、F・A・ハイエク『個人主義と経済秩序』、春秋社、2008年、17ページ。
[12] ハイエク、『法と立法と自由Ⅱ 社会正義の幻想』、14ページ。
[13] ハイエク、『法と立法と自由Ⅱ 社会正義の幻想』、10ページ。
[14] ダロン・アセモグル、デヴィッド・レイブソン、ジョン・リスト、『ミクロ経済学』、電子版、東洋経済新報社、2020年、317ページ。
[15] アダム・スミス、『諸国民の富 (四)』、大内兵衛、松川七郎訳、岩波書店、1966 年、5-224ページ。
[16] F・A・ハイエク、『法と立法と自由Ⅲ 自由人の政治的秩序』、新版、渡部茂訳、春秋社、1988年、67ページ。
[17] ハイエク、『法と立法と自由Ⅲ 自由人の政治的秩序』、68-69ページ。
[18] Article 5(3) of Consolidated version of the Treaty on European Union.
[19] ロバート・ノージック、『アナーキー・国家・ユートピア: 国家の正当性とその限界』、嶋津格訳、木鐸社、1992年。ハイエク、「真の個人主義と偽りの個人主義」、23-24ページ。
[20] ピエール・ジョゼフ・プルードン、『プルードン Ⅲ』、長谷川進、江口幹訳、三一書房、1971年、371-372ページ。
[21] ロバート・ケネディ、『13日間 キューバ危機回顧録』、毎日新聞社外信部訳、中央公論新社、2001年、97-98ページ。
[22] Ph・C・シュミッター、G・レームブルッフ、『現代コーポラティズム―団体統合主義の政治とその理論』、山口定監訳、木鐸社、1984年。
[23] イマヌエル・カント、「世界市民的見地における普遍史の理念」、福田喜一郎訳、『カント全集』、14巻、岩波書店、2000年、1-22ページ。
[24] ハイエク、『法と立法と自由Ⅱ 社会正義の幻想』、143-144ページ。
[25] アマルティア・セン、「講演 飢餓撲滅のための公共行動」、アマルティア・セン『貧困と飢饉』、黒崎卓、山崎幸治訳、岩波書店、2017年、302ページ。
[26] セン、「講演 飢餓撲滅のための公共行動」、302ページ。
[27] J・S・ミル、『自由論』、塩尻公明、木村健康訳、岩波書店、1971年、107-108ページ。
[28] ジョレス・メドヴェージェフ、『生物学と個人崇拝―ルイセンコの興亡』、現代思潮新社、2018年、349ページ。
© 2026 Ikuo Kinoshita