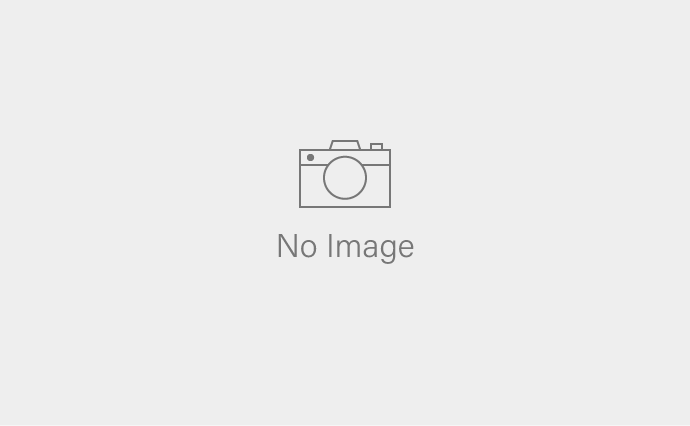『宋名臣言行録』の最後は王安石で飾りたい。
彼は花鳥風月の描写に長けた詩人だった。
王安石
月は花の影を移して欄干に上らしむ
(王安石、清水茂、『王安石』、岩波書店、1962年、p.76)
王安石
春風は自のずから江南の岸を緑にす
(王安石、清水茂、『王安石』、岩波書店、1962年、p.77)
蘇軾のような大胆なストーリー展開はないものの、細やかに自然の動きを捉ええた。
王安石
一鳥鳴かずして山更に幽なり
(王安石、清水茂、『王安石』、岩波書店、1962年、p.86)
鳥をまぶたの裏で想起させながら結局、鳴かせない演出は定家の「見渡せば花も紅葉もなかりけり浦の苫屋の秋の夕暮れ」と似た幽玄の境地だ。
王安石は耽美で終わる人でなく、社会の現実を直視せずにいられない人だった。民の貧困を描く詩は多い。しかし、白居易の「人、人を食らう」のような度肝を抜く句は生めず、閑適の詩人とみなされる。
こうした現実から目を背けない姿勢ゆえに、王安石は強く理想を求めた。歴史のなかの彼は新法派のリーダーとして教科書に登場する。新法派の革新官僚と守旧派の郷紳階級との対立は党争に発展し、北宋の衰退を招いたとされる。
新法が経済政策に関わるものだったことが不評の一因だった。ようやく王安石が再評価されたのは革命中国と高度成長期の日本だった。前者は地主階級への敵意が、後者は財界の地位向上が背景にあり、田沼意次の復権とも軌を一にした。
非難にも屈しなかった心のよりどころは『孟子』だった。王安石は孟子を理想主義の同志とみなし、「孟子」と題した詩を作った。
王安石
何ぞ妨げん 迂闊を嫌うを
故より斯の人有って寂寥を慰む
(王安石、清水茂、『王安石』、岩波書店、1962年、p.48)
「迂闊だなんて言われたってかまわない。孟子がいたんだから寂しくはない。」
この理想主義が彼を改革にこだわらせ、世間から頑固者やひねくれ者とそしられる原因になった。元来、経済政策は儒教の軽んずるところであり、保守派の本音は「余計なことをしてくれるな」だった。
朱熹は王安石の政敵だった司馬光を持ち上げ、王安石には悪意の筆誅を加えた。
朱子
王荊公、晩年、鐘山書院において、多く福建子の三字を写す。けだし呂恵卿に悔恨するものにて、恵卿のために陥れらるるを恨み、恵卿のために誤らるるを悔ゆるなり。山行するごとに多く恍惚として独言すること狂者のごとし。(朱熹、諸橋轍次、原田種成、『宋名臣言行録』、第3版、明徳出版社、1980年、p.143)
呂恵卿という部下に裏切られて引退し、その男の名前を書いたり、つぶやいたり狂人のようだった、というが、真実の王安石は花鳥風月を美しく詠んでいた。新法の功罪は私には評価しかねるが、王安石の執念と無念は理解できないわけでない。
ーー『宋名臣言行録』には納得できない点もあるが、論争的なところも魅力だ。